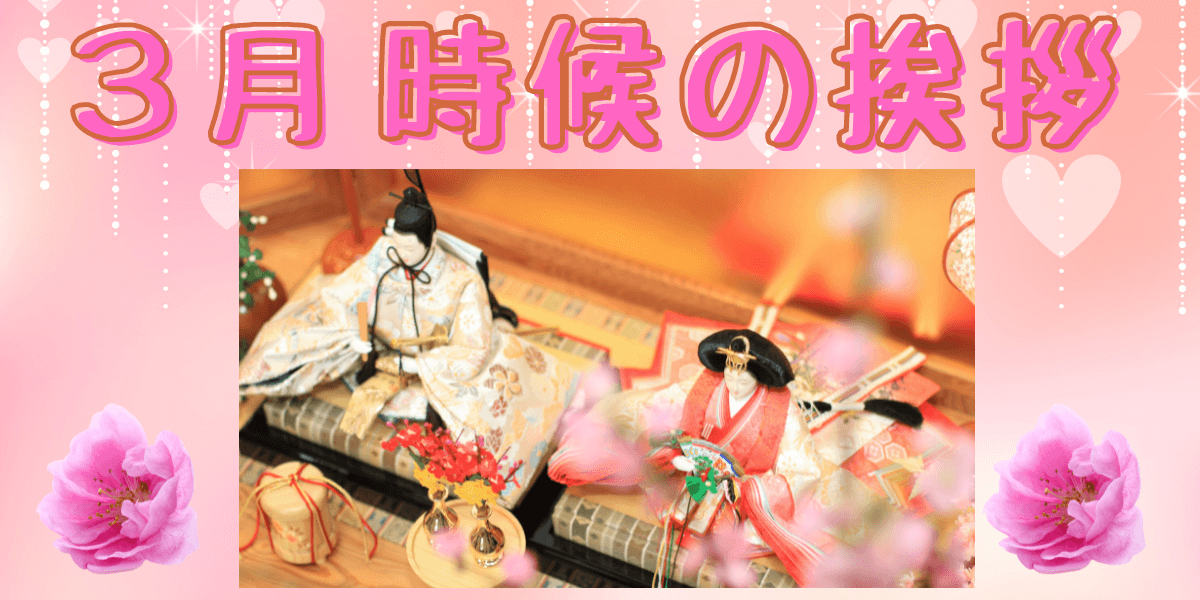この記事では、
3月に使える時候の挨拶と結びの言葉をご紹介します。
ビジネス関係と親しい人に出す、
3月の時候の挨拶と結びの言葉の例文もご参考ください。
いよいよ春本番、3月のはじまりです。
もの寂しげだった景色が、
花の色に彩られていくなか、
鳥や虫、私たちも活動的になる3月。
少しずつ世界が賑やかに動きはじめる季節です。
3月のはがきや手紙を送る相手に、
きらめく命の息吹を感じさせる季節感のある、
3月の季語を使った時候の挨拶を使用した方がよいでしょう。
その後に相手の健康や安否を気遣う言葉を書きましょう。
手紙を書くときに綺麗な手紙が書けずに悩んでいらっしゃる方がいたら、
別の記事で「きれいな手紙が書ける便箋と封筒」をご紹介しています。
👇
良かったら読んでみてください。
>綺麗な字が書ける便箋
目次
3月の異称:弥生(やよい)
3月の代表的な和風月名は、「弥生(やよい)」。
旧暦3月の呼び名でもある「弥生」は、
もともとは「いやおい」と読み、草木が
ますます生い茂るさまをあらわしています。
陽光とやわらかな春雨によって、
多くの植物が萌え出ずる時季であるため、この名前がつきました。
ほかにも3月に出すはがきや手紙の季語として、
百花繚乱(ひゃかりょうらん)となることにちなんで、
「花見月」や「花月」「桜月」といった美しい別名があります。
いずれにも、春を喜び、待ちわびた先人の思いが、
3月の季語に込められています。
いう3月の異称といえば、まず弥生ですね。
語源は、木草弥生月(きくさいやおいづき)が
変化したものだということです。「弥」や、「ますます」とか、「いよいよ」という意味ですから、
木や草がますます生い茂る月ということになります。その月に咲く代表的な花が季節の呼び名になることも多く、
桃月、桜月という呼び方もあります。そう、旧暦では、桜が咲くころですから、
花咲月(はなさきづき)、花見月ともいいました。桜のことを夢見草ともいいます。
そこから夢見月とも呼ばれるようになりました。
日に日に暖かくなり、
春を迎える喜びが、一番感じられる月です。新しい芽をふき、次々と花を咲かせる草木たち。
それにつられて、
私たちも、美しい夢を見ることができますね。引用
書名「美人の日本語」
作者「山下景子」
出版社「幻冬舎」
3月の昔の呼び名である和風月名を、
はがきや手紙の季語にして書き出しに使うと、
ひと味違った風流な時候の挨拶文になります。
3月の季語
早春(そうしゅん)の候
三寒四温(さんかんしおん)の候
弥生(やよい)の候
軽暖(けいだん)の候
浅春(せんしゅん)の候
啓蟄(けいちつ)の候
春分(しゅんぶん)の候
春暖(しゅんだん)の候
仲春(ちゅうしゅん)の候
3月の季語の読み方ですが、候は「こう」と読みます。
3月に咲く花:片栗(かたくり)

片栗(かたくり)の花は、
雪解けを待って野山でひっそりと淡紫色の花を咲かせます。
古くは、「かたかご」という名で万葉集にも登場しています。
籠(かご)が、傾いた感じで花が咲くからでしょう。
この花の根から片栗粉が作られていたのは有名です。
ユリ科 原産地 日本
花言葉「初恋」「きっといいことが…」
片栗(かたくり)の花は、
山野の湿気のある場所に群生します。
春を告げる花として万葉の昔から人々に愛されてきました。
花径は10センチから20センチ。
淡紫色の花は、花弁が反(そ)り返り、うつむいたように咲きます。
地中深くにある鱗茎から、
かつては貴重な澱粉(でんぷん)をとり、
片栗粉として利用されてきました。
ちなみに、現在、片栗粉として使用されているのは、
ほとんどが、ジャガイモからとった澱粉です。
『万葉集』にも登場する堅香子(かたかご)の花。
片栗(かたくり)の、名として知られています。
その名の由来はいろいろありますが、
傾いた籠(かご)のように、花が下向きに咲くからという説が有力です。
慎(つつ)ましさをたたえて、うつむき加減に咲いている姿。
でも、上に反り返った薄紅色の花びらからは、
春を迎えた喜びがあふれ出ているような気がします。昔は、この堅香子の地下茎(ちかけい)から、
良質の澱粉をとっていました。いわゆる「片栗粉」ですね。
今では、すっかり少なくなってしまって、
現在「片栗粉」として売られているのは、
ほとんどジャガイモのでんぷんだそうです。この堅香子、芽を出すまでに、7・8年かかるのだとか。
芽を出すと、その春のうちに花を咲かせます。
そして、枯れるとまた次の春まで、
地上からすっかり姿をけすのだそうです。花が咲いている期間は、1ヶ月あまり。
そのため、ヨーロッパでは、
「スプリング・エフェメル(春のはかない命)」と呼ばれているそうです。
もし、堅香子(かたかご)の花を見つけたら、
思い出してあげたいですね。引用
長い間、真っ暗な土の中で、
夢を見続けて、やっと咲かせた花だということを。
書名「花の日本語」
作者「山下景子」
出版社「幻冬舎」
3月の二十四節気:雨水・啓蟄・春分
3月のはがきの時候の挨拶は、
上旬、中旬、下旬によっても違ってきます。
それぞれ例文を交えて3月の季語の
はがきや手紙の書き方をご説明します。
まずは、はがきや手紙を出す日がいつごろか把握しましょう。
その上で、
以下に記載している3月の二十四節気の、
どの時期の季語に該当するかを確認しましょう。
雨水(うすい) :2月19日頃~3月5日頃
啓蟄(けいちつ) :3月6日頃~3月20日頃
春分(しゅんぶん):3月21日頃~4月4日頃
暖冬や冷夏があるように、
季節もその年によって移り変わる時期はさまざまです。
二十四節気の変わり目に「頃」としているのは、
その年によって季節感は異なるからです。
3月上旬の季語と時候の挨拶(雨水:2月19日頃~3月5日頃)
雨水(うすい)…
「暦便覧」には、
「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となれば也」とあります。
雪が雨に変わり、氷が解け始めて春の気配は歩みを強めます。
3月上旬のはがきや手紙の時候の挨拶には、
「三寒四温の候」「弥生の候」などの季語がふさわしいです。
3月の時候の挨拶を述べる場合は、
なるべく春の暖かさを表現する季語にして、
その年の暖かさの程度を考慮して選ぶのが良いでしょう。
そして、3月の時候の挨拶の後には、
相手の健康や安否を気遣う言葉を書きましょう。
3月の季語と時候の挨拶を使った例文:ビジネス関係
・早春の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
・三寒四温の候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。
・弥生の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
3月の季語と時候の挨拶を使った例文:親しい人
・日だまりにはもう草の芽が萌えたつ季節となりました。
・桃の節句も過ぎ、うららかな春の日が続いております。
・日ごとに暖かさを増し、風の色も春めいてまいりました。
・芳しい沈丁花の香りに、早くも春の到来を感じております。
・お雛祭りをお迎えになり、ますますお子様のお健やかな
ご成長が楽しみなことでございましょう。
3月中旬の季語と時候の挨拶(啓蟄:3月6日頃~3月20日頃)
啓蟄((けいちつ)…
「暦便覧」には、
「陽気地中に動き、ちぢまる虫、穴をひらき出れば也」とあります。
「驚蟄」とも書き、
「閉啓(へいけい)」というと小雪の頃、土の中に虫がこもること。
3月中旬のはがきや手紙の季語の時候の挨拶には、
「軽暖の候」「浅春の候」「啓蟄の候」を使用すると良いでしょう。
3月中旬は、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、
冬の寒さもやわらぎ、過ごしやすい時季がやってきます。
しかし、
日本列島は、東西に約3000km,東北に約2700km。
季節の巡りにも時間差があるので、3月の季語だけを見ると、
違和感を持つ言葉もありますが、誤りではありません。
3月の季語と時候の挨拶を使った例文:ビジネス関係
・軽暖の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
・浅春の候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。
・啓蟄の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
3月の季語と時候の挨拶を使った例文:親しい人
・春一番が吹き、いよいよ春も本番です。
・春光天地に満ちる季節となりました。
・春うらら、穏やかな毎日を過ごされていることでしょう。
・たらの芽を摘んで、少しほろ苦い春の味覚をいただいています。
・暑さ寒さも彼岸までと申しますが、まだお寒い日が続いております。
3月下旬の季語と時候の挨拶(春分:3月21日頃~4月4日頃)
春分(しゅんぶん)…
「暦便覧」には、「日天の中を行て昼夜等分の時也」とあります。
太陽が真東から昇って真西に沈み、
昼夜の時間がほぼ等しくなります。
春分の日とは、「自然を賛え、生物を慈しむ日」
煩悩の彼岸から知恵の彼岸へ。
それを目指して精一杯生きるのが、
波羅密多(はらみた)の意味だそうです。
3月下旬は、日ごとにあたたかさも増し、
「春めく」から「春本番」へ。
太陽の光が植物の成長を促し芽吹きや、
気温の高まりを感じさせる時期。
3月は菜の花が盛りを迎え、
ようやくあたたかくなったと思いきや、
寒々とした雨が降り続くことがあります。
つまり、
開花を催す雨、つまり「催花雨(さいかう)」が、
「菜花雨(なばなあめ)」に転じ、「菜種梅雨(なたねづゆ)」に
なったともいわれています。
はがきや手紙の季語の時候の挨拶として、
「春分の候」「春暖の候」「仲春の候」と
いった言葉を使用すると良いでしょう。
3月の季語と時候の挨拶を使った例文:ビジネス関係
・春分の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
・春暖の候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。
・仲春の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
3月の季語と時候の挨拶を使った例文:親しい人
・菜種梅雨の静かな午後、いかがお過ごしでしょうか。
・ひと雨ごとに木々の若芽が伸び、春めいてまいりました。
・遠山は紫にかすみ、春の息吹きがたちこめているようです。
・花見月といわれるだけあって、
行楽のお誘いにも心はずむ季節となりました。
・春眠暁を覚えずとはよくいったもので、
ついつい朝寝坊してしまいがちな心地よい気候となりました。
3月の時候の挨拶:結びの言葉
3月のはがきや手紙の結びの言葉は、
3月の季語に合わせた挨拶を入れたあと、
「お健やかな日々をお過ごしください。」「ご自愛専一に。」
「お身体にお気をつけください。」などの言葉で結びます。
3月の時候の挨拶:結びの言葉(ビジネス関係)
・春分の候、ご自愛専一に、益々ご活躍ください。
・仲春の候、貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
・季節の変わり目ですが、くれぐれもご自愛ください。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
・末筆ながら、貴社の一層のご発展をお祈り申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
・末筆ながら、一層のご躍進のほどご祈念申し上げます。
まことに略儀ではございますが、書中をもちまして
ご通知申し上げます。
・時節柄、くれぐれもご自愛ください。
今後とも、よろしくご指導のほどをお願い申し上げます。
社員皆々様には一層のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
・これからもご指導ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈り申しあげます。
3月の時候の挨拶:結びの言葉(親しい人)
・春の日差しのもと、お健やかな日々をお過ごしください。
・春光を受けて、ますますのご発展をお祈りしております。
・天も地も躍動の季節、さらなるご活躍をお祈りいたします。
・春風とともに、皆様にお幸せが訪れますようお祈りいたします。
・四月からの新生活、元気にがんばってください。
でも、あまりご無理なさいませんようご自愛くださいませ。
3月の時候の挨拶を使った「初節句のお祝いのお礼状」例文
日ごとに暖かさを増し、風の色も春めいてまいりました。
お父さん、お母さんお元気ですか。
いただいたひな人形のおかげで、家の中が
パッと華やいだ雰囲気になりました。
愛樺もこのところつかまり立ちをするようになりました。
子供の成長は本当に早いものですね。
夏休みには、
信二さんの休みが一週間とれますので、親子でそちらに行きます。
いまからとても楽しみです。
お父さんももう若くはないのだから、
仕事は無理をしないで早めに切り上げるようにしてね。
では、お元気で。
お礼まで。
まとめ
この記事では、
3月に使える時候の挨拶と結びの言葉をご紹介しました。
3月は、年度末。
入学、進級、進学、就職、転勤、と
たくさんの人たちが、新しいステージに踏み出す季節です。
はがきや手紙の文章を書くときは、
3月ならではの季語を入れた、趣のある
時候の挨拶を届けられるといいですね。