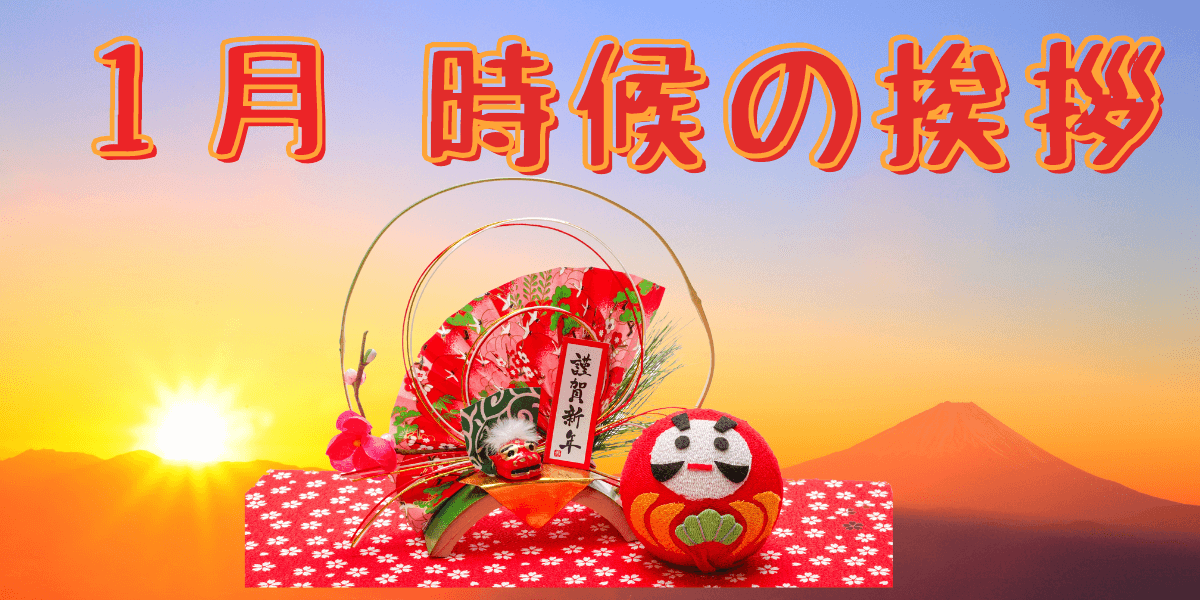新年のご挨拶や寒中見舞い、仕事始めのメールやお手紙など、1月は何かと「時候の挨拶」を使う機会が多い時期です。
とはいえ、「どんな言葉を選べばよいのか分からない」「失礼のないように書きたい」と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、1月にふさわしい時候の挨拶を【上旬・中旬・下旬】の時期別に整理し、【ビジネス】【友人】【学校・保護者】など用途別に使える例文をご紹介します。
また、季語の意味や手紙の結びの表現もあわせて解説。
大切な相手に思いが伝わる、心のこもった文章を書くためのヒントが満載です。
手紙を書くときに綺麗な手紙が書けずに悩んでいらっしゃる方がいたら、
別の記事で「きれいな手紙が書ける便箋と封筒」をご紹介しています。
👇
良かったら読んでみてください。
目次
1月の時候の挨拶とは?
1月は新しい年の始まりであり、あいさつ文や手紙、年賀状などで「時候の挨拶」を用いる場面が増える時期です。
時候の挨拶とは、その時期の季節感や天候にふれつつ、相手を気遣う定型的な文章のこと。
形式的な印象があるかもしれませんが、正しく使えば丁寧な印象を与え、気持ちがしっかり伝わります。
まずは1月にふさわしい時候の挨拶の基礎を確認しましょう。
1月の異称「睦月」の由来
「睦月(むつき)」は、1月を表す和風月名の一つ。
時候の挨拶や手紙の書き出しに季節感を添えるために使われることがあります。
その由来には諸説あり、日本の古くからの風習や人々の暮らしを反映しています。
- 「睦月」は「親しむ」「仲睦まじい」という意味から、正月に家族や親戚が集う月とされる
- その他の説:稲の実りを表す「実月」、物忌みの月という意味の「厳月」など
- 現代の文章で使う場合は「睦月の折」などと柔らかく取り入れるのが◎
例文:
「睦月の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。」
1月の代表的な季語一覧
1月には、新春や雪、寒さをテーマにした多くの季語があります。
手紙やメールに取り入れることで、相手に季節感や情緒を届けることができます。
以下では、1月にふさわしい代表的な季語と、その使い方を紹介します。
自然や気候を表す季語
- 新春(しんしゅん)
- 厳寒(げんかん)
- 小寒(しょうかん)
- 大寒(だいかん)
- 寒の入り(かんのいり)
- 冬日和(ふゆびより)
活用例:
「厳寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
行事や風習を表す季語
- お正月
- 初夢
- 七草
- 成人の日
- 初詣
- 松の内
活用例:
「初春のお慶びを申し上げますとともに、本年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。」
1月の二十四節気とその意味
日本の暦には、季節の移り変わりを24の節目で表す「二十四節気」があります。
1月には「小寒」と「大寒」という2つの節気が含まれており、いずれも冬の厳しさを表す大切な言葉です。
時候の挨拶にも頻繁に登場します。
小寒(しょうかん)|1月5日ごろ
意味・特徴:
「寒の入り」とも呼ばれ、本格的な寒さが始まる時期。年始の挨拶にふさわしい季語です。
例文:
「小寒の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。」
大寒(だいかん)|1月20日ごろ
意味・特徴:
一年の中で最も寒さが厳しいとされる時期。健康を気遣う表現とともに使うのが一般的です。
例文:
「大寒の折、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。」
1月の時候の挨拶|時期別の書き出しと結びの言葉
1月は新年の始まりとして特別な意味を持つ月。
時候の挨拶も「お正月ムード」が漂う上旬から、「寒さが本格化する」下旬へと、時期によって適した表現が変わってきます。
ここでは、1月を上旬・中旬・下旬に分けて、シーンに応じた書き出しと結びの言葉をご紹介します。
上旬(1日〜10日頃)
年賀状や新年の挨拶状など、もっとも丁寧でおめでたい表現が好まれる時期です。
希望や感謝を伝える内容が自然にマッチします。
書き出し例(ビジネス・フォーマル向け)
- 「謹んで新年のお喜びを申し上げます。」
- 「初春の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
- 「新春とは申せ、厳しい寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。」
結びの言葉例
- 「本年も変わらぬご厚情のほど、よろしくお願い申し上げます。」
- 「皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。」
- 「寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛ください。」
中旬(11日〜20日頃)
正月行事がひと段落し、日常が戻り始める頃。
年始の挨拶としてはやや落ち着いたトーンが好まれ、寒さや仕事始めを気遣う内容が適しています。
書き出し例
- 「寒さもいよいよ本格的になってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」
- 「寒中お見舞い申し上げます。」
- 「小寒の候、皆様におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。」
結びの言葉例
- 「まだまだ寒い日が続きますが、くれぐれもお体にお気をつけくださいませ。」
- 「本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。」
- 「向春の折、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。」
下旬(21日〜31日頃)
一年で最も寒さが厳しい「大寒」の時期にあたる下旬は、体調への気遣いや春の兆しを意識した表現が効果的です。
寒中見舞いや時候のご挨拶にふさわしい言い回しを選びましょう。
書き出し例
- 「大寒の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」
- 「寒さがひとしお身にしみる毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。」
- 「厳寒の折、皆様にはお変わりなくお過ごしのことと存じます。」
結びの言葉例
- 「春の訪れが待ち遠しい季節、どうぞご自愛のうえお過ごしくださいませ。」
- 「風邪など召されませぬよう、どうぞご健康にご留意ください。」
- 「まだ寒さが続きますが、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。」
1月の時候の挨拶|相手別の文例集
1月の時候の挨拶は、送る相手や状況に応じて表現を使い分けることが大切です。
ここでは、ビジネス関係・友人とのカジュアルなやりとり・学校や保護者向けの丁寧な挨拶文を、それぞれ具体的な文例とともにご紹介します。
書き出しと結びの言葉を押さえるだけで、ぐっと印象がよくなります。
ビジネス文書向け
ビジネス文書では、礼儀を重んじた丁寧な表現が求められます。
新年の挨拶として適した時候の言葉や、寒さを気遣う一文を添えると、形式的ながらも温かみのある印象を与えることができます。
書き出し例
- 謹んで新年のお慶びを申し上げます。
- 初春の候、貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
- 厳寒の折、皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます。
結びの言葉例
- 本年も変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
- 寒さ厳しき折、皆様のご健康とご発展をお祈り申し上げます。
- 今後とも一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
友人・LINE向け
親しい友人やLINEなどでのカジュアルなやり取りには、あまり堅苦しくならない自然な表現が適しています。
時候の挨拶にちょっとした近況報告や気遣いの一言を添えると、心のこもったメッセージになります。
書き出し例
- あけましておめでとう!今年もよろしくね。
- 新しい年が始まったね。寒いけど元気にしてる?
- 今年も寒さに負けず、楽しく過ごそうね!
結びの言葉例
- また近いうちに会おうね。今年もいっぱい遊ぼう!
- 体に気をつけて、元気な一年にしよう!
- 寒い日が続くけど、風邪ひかないようにね!
学校・保護者向け
学校関係や保護者宛ての文書では、丁寧で安心感のある表現が求められます。
堅すぎず、親しみのあるトーンで季節感と気遣いを伝えることがポイントです。
書き出し例
- 新年を迎え、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。
- 今年もどうぞよろしくお願いいたします。寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。
- 小寒の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
・寒冷の候 寒く冷たい時期になりました。
・松飾りも取れ普段の生活が戻ってまいりました。
・厳しい寒さが続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
・冬の冷たい風が吹く頃、皆様お障りもなくお過ごしですか。
・松の内の賑わいも過ぎ、寒さもなお厳しくなってまいりました。
結びの言葉例
- 本年も変わらぬご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
- 厳しい寒さが続いておりますので、どうぞご自愛くださいませ。
- ご家族皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
・大寒の候、ご自愛専一に、益々ご活躍ください。
・降雪の候、貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
・季節の変わり目ですが、くれぐれもご自愛ください。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
・末筆ながら、貴社の一層のご発展をお祈り申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
・末筆ながら、一層のご躍進のほどご祈念申し上げます。
まことに略儀ではございますが、書中をもちまして
ご通知申し上げます。
・時節柄、くれぐれもご自愛ください。
今後とも、よろしくご指導のほどをお願い申し上げます。
社員皆々様には一層のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
・これからもご指導ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈り申しあげます。
PTA・保育園・子ども会向け|1月の時候の挨拶【特化文例】
書き出し例
・新しい年を迎え、保護者の皆様にはお健やかにお過ごしのこととお喜び申し上げます。
・寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。昨年は格別のご協力を賜り、誠にありがとうございました。
・初春の候、子どもたちの元気な笑顔に、私たち職員一同も新たな気持ちで一年を迎えております。
・冬休みが明け、子どもたちのにぎやかな声が園内に戻ってまいりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
・新学期が始まり、寒さの中にも子どもたちの元気な姿が見られ、私たちも励まされております。
結びの言葉例
・本年も皆さまと一緒に、子どもたちの健やかな成長を見守ってまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
・寒さが一段と増してまいりますが、ご家庭でも体調管理にご留意ください。
・今後ともPTA活動へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
・ご家族皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
・今年も地域や保護者の皆さまと連携し、子どもたちの笑顔あふれる一年となりますよう努力してまいります。
1月に咲く花:梅(うめ)

「東風(こち)ふかば香(にお)ひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」
菅原道真(すがわらみちざね)公の、心を感じとった梅は、
はるか太宰府(だざいふ)まで飛んでいって咲いたという。
『菅公の飛梅』伝説にちなんだ花言葉。
梅は、寒さの中で咲く気品高い花です。
花言葉「忠実」「気品」
梅の花は、早春、葉に咲き立って花を咲かせます。
紅色の他、白色、淡紅色のものもあり、
5弁または重弁の花は、気品高く芳香があり、
万葉の昔から鑑賞用として愛されてきました。
果実を梅干しなどに利用するようになったのは、
江戸時代以降といわれています。
比較的温暖な気候を好み、
野梅性、豊後性、杏性、紅梅性など多くの園芸品種があります。
そこで、にわか仕込みの不確実な学問は「梅の木学問」、
生長がはやいけれども、大木にはならないそうです。
梅は、生長がはやいけれども、大木にはならないそうです。
そこで、にわか仕込みの不確実な学問は「梅の木学問」、
成り上がりのお金持ちは「梅の木分限(うめのきぶげん)」といいます。
春告草(はるつげぐさ)の異名を持ち、春の季語となっている梅ですが、
「万葉集」では、雪とともに詠(うた)われることも多かったようです。
『今日振りし 雪に競ひて 我がやどの 冬木の梅は 花さきにけり』
万葉集(大伴家持)大変たくさんの異称を持つ梅ですが、
その中のひとつに「好文木(こうぶんぼく)」があります。
昔、晋(しん)の武帝が、学問に励むと梅の花が咲き、
引用
怠(おこた)ると、しおれていたという故事からきた名前です。
書名「花の日本語」
作者「山下景子」
出版社「幻冬舎」
1月の時候の挨拶を使った「成人式のお祝い」例文
全国的な寒波というニュースでございますが、
ご当地はいかがでございますか?
年の暮れに買った福寿草の蕾がとても可愛らしく開きました。
雅子様、成人式おめでとうございます。
美しく成人されたあなたの晴れ姿、
目を細めていらっしゃるご両親の顔が目に浮かぶようでございます。
大学生活もなかなか忙しいようですが、
大きな人生の節目として、成人の日をお迎えください。
心ばかりですが、お祝いのしるしを同封します。
なにかの足しにしてくださいね。
健康に気をつけ、
学業第一にがんばってください。
風邪が流行っています。どうぞ風邪とは仲良しになられませんように、
お元気にお過ごしくださいませ。
まずはお祝いまで。
まとめ
この記事では、
1月に使える時候の挨拶と結びの言葉をご紹介しました。
1月は、1年をスタートする大事な時期です。
元旦(1日)にはじまり、
書き初め(2日)や鏡開き(11日)。
成人の日(第2月曜日)など、多くの行事があります。
文章を書くときは、
時候の挨拶や1月ならではの季語を入れて、
趣のあるはがきや手紙を相手に届けたいものです。
こうやって考えてみますと日本は本当に細かいところまで、
伝統や風習がある国なのだなと改めて気づかされます。
四季があるだけで珍しいのにも関わらず、
その四季の中にも様々な季節があって名前があり、
季語や時候の挨拶が変わるなんて他の国には、
なかなかないのではないでしょうか?
七十二候などの、季語の言葉も織り交ぜながら、
1月の時候の挨拶の参考にしてくださいね。
- 1月の時候の挨拶
- 2月の時候の挨拶
- 3月の時候の挨拶
- 4月の時候の挨拶
- 5月の時候の挨拶
- 6月の時候の挨拶
- 7月の時候の挨拶
- 8月の時候の挨拶
- 9月の時候の挨拶
- 10月の時候の挨拶
- 11月の時候の挨拶
- 12月の時候の挨拶
- 年中使える時候の挨拶