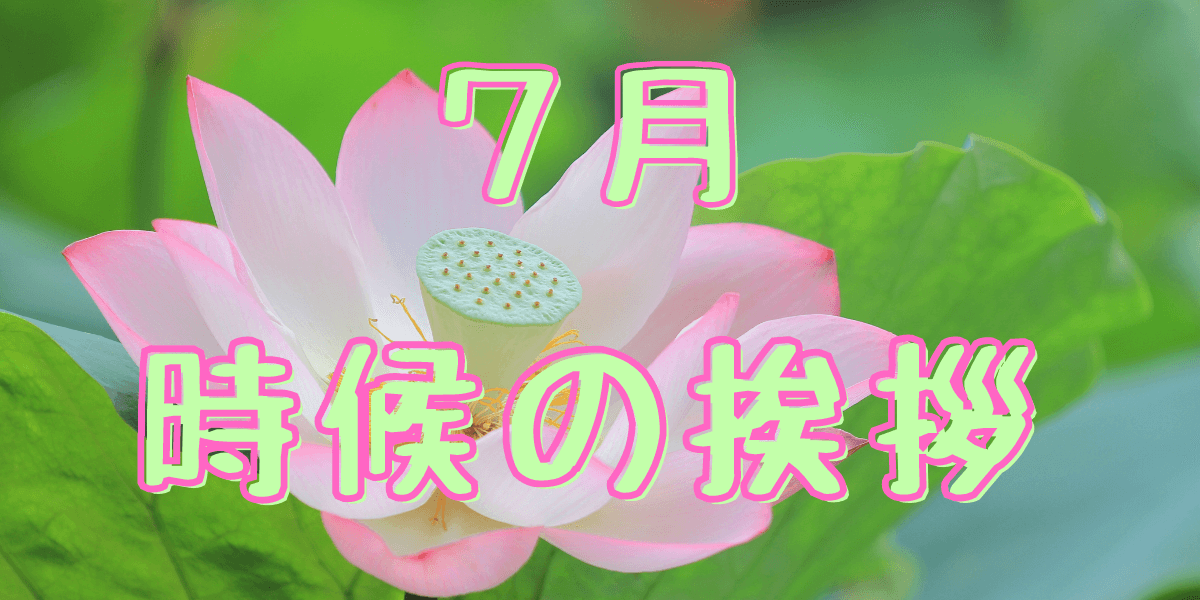7月は夏本番を迎え、暑中見舞いやお礼状、季節のご挨拶など、手紙を書く機会が増える時期です。
丁寧な時候の挨拶や結びの言葉を添えることで、相手に季節感と心遣いを伝えることができます。
この記事では、7月にふさわしい季語や結びの言葉、ビジネスや親しい相手への例文など、手紙に役立つ表現をわかりやすく紹介します。
基本マナーと共に、すぐに使える例文もご用意しましたので、ぜひご活用ください。
手紙を書くときに綺麗な手紙が書けずに悩んでいらっしゃる方がいたら、
別の記事で「きれいな手紙が書ける便箋と封筒」をご紹介しています。
👇
良かったら読んでみてください。
きれいな手紙が書ける!秘密の下敷き付き便箋と封筒【実例あり】
目次
時候の挨拶とは?7月に手紙を書く前に知っておきたい基本
時候の挨拶とは、日本の手紙文化において季節を感じさせる冒頭の言葉です。
7月は暑中見舞いやお礼状など、丁寧な印象を与える文章が求められます。
時候の挨拶の意味と役割
時候の挨拶は、季節感を伝えることで相手との心の距離を縮める役割があります。
書き出しの印象を決める大切な要素です。
夏の季節が訪れ、暑い日々が続く中で、
我々の間でよく耳にするのが7月の時候の挨拶です。
この時期に相手に対して述べる挨拶は、
ただ単に暑さを伝えるだけではありません。
この記事では、7月の時候の挨拶に込められた意味や背景について探ってみましょう。
7月に手紙を送る場面とタイミング
・暑中見舞い(7月7日頃〜8月上旬)
・お中元のお礼
・暑さを気遣う手紙 など
7月とはいえ、
梅雨や台風などの気象条件が大きく影響を与えるため、
挨拶にはそれに対する配慮が求められます。
また、暑い季節にふさわしい軽快な挨拶や、夏の風物詩を取り入れた挨拶もあります。
夏の季節にふさわしい挨拶を心得、さまざまな場面で人々との交流を深めてください。
季語とは、自然や季節の移り変わりを表す言葉であり、
日本の俳句や短歌において重要な要素となっています。
7月にはどのような季語があるのか、その意味や由来についても探っていきましょう。
また、時候の挨拶は、季節や天候に合わせた挨拶のことであり、
人々とのコミュニケーションを円滑にするために重要です。
7月の季語とその意味
7月は本格的な夏の到来を告げる季節です。
季語には日本の自然や暮らしが反映されており、手紙に彩りを加える効果があります。
霖雨(りんう)の候
梅雨晴れ(つゆばれ)の候
仲夏(ちゅうか)の候
猛暑(もうしょ)の候
盛夏(せいか)の候
酷暑(こくしょ)の候
大暑(たいしょ)の候
炎暑(えんしょ)の候
三伏(さんぷく)の候
7月の季語の読み方ですが、候は「こう」と読みます。
七十二候から見る7月の季節感
温風至(おんぷういたる)7月7日頃
蓮始開(はすはじめてひらく)7月12日頃
桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)7月23日頃
梅雨はまだ残るものの、本格的な夏の到来、7月がやってきました。
山開きや海開き、夏祭りと、7月は暑さを飛ばす行事がつづきます。
七十二候が大暑の次候、
「土潤いて溽し暑し(つちうるおいてむしあつし)」。
この「溽(じょく)」の字には、
湿気が多くて暑い、といった意味があります。
日本の夏独特の絡みつくような暑さは、
「溽暑(じょくしょ)」とも表現します。
上旬・中旬・下旬別|主な季語一覧
7月のはがきの時候の挨拶は、
上旬、中旬、下旬によっても違ってくるので、
それぞれ例文を交えて7月の季語の書き方をご紹介します。
【上旬】盛夏、青葉、向日葵
【中旬】蝉しぐれ、熱帯夜
【下旬】夕立、夏の雲、土用
まずは、はがきや手紙を出す日がいつごろか把握しましょう。
その上で、以下に記載している7月の二十四節気の
どの時期の季語に該当するかを確認しましょう。
夏至(げし) :6月22日頃~7月 6日頃
小暑(しょうしょ) :7月 7日頃~7月22日頃
大暑(たいしょ) :7月23日頃~8月 7日頃
暖冬や冷夏があるように、
季節もその年によって移り変わる時期はさまざまです。
今の季節の7月は例年と比べて暖かいのか、
暑いのか、移り変わりの早さなどを考慮して、
はがき手紙の季語と時候の挨拶を選びましょう。
上旬・中旬・下旬の季語と時候の挨拶+例文
7月の上旬・中旬・下旬それぞれにふさわしい季語を使った挨拶文をご紹介します。
夏至(げし)…
「暦便覧」には、
「陽熱至極しまた、日の長きのいたりなるを以て也」とあります。
7月上旬のはがきや手紙の時候の挨拶には、
「霖雨の候」「梅雨晴れの候」「仲夏の候」などの季語がふさわしいです。
その年の7月の気温を考慮して、季語を選んで書くと良いでしょう。
ビジネス向け 季語の使い方例文
・霖雨の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
・梅雨晴れの候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。
・仲夏の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
親しい人向け季語の使い方例文
・待望の夏がいよいよやってまいりました。
・梅雨も明け、海や山の恋しい季節となりました。
・七夕の短冊にお願いごとをしたのがなつかしい季節となりました。
・長引く梅雨に、さわやかな夏空の待ち遠しい日々が続いております。
・憂うつな梅雨も明け、
青空がひときわ爽快に感じられる今日この頃です。
7月中旬の季語と時候の挨拶
小暑(しょうしょ)…
「暦便覧」には、
「大暑来れる前なれば也」とあります。
この日を前後に梅雨が明け、
太陽が照り付けるようになって本格的な暑気入りとなります。
蓮の花など水辺の花が咲き始め、蝉の合唱も、もうそろそろです。
7月中旬のはがきや手紙の季語と時候の挨拶には、
「猛暑の候」「盛夏の候」「酷暑の候」の季語を
使用すると良いでしょう。
7月中旬は、「蓮始めて開く(はすはじめてひらく)」。
各地の池や沼で蓮の華が見頃を迎えるころです。
「早起きは三文の徳」のことわざ通り、
可憐な花が開いていく様子は早朝にしか見ることができません。
季語の「蓮始めて開く」の蓮の花は、
夜明けとともに開き、昼過ぎにはつぼみ、
また翌日には咲く。
というサイクルを3日間繰り返します。
儚(はかな)くも開花後4日で花は散りますが、生命力は旺盛。
2千年以上地中に眠っていた種から発芽し、
「古代蓮」が、今も大きく花開いています。
季節の巡りにも時間差があるので、7月の季語だけを見ると
違和感を持つ言葉もありますが、誤りではありません。
ビジネス向け 季語の使い方例文
・猛暑の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
・盛夏の候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。
・酷暑の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
親しい人向け季語の使い方例文
・盛夏のみぎり、皆様にはますますご活躍のことと存じます。
・近くの公園の池で、睡蓮が美しい花を咲かせておりました。
・暑さ厳しき折ではございますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
・日の暮れかかる頃には、夕顔が白い花を咲かせる季節となりました。
・窓辺につるした風鈴の音に、ひとときの涼を楽しんでいるこの頃です。
7月下旬の季語と時候の挨拶
大暑(たいしょ)…
「だいしょ」ともいいます。
「暦便覧」には、
「暑気いたりつまりたるゆへなれば也」とあります。
1年で最も気温の高い季節。
「大いに暑い」の名前通り、
1年でもっとも7月は気温が高く、
暑さも厳しくなる節気を迎えました。
蒸し暑さと大雨が降り、夏の土用に入ります。
7月下旬のはがきや手紙の季語の時候の挨拶として、
「大暑の候」「炎暑の候」「三伏の候」といった季語を使用すると良いでしょう。
ビジネス向け 季語の使い方例文
・大暑の候、貴社いよいよご盛栄のこととお慶び申し上げます。
・炎暑の候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。
・三伏の候、貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。
親しい人向け季語の使い方例文
・夕立ちのあとの涼風が心地よい今日この頃です。
・炎暑続きの毎日に、突然の白雨で心地よい涼を得られました。
・ふるさとの夏祭りがなつかしく思い出される季節となりました。
・土用に入りましてから、
ますます猛暑しのぎがたい日々が続いております。
・連日寝苦しい夜が続いておりますが、
お障りなくお過ごしでいらっしゃいますか。
7月に使える結びの言葉と例文
結びの言葉は、手紙の印象を左右する重要なパーツです。
相手との関係性やシーンに合わせて使い分けましょう。
7月の季語の挨拶をはがきや手紙に入れたあと、
「どうかご自愛専一に。」「お身体にお気をつけください。」
「お健やかな日々をお過ごしください。」などの言葉で結びます。
ビジネスシーンで使える結びの言葉
手紙の締めくくりには、相手の健康や発展を祈る「結びの言葉」を添えることで、礼儀正しい印象になります。
【例文】
・季節の変わり目ですが、くれぐれもご自愛ください。
貴社の更なるご発展を心よりお祈り申し上げます。
・末筆ながら、貴社の一層のご発展をお祈り申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
・末筆ながら、一層のご躍進のほどご祈念申し上げます。
まことに略儀ではございますが、
書中をもちましてご通知申し上げます。
・時節柄、くれぐれもご自愛ください。
今後とも、よろしくご指導のほどをお願い申し上げます。
社員皆々様には一層のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
・これからもご指導ご鞭撻のほどをお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈り申しあげます。
親しい相手に使える結びの言葉
・今年の夏の暑さは格別です。どうかご自愛専一に。
・暑さ厳しき折から、くれぐれも健康にはご留意ください。
・猛暑の折、皆様のご無事息災を心よりお祈りいたしております。
・どうか夏バテなどなさりませんように、
おからだにお気をつけください。
・これからいっそう暑さは厳しくなります。
くれぐれもご自愛ください。
7月の時候の挨拶を使った手紙の文例集
具体的な文例を参考にすれば、手紙の完成度がぐっと上がります。
ビジネス用と親しい人向け、両方の例文をご紹介します。
ビジネス向け例文
拝啓
盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
〜(本文)〜
暑さ厳しき折、何卒ご自愛のほどお願い申し上げます。
敬具
親しい人向けの例文
○○さん
梅雨も明けて、夏本番の陽気になってきましたね。
元気にしていますか?
私は最近、向日葵畑を見に行ってきました。
暑さに気をつけて、素敵な夏を過ごしてくださいね!
プラスで差がつく!7月の文化・花・言葉
一言添えるだけで、手紙がグッと印象深くなります。
「文月」や「露草」など、季節を感じさせる表現をご紹介します。
【7月の和風月名】文月(ふみづき)の意味と時候の挨拶
👇
文月(ふみづき)の意味と由来
7月の異称といえば、
「文月(ふみづき)」ですが、語源も諸説あります。
7月の昔の呼び名である和風月名を、
はがきや手紙の季語にして書き出しに使うと、
ひと味違った風流な時候の挨拶文になります。
七夕月(たなばたづき)、七夜月(ななよづき、または たなやづき)、
そして、愛逢月(めであいづき)。
どれも七夕にちなんだ異称です。
文月(ふみづき)の語源も諸説ありありますが、
一説には短冊や歌や字を書いた七夕の行事から、
文披月(ふみひろげづき、または、ふみひらきづき)、
それが転じて文月となったと言われています。
七月といえば、七夕だったのですね。
また、この月に咲く花の名前か蘭月(らんげつ)、女郎花月(おみなえしづき)…。
稲穂のふくらみを見る月でもあったので、穂見月(ほみづき)。
そして、旧暦では秋の始まりの月だったことから秋初月(あきはづき)。
現代版愛逢月はこれからが夏本番。
ロマンテックな出逢いを予感させるこの言葉…。
さあ、どんな愛に逢えるでしょう。
引用
書名「美人の日本語」
作者「山下景子」
出版社「幻冬舎」
7月に咲く花:露草(つゆくさ)

露草の表現方法
涼しげな藍色(あいいろ)の花びらが2枚と、
白くて小さな花びらがもう1枚。
真ん中に黄色い雄しべ。
青い花びらに朝露をためたこの花を見ると、
心が洗われる思いです。
夏の風物詩として、親しまれ愛されている花です。
露草の花言葉「尊敬」「懐かし間柄」
露草(つゆくさ)は、
道端や草地など、いたるところで見られる一年草です。
花は日の出とともに開き、
昼過ぎにはしぼんでしまいます。
朝露のようにはかなげな花です。
花弁は3枚。
内2枚は大きく青色で1枚は小さく白い。
6個の雄しべがありますが、
花粉を出すのは前に突き出た2本だけで、
黄色い葯(やく)が目立つ中央の雄しべは飾りです。
この花の青い汁は友禅の下絵描きに用いられます。
昔は露草(つゆくさ)のことを、月草(つきくさ)と呼んでいました。
露草の花を摺(す)り付けて、
布などに色を着けていたので「着草(つきくさ)」。
これに「月」という漢字を当てたものです。
染めた色が色落ちしやすかったことや、
早朝に咲き午後にはしぼんでしまうこから、
はかなさの象徴として、和歌に詠まれてきました。
梅雨の終わりごろから咲き始めるのに、
秋の季語になっているのも、そのせいかもしれません。
でも、決して、はかない花ではありません。
「苞(ほう)」と呼ばれる花を包んでいる葉の中には、
ちゃんと明日の蕾が眠っているのです。
1日でしぼんでしまう花は、花びらを散らすことなく、
次の花の栄養になるのだとか。
翌朝になると、また目のさめるような青い花を見せてくれます。
もし、虫が来てくれなくても大丈夫。
特に長く伸びた2本の雄しべと雌しべが、
しぼむ時に、くるくると巻きながら、自力で受粉するのだそうです。
日本の至るところで見かける花だと思っていたら、
なんとその仲間は世界の至るところに分布しているということです。
引用
書名 「花の日本語」
作者「山下景子」
出版社「幻冬舎」
特別な手紙例:誕生日祝いの送り状(7月バージョン)
ふるさとの夏祭りが、
なつかしく思い出される季節となりました。
皆様には、お変わりなくお過ごしのことと存じます。
さて、もうすぐお父様のお誕生日。
今年は古希を迎えられるとのこと。
おめでとうございます。
本当に若々しいお父様ですが、
どうかますますお元気でお過ごしになられますように、
そして私たちをご指導くださいますようお願い申し上げます。
本日、ささやかですがお祝いの品をお送りしました。
お気に召していただければ幸いです。
お身体を大切にされて、
さらにお祝いを重ねられることをお祈り申し上げます。
今年の夏の暑さは格別です。
くれぐれもご自愛くださいませ。
7月の時候の挨拶 Q&A
Q1:暑中見舞いの時期はいつから?
A:梅雨明け後(7月7日頃)から立秋前(8月7日頃)までが一般的です。
Q2:ビジネス文書に季語は必要ですか?
A:必須ではありませんが、時候の挨拶があると丁寧で好印象です。
Q3:文例の中で自由にアレンジしていい?
A:もちろんOKです。相手との関係や内容に合わせてカスタマイズしてください。
Q4:漢字が難しい季語は使うべき?
A:一般的に使われているものは問題ありませんが、不安な場合はひらがなや分かりやすい表現に置き換えると良いでしょう。
まとめ
7月の手紙には、相手の体調を気遣い、夏の情緒を織り交ぜた言葉を選ぶことが大切です。
時候の挨拶と結びの言葉を上手に使って、心のこもった文章を届けましょう。