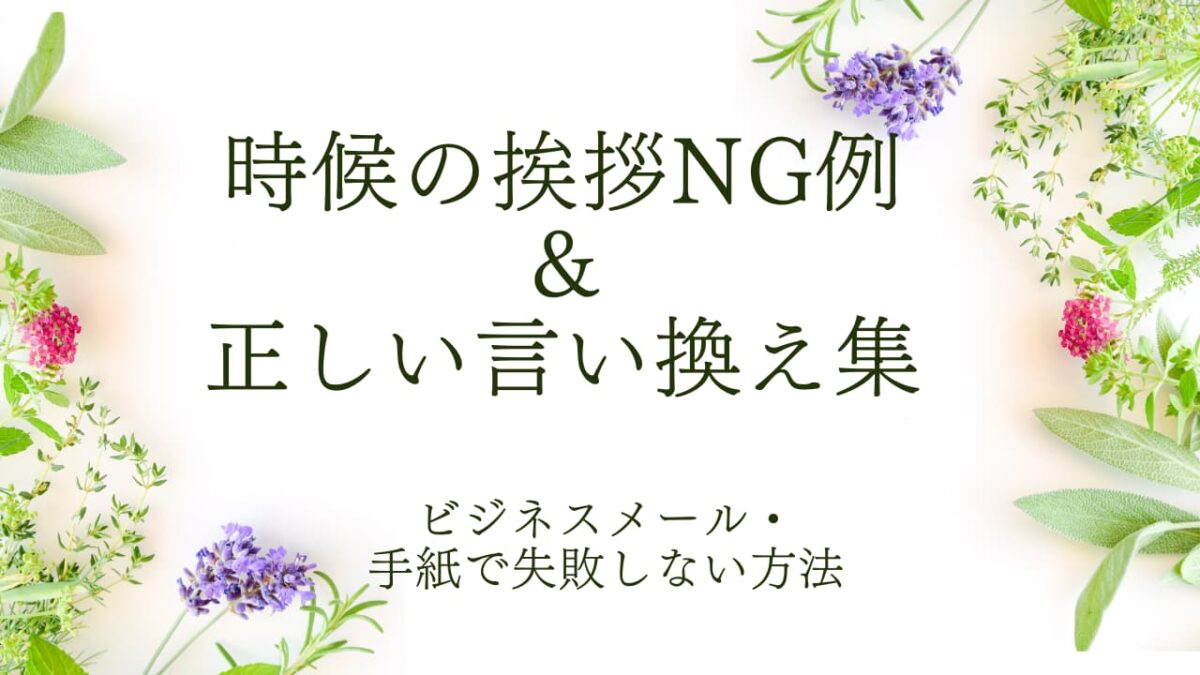時候の挨拶は、ビジネスメールや手紙で季節感を伝える大切なマナーです。
しかし、間違った表現を使うと「季節感がずれている」「形式的すぎる」といった印象を与えてしまうことがあります。
本記事では、誤用しやすい時候の挨拶NG例と、その正しい言い換え表現を季節別に解説。
具体例やメール文のテンプレートも紹介しているので、今日からすぐに活用できます。
一年を通して安心して使える「万能型の時候の挨拶」を厳選して紹介しています。
季節を問わず使える定番フレーズから、ビジネス・プライベートどちらにも応用できる例文まで網羅。
文章作成に迷ったときの“お守りフレーズ集”として活用できます。
👇
ビジネスシーンに特化した時候の挨拶フレーズと例文をまとめています。
取引先へのメールや上司への報告・依頼など、堅めの場面でそのまま使える正しい書き方を紹介。
信頼感を与える文章に仕上げたい方におすすめです。
👇
ビジネスメールで使える時候の挨拶と例文集|取引先・上司への正しい書き方
目次
- 1 時候の挨拶とは?|ビジネスメール・手紙での基本マナー
- 2 誤用しやすいNGフレーズ一覧表
- 3 よくある時候の挨拶NG例と注意点
- 4 NG例の正しい言い換え表現集
- 5 季節別おすすめフレーズ集|春夏秋冬の表現と実用例
- 6 よくある質問(FAQ)
- 6.1 Q1. 「暑中お見舞い申し上げます」と「盛夏の候」の違いは?
- 6.2 Q2. 季節感が合わない場合はどうする?
- 6.3 Q3. メールの冒頭だけで季節を表現するには?
- 6.4 Q4. NG例を使った文章例は?
- 6.5 Q5. 「時候の挨拶」と「季節の挨拶」はどう違う?
- 6.6 Q6. 季節を問わず使える無難な表現は?
- 6.7 Q7. メールで季節表現が長くなりすぎる場合は?
- 6.8 Q8. 取引先が海外の場合はどうすればいい?
- 6.9 Q9. 手紙で書くときとメールで書くときの注意点は?
- 6.10 Q10. 季節感を入れすぎると失礼になることはある?
- 6.11 Q11. 季節に合わせた挨拶のタイミングはどのくらい前後OK?
- 7 まとめ|失敗しない時候の挨拶のコツ
時候の挨拶とは?|ビジネスメール・手紙での基本マナー
時候の挨拶とは、手紙やメールの冒頭で季節感を伝える定型表現です。
ビジネスでは、季節感を取り入れることで文章に柔らかさや礼儀正しさが加わり、相手に好印象を与えます。
しかし、誤った表現や季節に合わない言い回しを使うと逆効果になることもあります。
本章では、時候の挨拶の基本的な役割と、間違いやすいポイントを解説します。
時候の挨拶の目的と役割
- 季節感を伝えることで文章が柔らかくなる
- 礼儀やマナーを示す
- ビジネスメールで信頼感を高める
誤用しやすい理由と具体例
季節感に敏感でないと適切な表現が選べない
時候の挨拶は、使える時期が数週間〜1か月程度と短いものが多く、タイミングを誤ると違和感のある文章になります。
例えば:
- 「早春の候」は本来2月末〜3月初旬の挨拶 → 4月に使うと「もう春真っ盛りなのに早春?」と不自然。
- 「残暑の候」は立秋(8月7日頃)以降に使う挨拶 → 7月に書くと間違い扱いされます。
📌 注意点
ビジネス文書では「おかしな日本語を使っている」と相手に感じさせると、信頼性に関わるため、使用時期を必ず確認することが大切です。
個人的な感覚で挨拶を書いてしまう
「今日は暖かいから春っぽい表現にしよう」といった自分の体感ベースで時候の挨拶を選ぶのは誤用につながります。
例えば:
- 1月の暖かい日に「春暖の候」と書いてしまう → 暦上はまだ冬なので不適切。
- 11月でも暑さが残る年に「残暑の候」と書く → 暦的には「晩秋の候」「初冬の候」を使うのが正解。
📌 注意点
挨拶文は「暦」に基づくのが基本。
気温やその日の天候ではなく、二十四節気や暦上の季節に合わせることが重要です。
地域差や気候に合わない表現を使いやすい
日本は南北に長いため、季節の感じ方に地域差があります。
- 北海道では4月でも雪が残るのに「陽春の候」を使うと違和感。
- 沖縄では11月でも半袖の気候なのに「厳冬の候」を使うと不自然。
また、海外の取引先に送る場合も注意が必要です。
- 例えばオーストラリアに「盛夏の候」と書くと、現地は真冬なのでちぐはぐに。
📌 注意点
国内では「暦」に合わせて使えば失礼にはなりませんが、地域や海外とのやり取りでは、時候の挨拶を避けてシンプルな健康や繁栄を願う表現に切り替えるのが無難です。
- 時候の挨拶は「暦」が基準。実際の気温や体感に流されないこと。
- 「この言葉はいつからいつまで使えるのか?」を意識すると誤用を防げる。
- 地域差や相手の立場を考え、場合によっては汎用的な表現に置き換えるのが安全。
誤用しやすいNGフレーズ一覧表
| 時期(目安) | 誤用しやすい表現 | 誤用の理由 | 正しい表現例 |
|---|---|---|---|
| 1月(真冬) | 春暖の候 | 暖かい日があっても暦上は冬 | 厳冬の候/新春の候 |
| 2月(初春) | 盛夏の候 | 季節が真逆 | 立春の候/早春の候 |
| 3月下旬〜4月(春本番) | 早春の候 | 3月上旬までの表現であり遅い | 陽春の候/春暖の候 |
| 6月(梅雨) | 盛夏の候 | 盛夏は7月中旬以降の表現 | 梅雨の候/初夏の候 |
| 7月(梅雨明け前) | 残暑の候 | 残暑は立秋(8月7日頃〜)以降 | 盛夏の候/酷暑の候 |
| 8月上旬(立秋前) | 初秋の候 | 暦の上では秋でも実感に合わず違和感大 | 盛夏の候/残暑の候(立秋以降) |
| 10月(秋深まり) | 初秋の候 | 初秋は8〜9月の挨拶で時期遅れ | 秋涼の候/錦秋の候 |
| 11月下旬(初冬) | 残暑の候 | 暦も気候も合わない | 晩秋の候/初冬の候 |
| 12月(冬本番) | 春暖の候 | 季節感が真逆 | 師走の候/寒冷の候 |
よくある時候の挨拶NG例と注意点
時候の挨拶は便利ですが、使い方を間違えると「季節感が合っていない」と違和感を与えてしまうことがあります。
特にビジネスシーンでは、適切な表現を選ぶことが信頼につながります。
ここでは、よく使われるものの誤用しやすい表現と、その注意点を解説します。
「暑さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか」
- NGポイント:5月や9月など、真夏以外の時期に使うと不自然。
- 解説:「暑さ厳しき折」は7月〜8月の盛夏に限定して使える表現。初夏や残暑には別の言い回しが必要です。
- 例文(NG):梅雨入り前の6月に使ってしまうケース。
件名:ご挨拶
○○株式会社 山田様暑さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。
先日はお忙しい中ありがとうございました。
→ 正しい表現例: 「初夏の候」「盛夏の候」など、時期に応じた挨拶に置き換えると自然です。
「寒さが身にしみる今日この頃」
- NGポイント:秋口や春先など、寒さが厳しくない時期に使うと違和感。
- 解説:この表現は11月後半〜2月ごろの冬本番に適しています。
- 例文(NG):10月上旬など、まだ寒くない時期に使用。
寒さが身にしみる今日この頃、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
→ 正しい表現例: 秋口なら「清秋の候」、12月なら「初冬の候」、1月なら「厳冬の候」と使い分けると適切です。
「梅雨の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」
- NGポイント:地域によって梅雨の時期が異なるため、実際の天候とずれる場合がある。
- 解説:梅雨入りや梅雨明けの表現を使う際は、気候の実情を確認することが重要です。
- 例文(NG):梅雨明け後の真夏に使ってしまうケース。
梅雨の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
→ 正しい表現例: 梅雨入りなら「入梅の候」、梅雨明け後なら「盛夏の候」と言い換えると正確です。
NG例の正しい言い換え表現集
誤用されやすいフレーズを避けるためには、季節や暦に即した正しい表現を知っておくことが重要です。
ここでは代表的なNGフレーズと、その正しい言い換え例を「そのまま使えるメール文」とともに紹介します。
「暑さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか」 → 「盛夏の候」
- 誤用理由
「暑さ厳しき折」はカジュアル寄りで、口語的な響きが強くビジネス文書ではやや軽い印象を与えます。
一方「盛夏の候」は暦の上で夏が本格化する 7月中旬〜8月上旬 に使える正式な季語です。
件名:ご挨拶
○○株式会社 山田様
盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
先日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
「寒さが身にしみる今日この頃」 → 「初冬の候」
- 誤用理由
「寒さが身にしみる〜」は日常的で私信向きの表現。ビジネス文書ではくだけすぎてしまいます。
「初冬の候」は 11月下旬〜12月上旬 に使える格式のある表現で、年末挨拶の始まりにも適します。
件名:年末のご挨拶
株式会社○○ 鈴木様
初冬の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
本年中は格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。
来年も変わらぬお付き合いのほどお願い申し上げます。
「梅雨の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」 → 「梅雨明けの候」
- 誤用理由
「梅雨の候」は 6月中旬〜7月初旬 の雨が続く時期に使います。
梅雨明け後に使ってしまうと違和感を与えるため、「梅雨明けの候」へ言い換えるのが正解です。
件名:ご挨拶
○○株式会社 田中様
梅雨明けの候、貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
酷暑の折、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
「春らしい陽気となりましたが」 → 「陽春の候」
- 誤用理由
「春らしい陽気〜」は丁寧ではあるものの、やや日常会話的で改まった場には不向き。
「陽春の候」は 4月頃 の明るい春を示す正式な時候の挨拶です。
件名:新年度のご挨拶
○○株式会社 佐藤様
陽春の候、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
新年度を迎えるにあたり、引き続きご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。
「秋も深まり〜」 → 「錦秋の候」
- 誤用理由
「秋も深まり〜」は情緒的で良い表現ですが、私信寄りで口語的。
「錦秋の候」は 10月下旬〜11月中旬、紅葉が美しい季節に最適なビジネス表現です。
件名:業務連携のご相談
株式会社○○ 高橋様
錦秋の候、貴社におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
さて、本日は新規プロジェクトに関するご相談でご連絡差し上げました。
後日、詳細をお打ち合わせさせていただければと存じます。
季節別おすすめフレーズ集|春夏秋冬の表現と実用例
時候の挨拶を自然に使いこなすためには、季節ごとの定番フレーズを把握しておくことが重要です。
「春暖の候」や「盛夏の候」といった言葉は、一見すると似ているようですが、それぞれ使用できる時期やニュアンスが異なります。
本章では、春・夏・秋・冬に分けておすすめのフレーズを紹介。
ビジネスメールで安心して使えるテンプレート例文と、使用時の注意点もあわせて解説します。
春(3月〜5月)
フレーズ例
- 早春の候(2月下旬〜3月上旬)
- 春暖の候(3月中旬〜4月)
- 陽春の候(4月〜5月)
使用の注意点
- 「早春の候」は、まだ肌寒さが残る時期に適しています。
- 「陽春の候」は日差しが暖かくなる頃に使うと自然です。
例文(ビジネスメール)
件名:ご挨拶
○○株式会社 佐藤様
春暖の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
夏(6月〜8月)
フレーズ例
- 初夏の候(6月上旬)
- 盛夏の候(7月中旬〜8月上旬)
- 酷暑の候(8月頃、暑さが厳しい時期)
使用の注意点
- 「初夏の候」は梅雨入り前後に使うと自然。
- 「盛夏の候」「酷暑の候」は夏本番に使うのが基本です。
例文(ビジネスメール)
件名:お世話になっております
○○株式会社 山田様
盛夏の候、皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。
暑さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。
秋(9月〜11月)
フレーズ例
- 初秋の候(9月上旬)
- 清秋の候(10月頃、空気が澄んだ秋らしい時期)
- 晩秋の候(11月頃、冬に近い晩秋の時期)
使用の注意点
- 「初秋の候」は残暑が残る9月初旬に適しています。
- 「清秋の候」は秋晴れの爽やかな時期に。
- 「晩秋の候」は木枯らしが吹く頃に使用すると自然です。
例文(ビジネスメール)
件名:ご挨拶
○○株式会社 高橋様
清秋の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
冬(12月〜2月)
フレーズ例
- 初冬の候(11月下旬〜12月上旬)
- 厳冬の候(1月、最も寒い時期)
- 余寒の候(2月、寒さが残る時期)
使用の注意点
- 「初冬の候」は年末の挨拶文にも適しています。
- 「厳冬の候」は真冬の時期に限定して使用しましょう。
- 「余寒の候」は立春後(2月上旬〜下旬)に使うのが正解です。
例文(ビジネスメール)
件名:年末のご挨拶
○○株式会社 田中様
初冬の候、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
本年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
💡 まとめポイント
- 季節のフレーズは「使える期間」が限定されている
- ビジネスでは 1〜2文にまとめてシンプルに使うのが基本
- 季節の後に「貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます」といった定型を続けると自然に仕上がる
よくある質問(FAQ)
時候の挨拶は、季節感や礼儀を伝える重要な文章ですが、「どの表現を使えばいいのか」「メールと手紙で違いはあるのか」と迷う方も多いでしょう。
本章では、ビジネスパーソンからよく寄せられる疑問をQ&A形式で詳しく解説。
NG例の修正方法や季節に合った表現、具体的なメール文例も紹介しています。
これを参考にすれば、文章の印象を格段にアップさせることができます。
Q1. 「暑中お見舞い申し上げます」と「盛夏の候」の違いは?
回答
暑中お見舞いは、主にハガキや手紙で使う個人的な季節の挨拶です。
一方、盛夏の候はビジネス文書やメールで正式に使える表現で、文章に格式と季節感を兼ね備えています。
テンプレート例
件名:ご挨拶
○○株式会社 山田様
盛夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
先日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございました。
Q2. 季節感が合わない場合はどうする?
回答
季節に合わない表現は避けることが大切です。
「暑さ厳しき折」や「寒さが身にしみる今日この頃」などは、時期を間違えると不自然に感じられます。
無難な表現としては、
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
のように、季節に左右されず使える定型文を選ぶと安心です。
テンプレート例
件名:ご挨拶
○○株式会社 佐藤様
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
Q3. メールの冒頭だけで季節を表現するには?
回答
冒頭に季節感を表す一文を入れるだけで、文章全体の印象が柔らかくなります。
形式ばらず自然に取り入れることがポイントです。
テンプレート例
平素よりお世話になっております。初秋の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
先日はご対応いただき、誠にありがとうございました。
Q4. NG例を使った文章例は?
回答
NG例文は季節や表現が不適切で、相手に違和感を与えやすいです。
正しい表現に置き換えることで、文章の印象を格段に向上させることができます。
NG例文
暑さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか。
修正例文
盛夏の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
Q5. 「時候の挨拶」と「季節の挨拶」はどう違う?
回答
「時候の挨拶」は文章の冒頭で季節感を伝える表現全般を指し、ビジネスメールや手紙で使われます。
「季節の挨拶」は個人的な手紙やハガキで季節にちなんだ言葉を添える表現で、よりカジュアルです。
テンプレート例
時候の挨拶(ビジネス向け)
盛夏の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
季節の挨拶(個人向け)
暑中お見舞い申し上げます。
Q6. 季節を問わず使える無難な表現は?
回答
ビジネス文書では、季節に左右されない表現が便利です。
- 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
- 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます
これらは年間を通して安心して使えます。
テンプレート例
件名:ご挨拶
○○株式会社 鈴木様
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃よりご厚情を賜り、誠にありがとうございます。
Q7. メールで季節表現が長くなりすぎる場合は?
回答
長すぎる時候の挨拶は文章が硬く感じられるため、1行程度にまとめるのがおすすめです。
季節感を示す単語+相手への挨拶だけで十分です。
テンプレート例
初夏の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
Q8. 取引先が海外の場合はどうすればいい?
回答
海外の取引先には、日本独特の時候の挨拶は理解されにくいため、簡潔に季節感を伝える表現が望ましいです。
テンプレート例
Spring greetings. I hope this message finds you well.
Thank you for your continued support.
Q9. 手紙で書くときとメールで書くときの注意点は?
回答
手紙では文字数や文章の体裁がより重視されるため、季節表現を丁寧に書くのが一般的です。
メールでは簡潔さを優先し、冒頭1文に時候表現を入れるだけでも十分です。
テンプレート例
手紙:初冬の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
メール:初冬の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
Q10. 季節感を入れすぎると失礼になることはある?
回答
個人的な挨拶やメールの本文で季節感を強調しすぎると、相手によっては形式ばった印象を与える場合があります。
ビジネスでは冒頭で季節感を簡潔に示すだけが無難です。
テンプレート例
盛夏の候、貴社ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
Q11. 季節に合わせた挨拶のタイミングはどのくらい前後OK?
回答
時候の挨拶は季節の前後1ヶ月程度までなら違和感なく使えます。
例えば「初夏の候」は5月下旬〜6月上旬まで、「盛夏の候」は7月中旬〜8月上旬が目安です。
テンプレート例
初夏の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
まとめ|失敗しない時候の挨拶のコツ
時候の挨拶は、季節感に合わせて正しい表現を選ぶことが大切です。
本記事で紹介したNG例と正しい言い換え表現、季節別フレーズを押さえれば、ビジネスメールや手紙で失敗することはありません。
文章に柔らかさと礼儀をプラスし、信頼感を高めるためのコツを覚えておきましょう。
・一年を通して安心して使える「万能型の時候の挨拶」を厳選して紹介しています。
季節を問わず使える定番フレーズから、ビジネス・プライベートどちらにも応用できる例文まで網羅。
文章作成に迷ったときの“お守りフレーズ集”として活用できます。
👇
・ビジネスシーンに特化した時候の挨拶フレーズと例文をまとめています。
取引先へのメールや上司への報告・依頼など、堅めの場面でそのまま使える正しい書き方を紹介。
信頼感を与える文章に仕上げたい方におすすめです。
👇