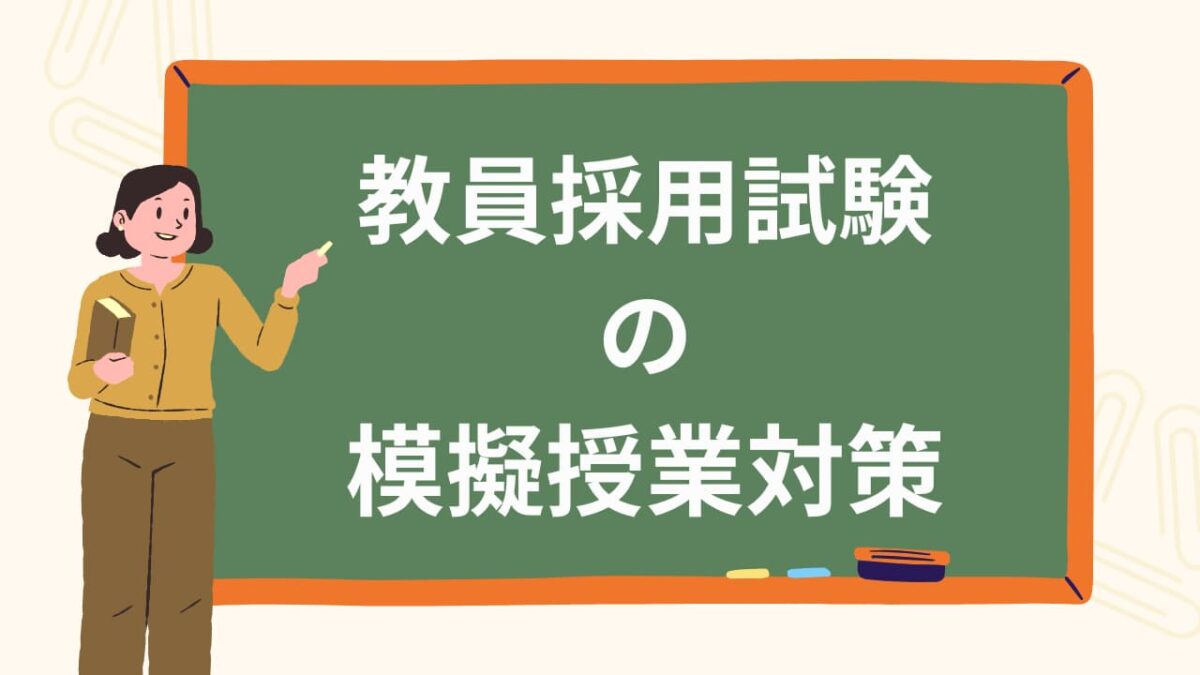教員採用試験の大きな山場となる「模擬授業」。
短い時間の中で授業構成、指導力、表現力などを評価されるため、多くの受験生が不安を感じます。
特に「どのように構成すればいいのか」「時間配分はどうするのか」「評価基準はどこにあるのか」という疑問は共通です。
本記事では、模擬授業の基本から実践的なテクニック、よくある失敗例、合格するための具体的な工夫まで徹底解説します。
例文を交えて解説しているので、初めて挑戦する方でもすぐに活用できます。
模擬授業だけでなく、教員採用試験の面接対策 も合否を左右します。
面接官がチェックする視点や回答例については別記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
教員採用試験の面接対策|合格する答え方・質問例・練習法を徹底解説
目次
- 1 模擬授業とは?基本を押さえよう
- 2 模擬授業の基本構成
- 3 時間配分のコツ
- 4 面接官が評価するポイントと基準
- 5 面接官が評価するポイントと基準
- 6 模擬授業対策の実践方法
- 7 受験生がつまずきやすいポイントと解決策
- 8 よくある質問(FAQ)
- 8.1 Q1. 模擬授業で沈黙が起きたらどうすればいいですか?
- 8.2 Q2. 模擬授業は暗記しないとダメですか?
- 8.3 Q3. 板書の字の上手さは評価されますか?
- 8.4 Q4. 実際の授業のように小道具を使ってもいいですか?
- 8.5 Q5. 緊張で声が震えてしまいます。どうすればいいですか?
- 8.6 ⏱️ ステップ1(10秒):深呼吸で整える
- 8.7 ⏱️ ステップ2(15秒):身体に力を入れて抜く
- 8.8 ⏱️ ステップ3(15秒):ハミング&小声
- 8.9 ⏱️ ステップ4(20秒):ポジティブ第一声リハーサル
- 8.10 Q6. 生徒役が思ったように反応してくれないときは?
- 8.11 Q7. 授業の導入で何を話せばよいか分かりません。
- 8.12 Q8. 時間が余ってしまった場合はどうすればいいですか?
- 8.13 Q9. 逆に時間が足りない場合はどうすればいいですか?
- 8.14 Q10. 声の大きさはどれくらいを意識すればいいですか?
- 8.15 Q11. 授業中に板書が間違ってしまったらどうすればいいですか?
- 9 まとめ
模擬授業とは?基本を押さえよう
模擬授業は、教員採用試験における「指導力の総合テスト」と言えます。
筆記試験では測れない授業運営力や、生徒を引き込む発問力、教師らしい立ち居振る舞いを評価する場です。
ここを理解せずにただ台本を暗記して挑むと、面接官の目には「授業らしさ」が伝わらず不合格に直結します。
まずは模擬授業の目的や形式を正しく把握しましょう。
模擬授業の目的
模擬授業は「教師としての実践力」を見るために行われます。
知識量ではなく、限られた時間で「生徒をどう学びに引き込むか」が重要です。
例:
- 学習課題を分かりやすく提示できるか
- 生徒が考える余白を残せるか
- 学びを次につなげる言葉をかけられるか
NG例:専門用語ばかりを並べて「説明」だけで終わる授業。
出題の形式とパターン(小学校・中高の違い)
模擬授業には「課題提示型」「自由設定型」の2種類があります。
- 小学校:道徳・国語・算数などで、身近な題材を使うケースが多い
- 中学校・高校:英語・数学など専門教科の学習活動を想定されるケースが多い
例題:
「小学校算数:割合の導入を10分で」
「中学校英語:関係代名詞を用いた会話練習」
面接官が見ているポイント
- 授業構成:導入・展開・まとめが一貫しているか
- 発問力:「考えさせる問い」になっているか
- 板書:整理されているか、見やすいか
- 姿勢・声量:教師としての信頼感があるか
チェックリスト
☑ 生徒役が参加したくなる導入になっているか
☑ 時間内で課題が完結しているか
☑ 板書や説明に無駄がないか
模擬授業の基本構成
模擬授業の構成は「導入→展開→まとめ」という基本形を守ることが合格の第一歩です。
特に導入で生徒の興味を引き、展開で学習活動を明確にし、最後にまとめで振り返る流れを意識すると「授業らしさ」が出ます。
1. 導入(アイスブレイク・課題提示)
- 目的
生徒の関心を引き、「学びたい!」と思わせる雰囲気をつくる。
- 工夫ポイント
- 身近な話題や体験を使う(買い物・スポーツ・SNSなど)。
- 今日の授業のゴールを一言で提示。
- 笑顔や声の抑揚で「場を温める」。
- 良い例 「みなさん、スーパーで“半額シール”を見たことありますよね?
今日はその“値引き”を使って、割合の仕組みを考えていきましょう。」
- NG例 「今日は割合の勉強をします。」(淡々として興味を引けない)
- 板書・指示例
- 板書:「今日のめあて:セールの値引きから割合を学ぼう」
- 指示:「ノートの上に“今日の課題”と書いてください」
2. 展開(学習活動の工夫・発問の仕方)
- 目的
生徒が考え、参加しながら理解を深める時間。
- 工夫ポイント
- 段階的発問で「考えやすい問い」をつなげる。
- 「考える → 答える → まとめる」の流れを繰り返す。
- 生徒の答えを想定して、褒めたり補足を入れる。
- 例(算数:割合の授業)
- 「5,000円のジャケットが20%引きです。割引額はいくらですか?」
- 「では、支払う金額はいくらでしょうか?」
- 「もし30%引きならどうなりますか?」
- 生徒の反応を想定したフォロー
- 「20%って、どんな意味かな? → 100のうちの20だよね。」
- 「引き算と掛け算、どちらで求めるのがわかりやすい?」
- 板書・指示例
- 板書:「5000円 × 20% = 1000円(割引額)」
- 指示:「計算式をノートの左側に、答えを右側に書きましょう」
3. まとめ(振り返り・次につなげる一言)
- 目的
学んだ内容を整理し、「できた!」という達成感と次への意欲を与える。
- 工夫ポイント
- 授業のゴールに立ち返って確認する。
- 「日常生活で使える」視点を提示。
- 生徒に振り返りの言葉を言わせる設定も効果的。
- 良い例 「今日の学びは『割引はもとの値段の割合で計算できる』ということでした。
次にスーパーに行ったとき、自分で割引額を計算してみましょう。」
- NG例 「これで授業を終わります。」(振り返りがなく、学びが定着しない)
- 板書・指示例
- 板書:「まとめ:割引額=もとの値段 × 割合」
- 指示:「今日のまとめをノートの下に赤で書きましょう」
総合ポイント
- 「導入」で心をつかみ、
- 「展開」で思考を深め、
- 「まとめ」で達成感を与える。
この3つの流れを意識することで「授業らしさ」が伝わり、面接官の評価も高まります。
時間配分のコツ
模擬授業は「短時間で評価される」ため、時間配分が合否を左右します。
一般的には10分〜15分で構成されることが多く、導入・展開・まとめの比率を意識することで安定した授業運営が可能になります。
模擬授業の時間枠と特徴
- 10分型
- 短い分「導入をコンパクトに」し、展開を中心に。
- 例:導入2分 → 展開6分 → まとめ2分
- 15分型
- やや余裕があり、活動を広げたり発問を1つ増やせる。
- 例:導入3分 → 展開9分 → まとめ3分
👉 「導入:展開:まとめ=2:6:2」の黄金比
- 導入に時間をかけすぎると展開が浅くなる。
- まとめを省くと「授業」ではなく「説明」で終わってしまう。
時間オーバーを防ぐ工夫
- リハーサル時にストップウォッチを使用
- 1回目:普通に通して時間を計る。
- 2回目:それぞれの場面で「1分オーバーしたらどこを削るか」を決めて練習。
- 「圧縮バージョン」を用意
- まとめを1分で言える形にしておく。
- 例:「今日の学びは“割合はもとの数にかける”ことでした。次に買い物のとき試してください。」
時間不足を防ぐ工夫
- 補助問題を準備
- 生徒役が早く答えた場合に使える。
- 例:ジャケットの20%引きの後に「では30%引きなら?」と追加。
- 問いを広げる
- 「他の考え方はあるかな?」と仮想生徒に投げかけることで自然に時間調整が可能。
模擬授業タイムスケジュール例(10分型)
- 導入(2分)
- 「セールで値引きを見たことある?」と問いかけ、今日の課題を提示。
- 板書:〈今日のめあて〉「割引を通して割合を考えよう」
- 展開(6分)
- 発問1:「5,000円のジャケットが20%引き。割引額は?」
- 発問2:「支払う金額は?」
- 板書:式と答えを整理、色分け。
- 補助問題(時間が余ったら):「30%引きなら?」
- まとめ(2分)
- 「今日の学びは『割引=もとの値段×割合』」
- 板書:「まとめ」欄に赤字で整理。
- 一言:「次にスーパーに行ったとき、自分で計算してみよう」
ポイント
- 授業の「軸(導入→展開→まとめ)」は崩さず、状況に応じて時間を前後に調整。
- 面接官は「時間の使い方=授業運営力」と見ている。
面接官が評価するポイントと基準
模擬授業の合否を分けるのは、教科知識以上に「授業運営力」と「教師らしさ」です。
面接官は単なる説明ではなく、「この人に教わりたい」と思える授業を求めています。
面接官が評価するポイントと基準
1. 教師としての立ち居振る舞い
- 姿勢
- 背筋を伸ばし、堂々とした立ち姿で授業を進める。
- 授業開始時に黒板の前で静止し、しっかりアイコンタクトをとることで「授業が始まる雰囲気」をつくる。
- 声の大きさ
- 教室の一番後ろまで届く声量を意識する。
- 重要な言葉は声のトーンを上げ下げして強弱をつける。
- アイコンタクト
- 左・中央・右を順に見渡し、全体に語りかけている印象を与える。
- 生徒役がいなくても「その場にいる」想定で視線を送る。
👉 評価基準:安心感・信頼感を与えられるか、授業をコントロールできる雰囲気を持っているか。
2. 発問力(問いかけの工夫)
- Yes/Noで終わらない問い
- ×「これは正しいですか?」
- 〇「なぜこの答えになると思いますか?」
- 思考を促す段階的な問い
- 事実確認 → 理由づけ → 応用へとステップアップさせる。
- 待つ姿勢
- 発問後は2~3秒の沈黙をとり、「生徒が考える時間」を演出する。
👉 評価基準:生徒の思考を引き出す授業になっているか。単なる説明型になっていないか。
3. 説明力(わかりやすさ)
- 具体例を用いる
- 抽象的な概念は日常の例や図解で説明。
- 短く区切る
- 長く話さず「1分以内でワンセンテンス説明 → 発問 or 板書」に切り替える。
- リピート
- 重要な内容は「まとめると~」と繰り返す。
👉 評価基準:専門知識を生徒が理解できる形に変換できているか。
4. 板書力(視覚的整理)
- 色の使い分け
- 黒:本文・基本事項
- 赤:重要点・結論
- 青:補足・例外
- レイアウト
- 左から右、上から下へ、見やすい順序で展開。
- 授業終了後に「板書だけ見ても要点がわかる」状態を目指す。
- 書きながら話す工夫
- 黙って書くのではなく、書きながら要約を口頭で伝える。
👉 評価基準:視覚的に整理され、生徒がノートにまとめやすい板書になっているか。
5. 授業展開力(シミュレーション)
- 生徒の反応を想定
- 例:「この問題、Aさんなら“○○”と答えるかもしれない。でも本当は~」と仮想的に拾う。
- リアクションの挿入
- 「なるほど、そう考える人もいるよね」「いい視点だね」と返答を想定して話す。
- 時間配分の意識
- 導入→展開→まとめを5分程度で構成し、テンポよく進める。
👉 評価基準:生徒が存在する授業として成り立っているか。単なる独りよがりの説明に終わっていないか。
6. 教師らしさ(総合評価)
- 授業のゴールを明示
- 「今日の授業のポイントは3つです」と冒頭で提示。
- まとめでの達成感
- 最後に「今日学んだことを自分の言葉で説明できるかな?」と問いかけ、学びの定着を演出。
- 人柄・熱意
- 笑顔、うなずき、明るさが「この先生から学びたい」と思わせる。
👉 評価基準:専門知識以上に“教育者としての人間力”を伝えられているか。
こうした観点を整理すると、模擬授業は「知識を披露する場」ではなく、「教室で生徒を前にした臨場感をどう再現するか」が最大のポイントになります。
NG例(失敗パターン集)
- 説明が長すぎて「一方的な講義」になる
- 板書が小さくて見えにくい
- 時間が足りずまとめが省略される
模擬授業対策の実践方法
1. リハーサルと録画で“客観視”する
- 録画のメリット
- 「声が小さすぎる」「黒板を隠してしまっている」「板書の字が見えにくい」など、自分では気づかない改善点が明確になる。
- 何度か見直すと 言葉のクセ(えー、あのー) も把握できる。
- 効果的なやり方
- 1回目:通しで授業をやって録画 → 自分でチェック
- 2回目:改善点を直したバージョンを録画 → 他者に見てもらう
- これを繰り返すと、1回ごとに「授業の完成度」が目に見えて上がる。
2. 台本ではなく「要点カード」で安心感を持つ
- 台本の落とし穴
- 暗記に頼ると「台詞っぽく」なり、受験者も聞き手も違和感を覚える。
- 要点カードの作り方
- 紙1枚に「授業の3本柱」だけを書いておく。
- 例:①導入の問いかけ ②展開で扱う資料や板書の流れ ③まとめのゴール
- キーワードだけを箇条書きにしておくと、頭が飛んでもすぐ戻れる。
- 紙1枚に「授業の3本柱」だけを書いておく。
- メリット
- 自然な会話調で進めやすくなる
- 緊張しても「カードを見れば軌道修正できる」という安心材料になる
3. 現職の先生や先輩にフィードバックをもらう
- 依頼のコツ
- 「全体的にどうでしたか?」よりも「導入のつかみ」「発問のレベル」「時間配分」など、項目を絞って聞くと的確なコメントを得やすい。
- よく指摘される改善点
- 導入が長すぎ → 3分以内で終える
- 発問が難しすぎ → 「誰でも答えられる簡単な問い」から入って、徐々に深める
- 板書が見づらい → 左側に立つ癖を直す、字を大きくする
- 授業後半が駆け足 → 時間配分をタイマーで管理
- おすすめの相手
- 教育実習でお世話になった先生
- OB・OGの現役教員
- 教育学部の先輩(模擬授業経験者)
4. 効果を高める工夫
- 模擬授業を「小さな単位」で練習
- いきなり15分通すのではなく、「導入だけ」「板書の説明だけ」と分けて練習 → 部分ごとの完成度が上がりやすい。
- タイマー練習
- 実際の試験時間に合わせて計ると「まとめが時間切れになる」ミスを防げる。
- 模擬生徒を想定
- 実際に友人や家族に生徒役をやってもらうと、「反応を見て発問を調整する感覚」が養える。
ポイントは「練習の量」と「改善の質」を組み合わせること。
1回の練習を“ただ繰り返す”のではなく、録画 → 振り返り → 他者のフィードバック → 改善のサイクルを回すのが一番の近道です。
模擬授業は「練習量」で差がつきます。
リハーサルや録画、他者からのフィードバックを積み重ねることで自然な授業運営力が身につきます。
受験生がつまずきやすいポイントと解決策
模擬授業で不合格になる受験生は「同じ失敗」をしています。
声が小さい、板書がごちゃごちゃ、時間が足りない…これらは事前準備で防げます。
1. 声が小さい/聞き取りづらい
- 原因
- 緊張で呼吸が浅くなる
- 自分にだけ聞こえる声量で話してしまう
- 解決策
- 背筋を伸ばして腹式呼吸 → 息をしっかり吐くと自然に声が安定
- 「教室の一番後ろ」または「最前列の端」に届く声を意識
- 冒頭に深呼吸+第一声を大きめに出す練習を習慣化
- リハーサルの録音を聞いて「どこで声が小さくなるか」を確認
2. 板書がごちゃごちゃして見づらい
- 原因
- 話す内容をそのまま書いてしまう
- 色・スペースの使い分けができていない
- 解決策
- 色分けルールを決める(例:黒=本文、赤=キーワード、青=まとめ)
- 1行空ける/段落を作ることで視覚的に整理
- 板書を「完成形」でノートに作っておき、練習時に同じように再現
- 生徒役に「読みにくいところある?」と確認してもらう
3. 時間が余る/足りない
- 原因
- 展開をイメージせず、ぶっつけ本番で授業を組む
- 生徒の反応を想定していない
- 解決策
- ストップウォッチでリハーサルし、各パートの所要時間を記録
- 時間が余りそうなら → 補助問題や関連質問を用意しておく
- 例:「もう1つ例を出してみましょう」
- 時間が足りないなら → まとめ部分をコンパクトにする練習をしておく
- 例:「今日はここまでですが、重要なポイントは○○です」
- 本番でも「残り2分でまとめに入る」といった目安を頭に置く
4. 発問が難しすぎる
- 原因
- 自分の知識レベルで問題を考えてしまう
- 生徒の“初学者目線”を忘れている
- 解決策
- 発問は3段階構成にする
- 誰でも答えられる簡単な問い(安心感)
- 少し考えれば答えられる問い(思考の活性化)
- 応用的な問い(理解の確認)
- 実際に友人や家族に問いかけ、反応をチェックして調整
- 発問は3段階構成にする
5. 導入が長すぎる
- 原因
- エピソードや説明に時間をかけすぎる
- 解決策
- 導入は「つかみ+問い」で2〜3分以内に収める
- 例:「みなさんは朝ごはんを食べましたか?実は今日のテーマと関係があります」
- 長くても「1問い+短い説明」で切り上げる
改善のカギ
- リハーサルの録画/録音 → 振り返り → 修正を繰り返す
- 現職の先生や仲間に見てもらい、第三者の目で評価してもらう
- 「同じ失敗」をしないために、練習のたびに改善点を1つクリアしていく
よくある質問(FAQ)
模擬授業の練習を重ねても、本番では「予想外の事態」に直面することがあります。
受験生からよく寄せられる質問の多くは「沈黙が怖い」「暗記が必要?」「板書の字は下手でも大丈夫?」といった不安に関するものです。
ここでは実際の合格者や指導経験のある先生のアドバイスをもとに、よくある疑問を整理しました。
すぐに使えるテンプレート例文も紹介するので、練習の際に取り入れてみてください。
Q1. 模擬授業で沈黙が起きたらどうすればいいですか?
回答
数秒の沈黙は自然な現象です。
生徒が考える時間を与えている証拠でもあるので、焦らず待ちましょう。
ただし、長引くと不安を与えるので、「考える時間ですよ」と言葉を添えると安心感を与えられます。
テンプレート例文
「いい質問ですね。では、ちょっと考えてみましょう。ノートに書いて整理してもいいですよ。」
Q2. 模擬授業は暗記しないとダメですか?
回答
暗記に頼ると棒読みになり、生徒とのやり取りが不自然になります。
おすすめは「授業の流れを箇条書きにして覚える」こと。
発問や活動のポイントだけ押さえておけば、自然な授業進行が可能です。
テンプレート例文
「今日は3つのことを学びます。
①〜を理解する、②〜を使って考える、③〜をまとめる。
この順番で進めますね。」
Q3. 板書の字の上手さは評価されますか?
回答
字の美しさではなく「見やすさ・整理されているか」が重視されます。
板書は大きめに書き、色を分け、行間に余白を取ると生徒が見やすくなります。
テンプレート例文
「ここが今日のポイントです。(赤で囲む)大事なことは強調して覚えましょう。」
Q4. 実際の授業のように小道具を使ってもいいですか?
回答
学習効果を高める小道具(図カード、簡単な模型など)はプラス評価です。
ただし準備や説明に手間がかかるものは時間を圧迫するので避けましょう。
テンプレート例文
「この図カードを見てください。ここから今日の学習課題が見えてきます。」
Q5. 緊張で声が震えてしまいます。どうすればいいですか?
回答
多くの受験生が本番で緊張します。
声が震える場合は「冒頭の第一声」を意識することが効果的です。
挨拶を大きな声で行うと、その後の声も安定しやすくなります。
冒頭の第一声は「声量」と「言葉の内容」の両方で安心感を与えるのが大切です。
挨拶だけでなく、自分の状態や授業への期待を一言添えると、聞き手にも自分にも落ち着きが生まれます。
テンプレート例文(改善版)
「みなさん、おはようございます!
私は○○と申します。
今日は△△についてお話しできるのをとても楽しみにしてきました。
最初は少し緊張していますが、精一杯お伝えしますので、どうぞよろしくお願いします。」
ポイント
名前を伝える:自己紹介を入れると落ち着きやすい。
期待や意欲を表現する:「楽しみにしてきました」と前向きな言葉を添える。
緊張を軽く言葉にする:「少し緊張していますが」と正直に言うと気持ちが和らぐ。
最後にお願いの一言:「どうぞよろしくお願いします」で聞き手の共感を得られる。
🎤 本番直前1分ルーティン
⏱️ ステップ1(10秒):深呼吸で整える
- 鼻から3秒かけて息を吸う(お腹をふくらませる)
- 口から6秒かけて「ふぅー」と吐く
👉 心拍数が落ち着き、声の震えが抑えられる
⏱️ ステップ2(15秒):身体に力を入れて抜く
- 両手をギュッと5秒握り、パッと開く(2回)
- 肩をすくめて5秒キープ → ストンと落とす
👉 筋肉の緊張がほぐれ、震えが出にくくなる
⏱️ ステップ3(15秒):ハミング&小声
- 「ん〜〜」と鼻にかけて軽く声を出す
- その後「あー」と小さく声を伸ばす
👉 声帯が温まり、第一声が安定
⏱️ ステップ4(20秒):ポジティブ第一声リハーサル
- 実際の声量で「おはようございます!」や「よろしくお願いします!」と一度練習
👉 大きく明るい声を先に出すと、本番の声も出しやすい
✅ 合計:約1分
→ 呼吸・体・声の準備が整い、震えを最小限にできます。
Q6. 生徒役が思ったように反応してくれないときは?
回答
模擬授業では、面接官や受験者仲間が「生徒役」を演じるため、反応が薄いことがあります。
その場合は想定回答を補ってあげるのが安全策です。
テンプレート例文
「なるほど、少し難しいかな?例えば、〜のように考えることもできますよね。」
Q7. 授業の導入で何を話せばよいか分かりません。
回答
導入では「生徒が知っていること」や「身近な例」から入るのが鉄則です。
急に専門的な説明に入ると、置いてきぼりにされる印象を与えます。
テンプレート例文
「みなさんはスーパーで『半額シール』を見たことがありますよね?
今日はそれを使って算数を考えます。」
Q8. 時間が余ってしまった場合はどうすればいいですか?
回答
想定より早く終わるのはよくあること。
そのために「予備問題」や「もう一度確認する発問」を準備しておくと安心です。
テンプレート例文
「では、最後にもう一つ練習してみましょう。同じように計算できますか?」
Q9. 逆に時間が足りない場合はどうすればいいですか?
回答
時間不足は大きな減点につながります。
練習時から「まとめを1分で終えられる形」にしておくと、本番で調整しやすくなります。
テンプレート例文
「時間が来たので、今日はここまで。
大事なことは『割合はもとの数を基準に計算する』という点でした。」
Q10. 声の大きさはどれくらいを意識すればいいですか?
回答
「教室の一番後ろに届く声」を意識してください。
緊張すると声が小さくなるため、実際には普段より1.5倍大きな声で話すとちょうど良いです。
テンプレート例文
「みなさん、こちらを見てください!今日の課題はこちらです。」
Q11. 授業中に板書が間違ってしまったらどうすればいいですか?
回答
間違いは誰にでも起きます。
慌てず訂正し、「間違いを活かした指導」に変えるとプラス評価になります。
テンプレート例文
「あ、ここは違いましたね。
実はこういう間違いをする人も多いんです。
正しくはこうなります。」
模擬授業のFAQは「緊張対策」「時間調整」「導入の工夫」「板書の扱い」が中心です。
これらを事前にイメージし、テンプレート例文を繰り返し練習すれば、本番でも落ち着いて対応できます。
模擬授業は完璧を求めるより、「教師としてどうリカバーするか」が評価につながる試験です。
まとめ
模擬授業は「構成・時間配分・評価基準」を理解すれば怖くありません。
リハーサルやフィードバックを重ね、自分らしい授業を形にしていきましょう。
失敗を恐れず、準備を繰り返すことが合格への最短ルートです。
模擬授業だけでなく、教員採用試験の面接対策 も合否を左右します。
面接官がチェックする視点や回答例については別記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
👇
教員採用試験の面接対策|合格する答え方・質問例・練習法を徹底解説
教育実習の振り返りから試験対策まで、段階別に押さえるべきポイントと準備チェックリストをまとめた完全ガイド。
スムーズに教員への道を進めるための必読記事です。
👇
教育実習から教員採用試験までの完全ロードマップ|学生必見の準備チェックリスト
教育実習後に必要なお礼状の書き方、実習レポート作成、採用試験への準備まで、やるべきことをわかりやすく解説しています。
👇
教育実習後にやるべきこと完全ガイド|お礼状の書き方・実習レポート・採用試験対策まで解説
教育実習を辞退した後にどんな進路を選ぶべきか、教職を諦めるべきか迷ったときの判断基準やキャリアの考え方を解説しています。
👇
教育実習を辞退した後の進路選択|教職を諦めるべきか迷ったときの判断基準とキャリアの考え方
教育実習を辞退すると卒業や単位、就職にどんな影響があるのか不安な方へ。
進路選択のポイントも詳しく解説しています。
👇
教育実習を辞退したらどうなる?卒業・単位・就職への影響と進路選択ガイド
教育実習を辞退する際のお詫び状やメールの文例を多数掲載。
正しい書き方からNG例、マナーまで詳しく解説しています。
👇