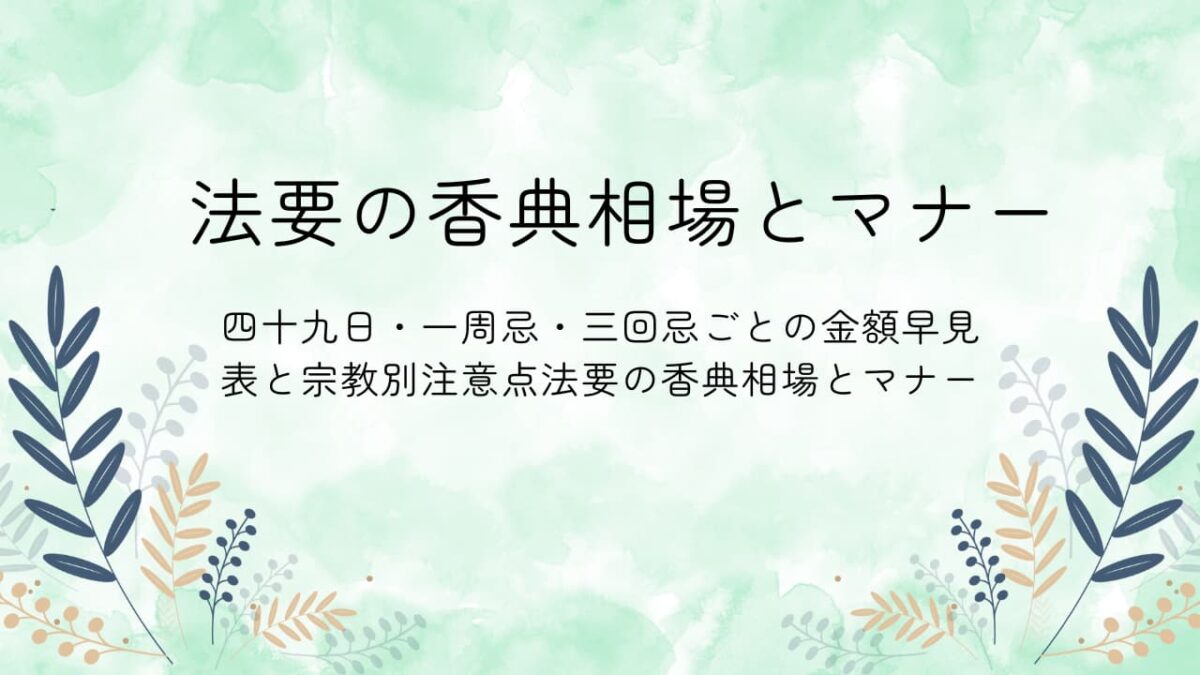法要に参列するとき、最も悩むのが「香典はいくら包むべきか」という点です。
四十九日、一周忌、三回忌と法要ごとに香典の相場は異なり、さらに宗教や故人との関係性によっても金額やマナーは変わります。
本記事では、法要ごとの香典金額を早見表で紹介するとともに、仏式・神式・キリスト教式の香典マナー、渡し方の注意点、NG集、そして最近増えている香典辞退の傾向まで、実例付きで丁寧に解説します。
初めて参列する方でも安心して準備できる、保存版の記事です。
香典の金額相場(両親・親族・友人別)、表書きや中袋の書き方、渡すタイミング、やってはいけないNGマナーまで徹底解説。
葬儀や法要に参列する前にチェックしておきましょう。
👇
香典マナー完全ガイド|金額相場・書き方・渡し方・NG例まで徹底解説
法要と香典の基本知識
香典相場を理解する前に、まず香典の意味と法要の種類を確認しておきましょう。
香典は単なる金銭のやり取りではなく、故人やご遺族への弔意を示す大切なものです。
香典とは?意味と役割
香典は故人の冥福を祈り、ご遺族を経済的に支えるために渡す金銭です。葬儀や法要に参列する際に持参し、心を込めて包むことが大切です。
法要の種類とタイミング
仏式の主な法要は以下の通りです。
- 四十九日(忌明け):最も重要な法要
- 一周忌:亡くなってから1年目
- 三回忌:数え年で3年目(実際は2年後)
- 七回忌以降:参列者も少なく規模も小さくなる
法要ごとの香典相場一覧表
香典の金額は法要の種類と故人との関係性で変わります。
ここでは四十九日・一周忌・三回忌ごとの相場を関係性別に解説します。
四十九日の香典相場について
四十九日は忌明けの大切な法要であり、遺族にとって区切りとなる場です。
そのため香典も「初七日や通夜より少し厚めに包む」のが一般的です。
ただし、金額は地域の習慣や故人との関係性によって異なるため、目安を知っておくと安心です。
| 関係性 | 相場 | 補足 |
|---|---|---|
| 両親 | 30,000〜50,000円 | 最も近しい親族。自立した社会人は3万円以上、余裕があれば5万円も。 |
| 兄弟姉妹 | 10,000〜30,000円 | 未婚なら1万円前後、既婚・家庭持ちは2〜3万円が多い。 |
| 親戚 | 5,000〜20,000円 | 付き合いの深さで変動。お世話になった場合は1〜2万円が目安。 |
| 友人・知人 | 5,000〜10,000円 | 一般的には5千円。特に親しい場合は1万円を包むことも。 |
両親の場合:30,000〜50,000円
両親は最も近しい親族のため、香典も高めが基本です。
兄弟姉妹で金額を揃えるケースもあります。
特に自立した社会人であれば、30,000円以上を包むことが多いです。
生活に余裕がある方や一人っ子の場合は50,000円を選ぶケースもあります。
兄弟姉妹の場合:10,000〜30,000円
兄弟姉妹への香典は10,000〜30,000円が目安です。
社会人であれば20,000円前後を選ぶ方が多く、特に既婚者や家庭を持つ立場なら30,000円程度にすることもあります。
兄弟姉妹間で不公平にならないよう、事前に相談して金額を揃えると遺族にとっても整理しやすいです。
親戚の場合:5,000〜20,000円
叔父・叔母、いとこなど親戚関係では、付き合いの深さによって金額が変わります。
普段から行き来が多い場合や、特にお世話になった場合は10,000〜20,000円が望ましく、遠い親戚であれば5,000円程度でも失礼にはなりません。
友人・知人の場合:5,000〜10,000円
友人・知人にあたる場合は5,000円が一般的です。
特に親しい間柄なら10,000円にすることもあります。
同僚や会社関係で参列する場合は、個人では5,000円程度にして「部署一同」でまとめるケースも多いです。
一周忌の香典相場
一周忌は、故人が亡くなってから一年目の大切な節目であり、親族や親しい友人が集まる法要です。
忌明け後初めての年忌法要となるため、香典も初七日や四十九日よりは控えめになりますが、弔意を表す気持ちはしっかり込めることが大切です。
金額の目安は関係性によって異なり、両親や兄弟姉妹など近しい親族にはやや高め、親戚や友人・知人は相場に沿った金額を包むのが一般的です。
| 関係性 | 相場 | 補足 |
|---|---|---|
| 両親 | 30,000円前後 | 最も近しいため高め。忌明け後も変わらず3万円程度が一般的。 |
| 兄弟姉妹 | 10,000〜20,000円 | 既婚・独立している場合は2万円、学生や若年層なら1万円程度でも失礼にあたらない。 |
| 親戚 | 5,000〜10,000円 | 関係性の近さや付き合いの深さで調整。遠方や疎遠の場合は5千円が目安。 |
| 友人・知人 | 3,000〜5,000円 | 無理のない範囲で気持ちを表す。特に親しい友人なら5千円程度。 |
三回忌以降の香典相場
三回忌以降の法要では、香典の金額は徐々に少なくなっていくのが一般的です。
初七日や四十九日、一周忌と比べると、三回忌以降は弔意を示しつつも、金額は控えめにする傾向があります。
ただし、故人との関係の深さや地域の習慣によっても相場は変わりますので、以下を目安としてご参考ください。
| 関係性 | 相場 | 補足 |
|---|---|---|
| 両親 | 10,000〜30,000円 | 近しい親族のため、1〜3万円程度が目安。生活状況に応じて調整。 |
| 親戚 | 5,000〜10,000円 | 付き合いの深さで変動。疎遠な場合は5千円、親しい場合は1万円。 |
| 友人・知人 | 3,000〜5,000円 | 気持ちを示す程度でよい。特に親しい場合は5千円程度。 |
【早見表】香典金額まとめ
| 法要 | 両親 | 兄弟姉妹 | 親戚 | 友人・知人 |
| 四十九日 | 30,000〜50,000円 | 10,000〜30,000円 | 5,000〜20,000円 | 5,000〜10,000円 |
| 一周忌 | 30,000円前後 | 10,000〜20,000円 | 5,000〜10,000円 | 3,000〜5,000円 |
| 三回忌以降 | 10,000〜30,000円 | 5,000〜10,000円 | 5,000〜10,000円 | 3,000〜5,000円 |
香典のマナーと注意点
香典は金額だけでなく、渡し方や香典袋の扱い方にもマナーがあります。
知らずに誤ると失礼になるため、注意が必要です。
香典袋の選び方と表書き
- 仏式:四十九日までは「御霊前」、以降は「御仏前」
- 神式:「御玉串料」
- キリスト教式:「御花料」
お札の入れ方と注意点
- 新札は避ける
- 人物の顔を裏向きに入れる
法要後の振る舞い
法要のあとには、僧侶を交えての会食(お斎)が用意されることがあります。
その際には、遺族が心を込めて準備してくださっているため、着席する前に「本日はご用意いただきありがとうございます」と一言添えるのが丁寧です。
食事の場では和やかな雰囲気を大切にしつつ、故人をしのぶ会話を心がけましょう。
また、法要後には引き出物をいただくこともあります。
受け取った際は「お気遣いいただきありがとうございます」と感謝を伝え、帰宅後にはできればお礼の電話やメッセージを入れるとより丁寧です。
会食に出席する場合
法要のあとには、僧侶や親族を交えて会食(お斎)が開かれることがあります。
遺族が用意してくださった場ですので、着席する際に「本日はお心遣いありがとうございます」と一言伝えるのが丁寧です。
食事中は故人を偲びながら、和やかな雰囲気を大切にしましょう。
会食に欠席する場合の断り方
やむを得ない事情で会食に参加できないときは、法要の場で失礼のないように丁寧に断ることが大切です。
遺族に対して一言添えるだけでも印象が違います。
【例文】
- 「本日はお招きいただきありがとうございます。誠に恐縮ですが、このあと所用があり失礼させていただきます。」
- 「せっかくのお心遣いを頂戴しましたのに、都合により出席がかないません。どうぞ皆さまで故人を偲ぶひとときをお過ごしください。」
引き出物をいただいた際のお礼
法要後に引き出物をいただくことがあります。
その場で「お気遣いいただきありがとうございます」と伝えたうえで、帰宅後に電話や手紙でお礼をするのが望ましいです。
電話でのお礼例
「本日は法要にお招きいただき、誠にありがとうございました。
お心のこもったおもてなしとお品まで頂戴し、心より感謝申し上げます。」
お礼状の書き方
お礼状は便箋に毛筆やペンで丁寧に書き、後日郵送するのが一般的です。
拝啓 このたびはご法要にお招きいただき、誠にありがとうございました。
心温まるおもてなしにあずかり、またお心遣いのお品まで頂戴し、重ねて御礼申し上げます。
ご遺族の皆様におかれましては、どうぞご自愛のうえお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。
敬具
宗教別の香典マナー
香典のマナーは、故人やご遺族の宗教によって表書きや包み方が異なります。
仏式では一般的に「御霊前」「御仏前」とするのに対し、神式やキリスト教式では専用の表書きや封筒を用いるのが礼儀です。
誤った表書きをしてしまうと失礼にあたるため、宗教ごとの正しいマナーを理解しておくことが大切です。
以下では、神式とキリスト教式の香典マナーを詳しくご紹介します。
神式の香典マナー
- 表書き
神式では「香典」という言葉は用いません。代わりに以下の表書きを使います。
- 御玉串料(おたまぐしりょう)
- 御榊料(おさかきりょう)
- 御神前(ごしんぜん)
- 封筒
神式では仏式と同じく白黒や双銀の水引が付いた香典袋を使用します。 - 蓮の花が印刷されている袋は仏式専用のため避けましょう。
- 相場
金額は仏式とほぼ同じで、両親・兄弟姉妹は1〜3万円、親戚は5千円〜2万円、友人・知人は3千円〜1万円が一般的です。
- 渡し方
神式では「御霊前」という表書きは仏式用となるため使用せず、上記の表現を用いるように注意しましょう。
キリスト教式の香典マナー
- 表書き
キリスト教では「香典」という考え方はなく、代わりに以下のような表記を使います。
- 御花料(ごかりょう)
- 献花料(けんかりょう)
- 御ミサ料(ごみさりょう・カトリックで使用)
- 封筒
キリスト教では水引のついた香典袋は使用しません。白無地の封筒や、十字架・百合の花が印刷された封筒を用います。派手な装飾や色付き封筒は避け、清らかなイメージのものを選ぶのが基本です。
- 相場
仏式とほぼ同程度ですが、教派や地域によっては控えめにする傾向もあります。友人・知人は3千円〜5千円、親族は1〜2万円程度が一般的です。
- 注意点
キリスト教では数珠を持参せず、黙祷や祈りを捧げるのが一般的です。表書きに「御霊前」「御仏前」など仏教用語を用いるのは失礼にあたりますので注意しましょう。
違いまとめ表
| 宗教 | 表書き | 香典袋の特徴 | 呼び方 |
| 仏式 | 御霊前/御仏前 | 黒白・双銀の水引 | 香典 |
| 神式 | 御玉串料/御榊料 | 白無地や双銀の水引 | 玉串料 |
| キリスト教 | 御花料/献花料 | 白封筒(十字架・百合柄) | 花料・ミサ料 |
香典のNG集
- 新札を入れる
- 金額に「4」や「9」を使う
- 仏式に神式・キリスト教用の表書きを使う
- 案内に反して香典を持参する
- 「お気持ちだけですが」と無理に渡す
- 他の参列者と差をつける
香典辞退の最近の傾向
香典相場や宗教マナーに加え、近年は「香典辞退」が増えています。
家族葬や直葬、コロナ禍による葬儀の簡素化など、現代ならではの理由で辞退を選ぶケースが増加中です。
増えている理由
- 金銭的負担を減らす配慮
- 小規模葬・家族葬の普及
- 故人・遺族の意志の尊重
- コロナ禍による葬儀の簡素化
参列者の対応
- 香典は持参せず、弔意を言葉や供花で示す
- 迷ったら事前に遺族に確認する
よくある質問(Q&A)
香典や弔問に関するマナーは、地域や関係性によって細かく異なるため、迷う方も多いものです。
ここでは「香典を辞退された場合の対応」や「夫婦で参列する場合のまとめ方」など、よくある疑問をわかりやすくまとめました。
実際に使える文例もご紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
Q1. 香典辞退と書かれていた場合は?
A. 「香典辞退」と案内がある場合は、遺族の意向を尊重し、無理に渡す必要はありません。
弔意を示したい場合は、菓子折りや果物、または手紙などで気持ちを伝えると良いでしょう。
【例文】
「このたびはご愁傷様でございました。心ばかりではございますが、お供えの品をお送りいたします。どうぞご仏前にお供えいただければ幸いです。」
Q2. 夫婦で参列する場合は?
A. 夫婦で参列する場合、香典はまとめて一つにしても構いません。
名字が異なる場合や、それぞれ個別に気持ちを伝えたいときは別々でも問題ありません。
Q3. 欠席する場合は?
A. 都合で参列できない場合は、現金書留で香典を送るのが丁寧です。
必ず手紙を添え、欠席のお詫びと弔意を記しましょう。
【例文】
「ご訃報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。当日は参列叶いませんため、心ばかりを同封いたしました。ご霊前にお供えいただければ幸いです。」
Q4. 地域によって相場は変わる?
A. 香典の金額は地域によって差があります。
首都圏では友人関係で5,000円程度が多いですが、地方では1万円が一般的な場合もあります。
親族や関係性の深さによっても変わるため、迷ったら親族や地元の知人に確認すると安心です。
Q5. 会社関係(上司・同僚)の場合はいくらが目安?
A. 会社関係では、上司に対しては1万円程度、同僚や部下の場合は5,000円程度が一般的です。
会社の慣習として「部署一同」でまとめる場合もあります。
【例文】
「御霊前 ○○株式会社 営業部一同」
Q6. 香典袋の表書きはどうすればいい?
A. 仏式では「御霊前」または「御香典」、神式では「御玉串料」、キリスト教では「御花料」と書きます。
宗教がわからない場合は「御霊前」を使えば無難です。
Q7. 旧札を使うべき?
A. 香典には新札を避けるのが基本です。
新札しかない場合は、折り目をつけてから包みましょう。
Q8. 連名で出すときの並び順は?
A. 夫婦連名の場合は右に夫、左に妻を書きます。
友人同士の場合は、年齢や役職の高い人から順に右から並べるのが基本です。
Q9. 香典袋の中袋は必ず書くべき?
A. 中袋には住所・氏名・金額を書くのがマナーです。
遺族が整理しやすくなるため、略さず丁寧に記入しましょう。
【例文】
「住所:東京都渋谷区〇〇町1-2-3
氏名:山田太郎
金額:金壱萬円也」
Q10. 遠方の葬儀で参列が難しい場合はどうする?
A. 遠方で参列が難しいときは、欠席の旨を伝えたうえで現金書留で香典を送り、弔意を伝えるのが一般的です。
供花や弔電を送るのも良い方法です。
【例文】
「ご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。遠方のため参列できませんが、謹んで哀悼の意を表します。」
Q11. 四十九日以降に知った場合でも香典は送る?
A. 四十九日を過ぎてから訃報を知った場合でも、香典を送って構いません。
その際は「御霊前」ではなく「御仏前」と表書きします。
手紙を添えて遅れたことをお詫びしましょう。
【例文】
「ご訃報を後から知り、大変失礼いたしました。
遅ればせながら、心ばかりを同封いたします。
御仏前にお供えいただければ幸いです。」
まとめ
香典は、故人を偲び遺族を支えるための大切な心遣いです。
法要の種類や香典相場は親族・友人・会社関係など立場によって異なり、相場を把握しておくことが遺族への思いやりにつながります。
また、香典袋の表書きやお札の入れ方といったマナー、会食やお礼の対応、宗教ごとの違いなど、細部まで注意を払うことが求められます。
最近では「香典辞退」の風潮も広がっていますが、記載がある場合は無理に渡さず、弔意を手紙や供花などで表すのが望ましいでしょう。一方で、辞退の記載がない場合や地域慣習が強い場合には、相場やマナーを守った香典を準備するのが安心です。
記事内で紹介した 相場一覧表・添え状文例・お礼状例文 は、実際の場面でそのまま参考にできる内容です。
突然の訃報や法要の案内に備え、あらかじめ目を通しておくことで、いざという時に失礼なく対応できるでしょう。
香典は金額の多寡ではなく、遺族や故人への思いを込めて誠意を示すことが大切です。
本記事を通して、香典の相場やマナーを理解し、安心して故人を偲ぶ機会に役立てていただければ幸いです。
・香典の金額相場(両親・親族・友人別)、表書きや中袋の書き方、渡すタイミング、やってはいけないNGマナーまで徹底解説。
葬儀や法要に参列する前にチェックしておきましょう。
👇
香典マナー完全ガイド|金額相場・書き方・渡し方・NG例まで徹底解説
・香典返しに添える挨拶状の正しい書き方や文例、送付時期を徹底解説。
失礼のない表現や注意点も紹介しており、法要後のマナーを確認できます。
👇
・法事・法要の案内状の書き方を完全ガイド。
四十九日、一周忌、三回忌に対応したテンプレートや文例、マナーのポイントを詳しく解説しています。
👇
法事・法要案内状の書き方決定版|四十九日・一周忌・三回忌対応テンプレート付き
・香典の郵送方法だけでなく、同封する添え状の書き方も知っておきたい方は、こちらをご確認ください。
👇
香典を郵送するマナーと現金書留の送り方|失礼にならない添え状文例付き
お布施、供物、線香、手土産など、法要当日に必要な持ち物を一覧化。
チェックリスト付きで漏れなく準備できます。
👇