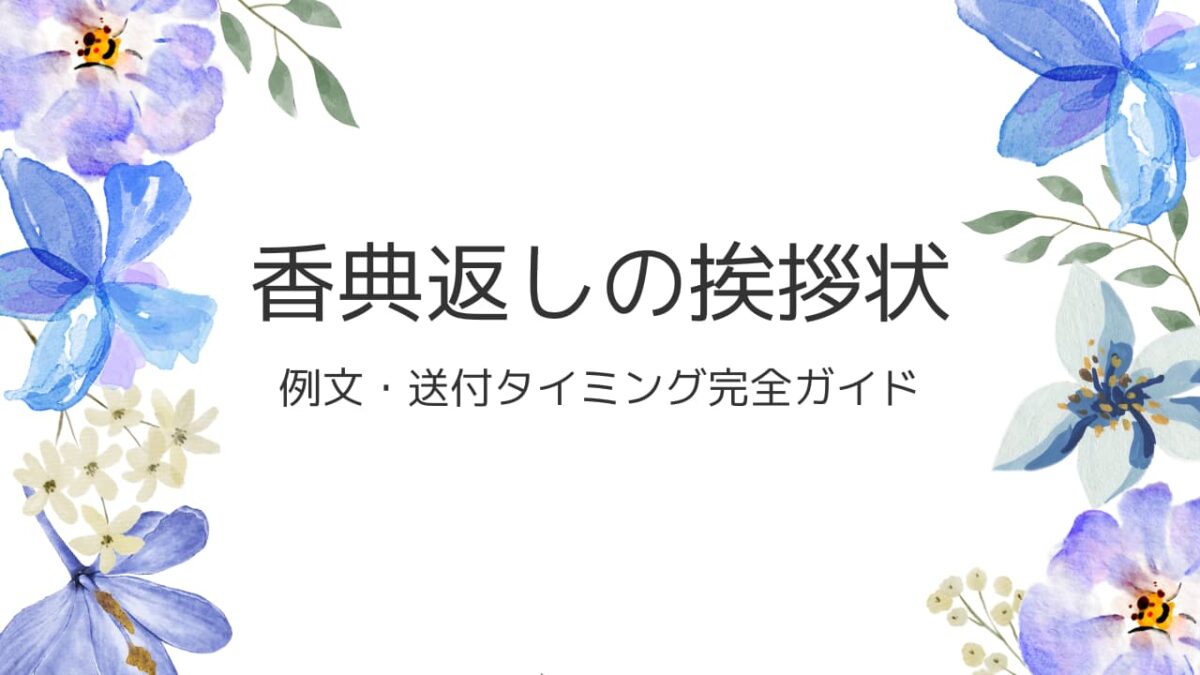大切な方を見送った後、弔意に対するお礼として欠かせないのが「香典返しの挨拶状」です。
丁寧で誠実な文章は、故人やご遺族の想いを正しく伝えるだけでなく、今後のご縁を円滑に保つうえでも重要な役割を果たします。
本ガイドでは、香典返しの挨拶状を失礼なく作成するためのマナー、送付タイミング、シーン別例文、NG集まで網羅的に解説。
この記事を読めば、どなたでも安心して挨拶状を書けるようになります。
法事・法要の案内状の書き方を完全ガイド。
四十九日、一周忌、三回忌に対応したテンプレートや文例、マナーのポイントを詳しく解説しています。
👇
法事・法要案内状の書き方決定版|四十九日・一周忌・三回忌対応テンプレート付き
香典の郵送方法だけでなく、同封する添え状の書き方も知っておきたい方は、こちらをご確認ください。
👇
香典を郵送するマナーと現金書留の送り方|失礼にならない添え状文例付き
目次
- 1 香典返しの挨拶状とは?
- 2 香典返しの挨拶状を送るタイミング
- 3 挨拶状の基本構成とマナー
- 4 シーン別の例文集
- 5 NG集|やってはいけない表現と注意点
- 6 香典返しの挨拶状を簡単に作成する方法
- 7 よくある質問(FAQ)
- 7.1 Q1. 忌明け前に香典返しの挨拶状を送ってもいいですか?
- 7.2 Q2. 挨拶状をメールやLINEで送っても失礼ではありませんか?
- 7.3 Q3. キリスト教式の場合はどう書けばいい?
- 7.4 Q4. 挨拶状なしで品物だけ送ったら?
- 7.5 Q5. 挨拶状は縦書きと横書き、どちらがよいですか?
- 7.6 Q6. 香典返しの挨拶状は手書きがよいのでしょうか?
- 7.7 Q7. 会社の同僚や取引先にはどのように書くべき?
- 7.8 Q8. 親しい友人に送る場合は少し砕けてもいいですか?
- 7.9 Q9. 香典を辞退した場合でも挨拶状は必要ですか?
- 7.10 Q10. 香典返しが少額の場合も挨拶状をつけるべきですか?
- 7.11 Q11. 香典返しの挨拶状は誰の名前で出すの?
- 8 まとめ
香典返しの挨拶状とは?
香典返しの挨拶状は、葬儀で香典を頂いた方へ感謝を示し、香典返しの品物を同封または別送する際に添えるお礼状です。
故人の冥福を祈りつつ、遺族として礼を尽くす場面だからこそ、格式と温かさを両立させた言葉選びが求められます。
挨拶状の目的と重要性
- 感謝の気持ちを正式に伝える
- 遺族としての礼節を保つ
- 今後のご縁を大切にする意思表示
香典返しと香典返しの挨拶状の違い
| 区分 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 香典返し(品物) | タオル・お茶・カタログギフトなど | 地域慣習と価格帯(半返し)が目安 |
| 挨拶状 | 品物や現金書留に添える書面 | 書式や敬語の正確さが必須 |
香典返しの挨拶状を送るタイミング
送付時期を誤ると、先方に失礼となるだけでなく宗教・地域慣習との不一致を招きます。
ここでは一般的な仏式を中心としつつ、宗派や地域の差異に配慮したタイミングの決め方を解説します。
四十九日法要後
- 一般的目安:忌明け後の1〜2週間以内
- 法要当日に授与品を手渡す場合は同封で可
- 遠方の参列者・辞退者には後日郵送
三十五日法要で忌明けとなる地域
- 孤立地域や浄土真宗など
- 三十五日+1週間が目安
遅れた場合の対処
- 挨拶状の冒頭でお詫び
- 理由は簡潔に(「諸般の事情により遅延し…」)
- 送付が3か月超なら電話連絡で先に謝意を伝える
法要ごとの香典相場(四十九日・一周忌・三回忌)を早見表で確認。
仏式・神式・キリスト教式の表書き、渡し方、マナーの注意点まで徹底解説しています。
👇
法要の香典相場とマナー|四十九日・一周忌・三回忌ごとの金額早見表と宗教別注意点
挨拶状の基本構成とマナー
形式を整えながらも温かみを持たせるには、「定型+故人らしさ+遺族の感謝」をバランスよく配置することがコツです。
全体構成(縦書きを想定)
- 頭語(謹啓・拝啓)
- 時候の挨拶
- 御礼の言葉
- 故人の逝去報告と生前の厚誼への感謝
- 香典返しの品物の案内
- 結語(敬具・謹白)
- 日付・差出人
頭語と結語
- 最も無難なのは「謹啓」「謹白」
- カジュアル禁止(「こんにちは」等はNG)
時候の挨拶
- 忌明け後であれば季節の言葉を使用: 「向暑の候 皆様にはいよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。」
- 忌中は「時下」とし、季語を控える
故人への言及と感謝
「去る○月○日 享年◯歳にて永眠いたしました故 ○○ 儀 生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます。」
品物の案内
「心ばかりの品をお届けいたしますので ご受納賜りますれば幸いに存じます。」
シーン別の例文集
関係性に応じた言葉選びは、同じフォーマルでも微妙に異なります。
以下の例文をベースに調整すると、失礼なく気持ちを伝えられます。
近親者向け(親戚・親族)
謹啓 向暑の候 皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます
去る○月○日 ○○が永眠いたしました折には ご丁重なるご香典並びに温かいお言葉を賜り 厚く御礼申し上げます
本日 忌明けの法要を相営み 供養の印として心ばかりの品をお送りいたしました
略儀ながら書中をもちまして御挨拶申し上げます
謹白
令和○年○月○日
喪主 ○○ ○○
友人・同僚向け
拝啓 盛夏の候 益々ご繁栄のこととお慶び申し上げます
父 ○○ 儀 逝去の折には ご丁重なるご厚志を賜り誠にありがとうございました
本来なら拝眉のうえ御礼申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
敬具
会社関係・上司向け
謹啓 晩夏の候 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
このたびは ご多忙のところ過分なるご厚志を賜り 誠にありがとうございました
忌明け法要を滞りなく相営みましたので 謹んで香典返しの品をお届け申し上げます
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げ 略儀ながら書中をもちまして御礼に代えさせていただきます
謹白
連名・団体宛て
拝啓 秋晴の候 皆さまにおかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます
先般は 故 ○○ 儀 の葬儀に際し 有志一同としてご厚志を賜り誠にありがとうございました
供養の印として心ばかりの品を同封いたしましたので ご笑納くださいませ
まずは書中をもちまして御礼申し上げます
敬具
NG集|やってはいけない表現と注意点
せっかく心を込めた挨拶状でも、タブー表現が含まれていると台無しに。
以下は必ずチェックしましょう。
タブー表現
- 「ご冥福をお祈りします」(忌明け後の遺族が使うのは不適切)
- **「再起を祈念」「がんばります」**など前向きすぎる語
カジュアルすぎる言い回し
- 絵文字・顔文字
- 口語体(「ありがとう!」など)
過度な装飾やデザイン
- 派手すぎるフォントや色紙
- キャラクター柄の便箋
香典返しの挨拶状を簡単に作成する方法
忙しい喪主や家族にとって、数十通〜数百通の挨拶状を手書きするのは大きな負担です。
効率的かつ丁寧に仕上げるコツを紹介します。
テンプレートの活用
- この記事の例文をコピペ → 故人名・日付を編集
- 表現の重複や誤字脱字チェックを忘れずに
オンラインサービス
- 挨拶状専門の印刷サイトを利用
- フォーマット選択 → 文面入力 → 校正 → 投函代行までワンストップ
専門業者への外注
- 仏壇店・葬儀社の提携印刷所
- 校正者によるマナー監修付きプランが安心
よくある質問(FAQ)
香典返しの挨拶状は、喪家の気持ちを伝える大切な書面です。
しかし、送付のタイミングや表現方法などについては迷う方が多いものです。
ここでは、よく寄せられる質問に加え、実際に読者から想定される疑問もまとめ、具体的な回答と例文をご紹介します。
挨拶状を書く際の参考にしてください。
Q1. 忌明け前に香典返しの挨拶状を送ってもいいですか?
A.
本来は四十九日の忌明け後に送るのが正式です。
ただし、遠方で法要に参加できない方や、早めに感謝を伝えたい場合には「略式挨拶状」を先に送り、正式な挨拶状は忌明け後に改めて送る方法もあります。
状況に応じて臨機応変に対応しましょう。
テンプレート例文
このたびはご丁寧なお心遣いを賜り、誠にありがとうございました。
四十九日の法要後に改めてご挨拶申し上げますが、まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます。
Q2. 挨拶状をメールやLINEで送っても失礼ではありませんか?
A.
目上の方や会社関係には、紙の挨拶状を送るのが無難です。
メールやLINEだけで済ませるのは失礼にあたる場合があります。
ただし、親しい友人や親族であれば、紙の挨拶状を送ったうえで補足的にメールで感謝を伝えるのは差し支えありません。
テンプレート例文(補足メール)
先日はお心のこもったご厚志をいただき、誠にありがとうございました。
後日改めて書面にてご挨拶申し上げますが、ひとまずメールにて御礼をお伝えいたします。
Q3. キリスト教式の場合はどう書けばいい?
A.
仏教用語の「四十九日」「御霊前」などは用いず、「召天」「安息」などのキリスト教式の表現を使います。
感謝の気持ちと香典返しをお届けする趣旨は変わりません。
宗教に応じた言葉遣いに注意することが大切です。
テンプレート例文
このたびはご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
故○○の召天に際し、皆様より頂戴したご厚志に深く御礼申し上げます。
ささやかではございますが、感謝のしるしとして品を同封いたしました。
Q4. 挨拶状なしで品物だけ送ったら?
A.
香典返しの品物に挨拶状を添えないのは、非常に失礼に当たります。
たとえ親しい間柄であっても、最低限の礼を尽くす意味で必ず書面を添えましょう。
テンプレート例文
このたびは格別のお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます。
本来であれば直接ご挨拶に伺うべきところ、略儀ながら書面にて失礼いたします。
心ばかりの品をお届けいたしますので、ご受納いただければ幸いです。
Q5. 挨拶状は縦書きと横書き、どちらがよいですか?
A.
一般的には縦書きが正式です。
ただし、近年は横書きも広く受け入れられています。
会社関係や格式を重んじる相手には縦書き、カジュアルな関係には横書きでも構いません。
テンプレート例文(縦書きイメージ)
謹啓
このたびはご厚志を賜り、誠にありがとうございました。
略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。
謹白
Q6. 香典返しの挨拶状は手書きがよいのでしょうか?
A.
手書きは丁寧で心のこもった印象を与えますが、必ずしも手書きである必要はありません。
印刷でも失礼には当たりません。
ただし、署名部分だけを直筆にすると、より誠意が伝わります。
テンプレート例文(印刷+直筆署名)
このたびはご丁寧なご厚志を賜り、誠にありがとうございました。
略儀ながら書面にて御礼申し上げます。
令和○年○月
喪主 □□□(直筆署名)
Q7. 会社の同僚や取引先にはどのように書くべき?
A.
ビジネス関係の相手には、私情を抑え、簡潔かつ礼儀正しい文章を心がけます。
宗教的な表現は避け、「このたびはご厚情を賜り…」など一般的な表現が無難です。
テンプレート例文
このたびはご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
心ばかりの品をお送りいたしますので、ご受納くださいますようお願い申し上げます。
Q8. 親しい友人に送る場合は少し砕けてもいいですか?
A.
親しい友人であれば、形式ばかりにとらわれず、心のこもった温かい言葉を添えると良いでしょう。
ただし、あくまで礼状であることを忘れず、礼を尽くす姿勢を示してください。
テンプレート例文
先日は温かいお心遣いを本当にありがとう。
○○もきっと喜んでいることと思います。
ささやかだけれど、お礼の品を送りますので受け取ってくださいね。
Q9. 香典を辞退した場合でも挨拶状は必要ですか?
A.
香典を辞退した場合でも、挨拶状は必要です。
「香典をご遠慮したにもかかわらず…」などの表現を添え、感謝を伝えることで誠意が伝わります。
テンプレート例文
このたびは、香典をご遠慮申し上げましたにもかかわらず、あたたかなお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
Q10. 香典返しが少額の場合も挨拶状をつけるべきですか?
A.
金額に関わらず、挨拶状は必ず添えましょう。
金品よりも、感謝の気持ちを伝えることに意味があります。
テンプレート例文
このたびはご厚志を賜り、心より感謝申し上げます。
ほんの心ばかりの品ではございますが、どうぞお納めください。
Q11. 香典返しの挨拶状は誰の名前で出すの?
A.
通常は喪主の名前で出します。
家族連名にする場合もありますが、ビジネス関係や改まった相手には喪主の単独名が基本です。
テンプレート例文
令和○年○月
喪主 □□□
まとめ
香典返しの挨拶状は、故人を偲びつつご厚志への感謝を伝える大切な手紙です。
この記事で紹介した基本構成、送付タイミング、シーン別例文、NGチェックリストを活用すれば、どなたでも誠意ある文章を作成できます。
忙しいときはテンプレートや外注も賢く利用し、心のこもったごあいさつを届けましょう。
挨拶状の印刷を代行してくれる 挨拶状ドットコム もおすすめです。
プロが作成・印刷・発送まで対応してくれるので、短時間で失礼のない案内状が完成します。
👇

法事・法要の案内状の書き方を完全ガイド。
四十九日、一周忌、三回忌に対応したテンプレートや文例、マナーのポイントを詳しく解説しています。
👇
法事・法要案内状の書き方決定版|四十九日・一周忌・三回忌対応テンプレート付き
香典の金額相場(両親・親族・友人別)、表書きや中袋の書き方、渡すタイミング、やってはいけないNGマナーまで徹底解説。
葬儀や法要に参列する前にチェックしておきましょう。
👇
香典マナー完全ガイド|金額相場・書き方・渡し方・NG例まで徹底解説
法要ごとの香典相場(四十九日・一周忌・三回忌)を早見表で確認。
仏式・神式・キリスト教式の表書き、渡し方、マナーの注意点まで徹底解説しています。
👇
法要の香典相場とマナー|四十九日・一周忌・三回忌ごとの金額早見表と宗教別注意点
お布施、供物、線香、手土産など、法要当日に必要な持ち物を一覧化。
チェックリスト付きで漏れなく準備できます。
👇
初めての法要準備ガイド|日程・手順・持ち物一覧とマナー・NG集付き
香典の郵送方法だけでなく、同封する添え状の書き方も知っておきたい方は、こちらをご確認ください。
👇
香典を郵送するマナーと現金書留の送り方|失礼にならない添え状文例付き
法要に参列する際の服装マナーや、お布施を包むのし袋の書き方、僧侶への正しい渡し方までを詳しく解説しています。
香典とあわせて知っておきたい実践的なマナーを網羅した内容です。
👇