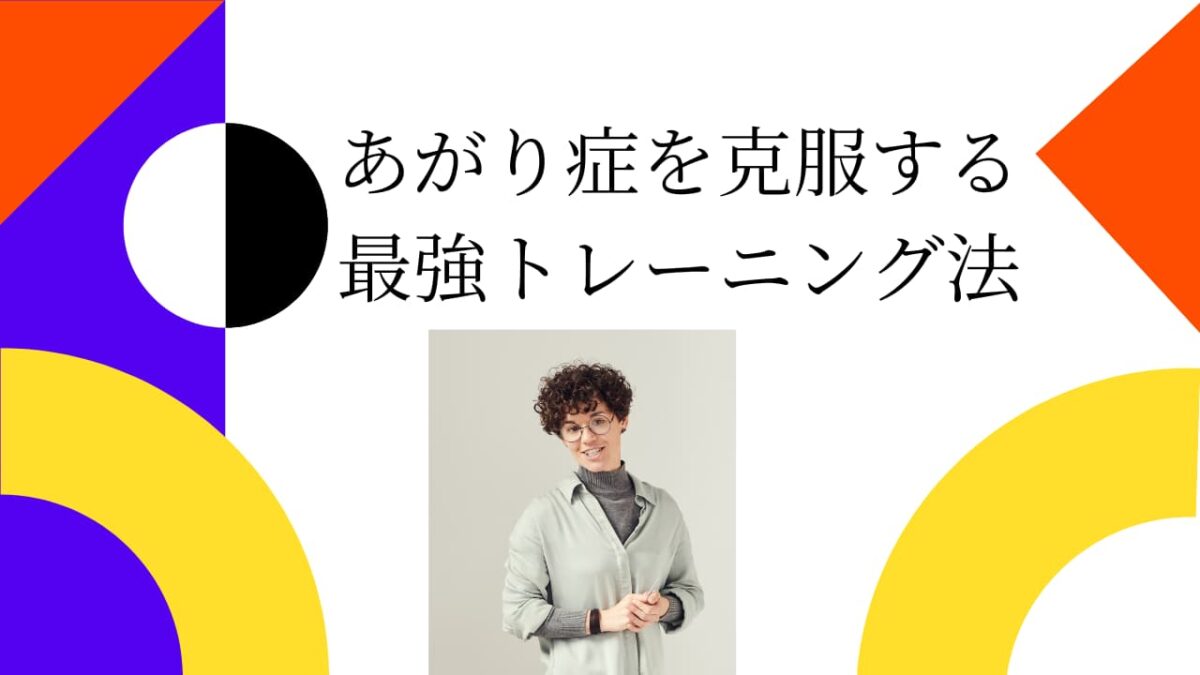人前に出ると頭が真っ白になる。声が震える。
言いたいことの半分も伝えられない——。
そんな「あがり症」は、決して“性格”ではありません。
正しいトレーニングを重ねれば、誰でも改善できる「スキル」です。
本記事では、日本人に多い“真面目さゆえの緊張”に着目し、
科学的根拠+実践例+トレーニングテンプレ を組み込んだ「完全版メソッド」をまとめました。
「明日の発表が怖い…」
「初対面の場で緊張して自分が出せない…」
そんなあなたも、この記事通りに進めれば“緊張しにくい体質”へ変わっていきます。
目次
- 1 あがり症は努力で克服できる理由
- 2 あがり症は“訓練次第で誰でも改善”のエビデンス
- 3 今日からできる!あがり症克服トレーニング
- 4 3-4-5呼吸法 vs 4-2-6呼吸法
- 5 話す前の“声の震え防止”ウォームアップ
- 6 声の震え防止+呼吸法のセットウォームアップ例
- 7 頭が真っ白になる人の「話すテンプレ」
- 8 実践で使える!あがり症克服の例文集
- 9 あがり症克服のNG行動集
- 10 よくある質問(Q&A)
- 10.1 Q1. 緊張すると声が震えるのですが治りますか?
- 10.2 Q2. 何年もあがり症ですが、今からでも克服できますか?
- 10.3 Q3. 人前が本当に苦手で、避けてしまいます。どうすれば?
- 10.4 Q4. あがり症はどれくらいで改善できますか?
- 10.5 Q5. 何から練習すれば一番効果的ですか?
- 10.6 Q6. 本番で急に緊張したらどう対処する?
- 10.7 Q7. あがり症は病気なんですか?病院に行くべき?
- 10.8 Q8. 初対面の場で頭が真っ白になるのを防ぐには?
- 10.9 Q9. 大人数の前だと急に緊張が跳ね上がるのはなぜ?
- 10.10 Q10. 噛んだり間違えたりしたら終わりだと思ってしまいます。どうしたら?
- 10.11 Q11. プレゼン中に質問されると動揺します。どう対応すべき?
- 11 まとめ
- 12 緊張しない話し方に効果的な本・アプリ紹介
あがり症は努力で克服できる理由
あがり症は「性格だから治らない」と思い込みがちですが、実は脳科学・心理学の観点では“後天的に強化された反応”にすぎません。
人前での失敗経験や、評価を気にしすぎる癖、過去の記憶などが重なり、脳が「人前=危険」と誤認している状態です。
つまり、脳の誤ったクセを矯正すれば、あがり症は確実に改善します。
この章では、まず“あがり症がなぜ起こるのか”“どうすれば治るのか”という全体像をわかりやすく解説し、後のトレーニングでスムーズに効果が出る土台を作ります。
恐怖の正体は「交感神経の暴走」――脳の誤作動が生む身体反応
初対面の場や人前に立つと、体が固まったり、手が震えたりすることがあります。
これは決してあなたの性格や能力の問題ではなく、脳と自律神経の働きによる自然な反応です。
特に交感神経が活発になると、次のような反応が現れます。
- 心臓がドキドキして早く打つ
- 声が震えて安定しない
- 手や指に汗が出る
- 頭が真っ白になり、言葉が出にくくなる
これらは「危険から逃げろ」という命令ではなく、脳が『今、全力を出せ』と体に指示しているサインです。
つまり、プレゼン前に心臓がバクバクするのは、恐怖ではなくパフォーマンスを上げる準備反応と考えられます。
例:プレゼン直前の心臓のドキドキ
- 心臓が高鳴る → 血流が増えて筋肉や脳に酸素が行き渡る
- 手汗が出る → 手の滑りを防ぎ、紙やペンの操作がしやすくなる
- 呼吸が浅くなる → 短期的な緊張下で瞬発力を高める
このように、身体の反応自体はむしろ役に立つ仕組みなのです。
恐怖や不安の意味を正しく理解するだけで、「なぜ自分だけ?」という不安は減り、自然に落ち着きを取り戻せます。
💡 ポイント
- 身体の症状は脳が過剰に反応しているだけ
- 「恐怖=危険」ではなく「パフォーマンスを上げる反応」と捉える
- 理解するだけでも心理的負担は半減し、次のトレーニング効果も上がる
プレゼン前に心臓がドキドキする → 危険の判断ではなく、脳が“頑張れ”と出している反応。
反応の意味を正しく理解するだけで、恐怖は半減します。
あがり症は“訓練次第で誰でも改善”のエビデンス
心理学の研究では
「暴露(慣れる)×認知修正」 が最も効果的とされています。
つまり、
① 小さな場面で経験を積む
② 緊張しても大丈夫だという成功体験を重ねる
この2つを繰り返すことで、人前での緊張は自然と薄れていきます。
あがり症の背景には過去の経験やトラウマが関係していることがあります。
詳しくは過去のトラウマを癒す心理リセット法|怖い記憶を手放し「話せる自分」に変わる具体ステップをご覧ください。
今日からできる!あがり症克服トレーニング
ここでは、実際に“あがり症を克服した人が使ってきた具体的なトレーニング”を体系的に紹介します。
ポイントは、いきなり「大勢の前で話す練習」をしないこと。
あがり症が強い人ほど、段階を踏んだ負荷調整が必要です。
この章では、呼吸法、発声練習、思考の整理、会話テンプレなど、初心者でも今日から実践できるメソッドを豊富な例文とともに解説します。
毎日10分でも続ければ、1〜2週間で「緊張が前より軽い」と感じ始めます。
あがり症克服トレーニングを始める前に、まず“緊張しにくい話し方の基礎ステップ”を押さえておくと効果が高まります。
基本の流れは【人前で話すときに緊張しない方法|実践できる7つのステップとNG例】で詳しく紹介しています。
3-4-5呼吸法 vs 4-2-6呼吸法
どちらがより効果的?何が違う?
結論から言うと、
どちらも効果はあるが、目的によって使い分けるのが最適 です。
- 3-4-5呼吸法 → 即効で緊張を下げたい人向け(初心者向き)
- 4-2-6呼吸法 → 深いリラックスを得たい人向け(慣れた人向き)
それぞれの特徴と違いを、具体的にわかりやすく説明します。
スピーチ前の緊張を和らげるには、事前の呼吸リセットが非常に効果的です。
発表前に行う1分メソッドは【スピーチ前に心を整える呼吸テクニック】でまとめています。
3-4-5呼吸法とは(初心者向き・即効性重視)
もっとも簡単で、あがり症の人でもすぐに取り組める呼吸法です。
特に “吐く息を長くする” ことで、交感神経(緊張)を素早く落ち着けられます。
手順
① 3秒 吸う
② 4秒 止める
③ 5秒 吐く(吐く時間を長く)
→ これを5回。
向いている人
- 本番前に手が震える、心拍が上がる人
- 深呼吸しても落ち着かない人
- あがり症の初心者
- 短時間で気持ちを整えたい場面
メリット
- “止める”時間が4秒あるため、脳の混乱が一度リセットされる
- 呼吸を整える動作そのものに集中でき、思考が暴走しにくい
- 5回だけでも、体感的に「スッ」と落ち着く
自分にかける言葉例(メンタルアンカー)
「吐く息を長くすれば落ち着いてくる、大丈夫。」
4-2-6呼吸法とは(上級者向け・深い鎮静効果)
4秒吸う → 2秒止める → 6秒吐く。
こちらは 副交感神経を強く働かせる 呼吸法で、より深いリラックスが得られます。
特徴
- “6秒吐く”という長い呼気が迷走神経を刺激し、心拍を下げる
- 呼吸のリズムへ集中することで、不安のループを自然に遮断できる
- 短時間で脳の緊張をゆるめ、広い視野が戻る
効果の根拠
- 長い吐息 → 心拍が落ち着く
- 呼吸リズム → 脳の過活動をストップ
- 横隔膜が動く → 身体の緊張がゆるむ
向いている人
- 緊張が強く、息が浅い人
- 本番の数分前に深く落ち着きたい人
- 3-4-5を試したことがある人
- 面接・プレゼン・司会など、“集中力”も必要な場面
【違いを比較】一目で分かるチャート
| 比較項目 | 3-4-5呼吸法 | 4-2-6呼吸法 |
|---|---|---|
| 難易度 | ◎(かんたん) | ○(すこし長い) |
| 即効性 | ◎ | ○ |
| リラックスの深さ | ○ | ◎ |
| 初心者向け度 | ◎ | △ |
| 緊張リセット | ◎ | ○ |
| 集中力アップ | ○ | ◎ |
どっちが効果ある?
結論:
・初心者→3-4-5
・慣れてきたら→4-2-6
- 3-4-5:緊張の“初期消火”に最適
- 4-2-6:本番前〜練習前の“深い調整”に最適
つまり、
両方使うのが一番強いです。
【使い分けの具体例】
緊張がピーク → 3-4-5を5回
(心拍が高い、手が冷たい、息が浅い)
心を整えたい → 4-2-6を3回
(プレゼン本番前、面接前、練習前)
朝のルーティン → 4-2-6
(気持ちが安定し、1日のパフォーマンスが上がる)
テンプレート例文
3-4-5呼吸をする時の心の呟き
「吐く息が長いほど落ち着く。今、体がリラックスしてきている。」
4-2-6呼吸をする時の心の呟き
「大丈夫。ゆっくり吐けば、心拍が落ち着く。」
- 3-4-5は“まず落ち着くため”
- 4-2-6は“さらに安定させるため”
あがり症の改善には
「短い鎮静」+「深い鎮静」
の両方を使うのがもっとも効果的です。
呼吸法は短時間で緊張を和らげることが可能です。
詳しくは【緊張が一瞬で消える】たった30秒で心を落ち着ける呼吸法|面接・プレゼン・人前で緊張しないコツをご覧ください。
話す前の“声の震え防止”ウォームアップ
声の震えは、緊張や不安だけが原因ではありません。
実は、喉まわりや顔の筋肉が固まっていることが大きな要因です。
この筋肉の緊張をほぐすだけで、声の安定感が格段にアップします。
話す前に1〜2分でできる簡単ウォームアップを習慣化することが、あがり症克服の第一歩です。
呼吸とウォームアップだけでなく、正しい姿勢と体の使い方も緊張を抑える鍵です。
詳しくは緊張を一瞬で和らげる正しい姿勢と体の使い方|人前でも震えない体をつくるコツをご覧ください。
具体的ウォームアップ手順:
- 「あー」ではなく、鼻に響かせる「んー」で喉を震わせる
- 顔の筋肉を上下に軽く動かし、口周りや頬の緊張をほぐす
- 舌を軽く回す(左右・前後・上回しなど)ことで舌・口の動きをスムーズにする
それぞれの動作を、呼吸に合わせてゆっくり行うことがポイントです。
実践例:
“んーー”と鼻に響かせながら10秒キープ×3回。顔と舌の動きを加えて、全体で1〜2分程度。
このウォームアップを行うだけで、声の震えが抑えられ、話すときの自信と安定感が大幅に向上します。
特にプレゼンや面接など、人前で話す前に必ず取り入れると効果的です。
ポイントは、筋肉をリラックスさせることを意識すること。
早口で行ったり、無理に力を入れたりすると逆効果になるため、呼吸と声の響きに集中しながらゆったり行うことが大切です。
声の震えを防ぐには、原因を知ることが最初の一歩です。
詳しくは緊張で声が震える原因と防ぐ方法|本番で落ち着いて話すための準備と対処法をご覧ください。
声の震え防止+呼吸法のセットウォームアップ例
話す前の緊張を一気に和らげるには、筋肉をほぐすウォームアップと、呼吸法で自律神経を整えるの両方を組み合わせるのが最も効果的です。
以下は、初心者でも1〜2分でできる実践例です。
💡 読者へのアドバイス
- 初めての人は、まず3-4-5呼吸と声のウォームアップだけでOK
- 慣れてきたら4-2-6呼吸を追加して、本番直前まで心身を整える
- 毎回同じセットを行うことで「本番前ルーティン」として脳が覚え、緊張が出にくくなる
声が震えるのは、体が緊張モードに入ったサインです。
原因と防ぐ方法の基礎知識は【緊張で声が震える原因と防ぐ方法】でまとめています。
頭が真っ白になる人の「話すテンプレ」
緊張すると“構成”が飛ぶ。
だからテンプレに頼ってOKです。
黄金テンプレ(PREP法)
- Point(結論)
- Reason(理由)
- Example(例)
- Point(再結論)
例:自己紹介
①結論:私はWebマーケティングを担当しているAです。
②理由:前職でSNS運用をしていた経験を活かすためです。
③例:フォロワーを半年で2万人増やした実績があります。
④再結論:今後は御社でも成果を出していきたいと思っています。
テンプレを作っても、実際には緊張で言葉が詰まることもあります。
そんなときに“伝わる話し方の技術”を知っておくと安心です。
詳しくは【緊張しても伝わる話し方|言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術】をご覧ください。
“慣れ”を作るための小さな暴露トレーニング
いきなり大勢の前に立つ必要なし。
段階例(1週間ごとに進むだけでOK)
1週目:店員に自分から質問
2週目:オンライン会議で1回だけ発言
3週目:5分でいいので簡単な説明をする
4週目:少人数でプレゼン練習
例:スタバでの練習
「新作でおすすめの味はどちらですか?」
これだけで“人に声を出す経験値”が増えます。
実践で使える!あがり症克服の例文集
読者が最も困るのは「どう言えばいいかわからない」という部分です。
この章では、実際の場面でそのまま使える話し方テンプレを多数用意しました。
プレゼン、面接、初対面の会話など、多くの人が緊張しやすい場面をカバーしています。
話す内容は覚えても、緊張で言葉が詰まることがあります。
詳しくは緊張しても伝わる話し方|言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術をご覧ください。
プレゼン開始の例文
「少しドキドキしていますが、丁寧にお伝えしますのでよろしくお願いします。」
最初に“緊張している事実”を軽く共有すると楽になります。
初対面の会話例文
「はじめまして。話す前は少し落ち着かないのですが、よろしくお願いします。」
開示すると相手が配慮してくれます。
面接で使える例文
「少し心が高ぶっていますが、準備したことをしっかりお話しします。」
誠実さが伝わり、好印象です。
面接やプレゼンで言葉が詰まっても、印象を下げずに伝える方法があります。
詳しくはスピーチで緊張しても安心!言葉が詰まっても伝わる話し方とプロのテクニックをご覧ください。
あがり症克服のNG行動集
あがり症を改善したいのに、逆効果の行動を無意識にしている人が多いです。
この章では、改善を遅らせる“NG行動”をまとめました。
多くの人が陥りやすいので、必ずチェックしてください。
NG1:緊張をゼロにしようとする
緊張は悪ではなく、集中力を高める味方。
NG2:完璧な文章を暗記しようとする
暗記すると1カ所飛んだ瞬間に全て飛びます。
→ テンプレ(PREP法) で話す方が安全。
NG3:失敗後に自己否定する
「また失敗した…」
→ これが最も脳を“恐怖モード”に戻します。
よくある質問(Q&A)
あがり症の人が必ず抱える共通の悩みがあります。
「どれくらいで治るの?」「本番で急に緊張したときは?」「声の震えは一生続く?」
こうした疑問を放置してしまうと、不安が増えて練習が続かなくなり、改善のチャンスを逃してしまいます。
本章では、実際にあがり症の相談で多く寄せられた質問を11個に厳選し、専門家視点で丁寧に回答します。
科学的根拠・実践経験にもとづいたアドバイスに加え、そのまま使えるテンプレ例文も収録。
“いま、あなたがつまずいているポイント” を確実に解消し、着実に克服へ進むための「安心できる回答セット」です。
Q1. 緊張すると声が震えるのですが治りますか?
治ります。
声の震えは「メンタルが弱いから」ではなく、
喉・肩・胸周りの筋肉が緊張で固まっているだけ です。
つまり、筋肉をゆるめる習慣をつければ、震えは自然と消えていきます。
特に効果が高いのは以下の2つ:
「長く吐く」呼吸法(3-4-5呼吸)
発声前のウォームアップ(鼻に響かせる“んー”練習)
多くの相談者が、この2つを2週間続けただけで
「震えがほぼ出なくなった」と報告しています。
・例文テンプレ
「少し緊張していますが、落ち着いてお話ししますのでよろしくお願いします。」
“緊張を隠さない”ことで楽になります。
Q2. 何年もあがり症ですが、今からでも克服できますか?
はい、何年経っていても克服できます。
あがり症は性格ではなく 「脳が誤って学んだクセ」 だからです。
クセは年齢に関係なく上書きできます。
実際、40代・50代で克服した人は多く、
共通点は 「小さい成功体験から積み重ねた」 こと。
いきなり人前に立つのではなく、以下のステップで十分改善します:
少人数の会議で一言だけ発言
店員に質問
オンライン会議で3行だけ発言
簡単な説明を友人に試す
・ 例文テンプレ
「以前は緊張が強かったのですが、少しずつ慣れる練習をしています。」
Q3. 人前が本当に苦手で、避けてしまいます。どうすれば?
避けるほど悪化します。
脳が「避けた=危険から守れた」と認識してしまうため、
あがり症が強化されてしまうのです。
ただし 無理に人前へ飛び込む必要はありません。
重要なのは
“小さく挑戦 → 成功 → 慣れる” のループ。
本記事で紹介した“暴露トレーニング”を
あなたのペースで段階的に進めていけば、必ず改善していきます。
・例文テンプレ
「緊張はありますが、まずは小さなことから挑戦します。」
過去の出来事が原因で人前を避けてしまう方は、心の傷を癒すことが大きな助けになります。
具体的な心理リセット法は【過去のトラウマを癒す心理リセット法】を参考にしてください。
Q4. あがり症はどれくらいで改善できますか?
一般的な目安は以下の通りです:
軽度(緊張はするが話せる)
→ 2〜4週間で変化を実感
中度(手足の震え・動悸が強い)
→ 1〜2ヶ月
重度(避ける癖が強い)
→ 3ヶ月〜半年
重要なのは、
「毎日10分の練習を続けられるか」。
量ではなく「継続」がすべてです。
・例文テンプレ
「まずは1ヶ月、毎日10分だけ取り組んでみます。」
Q5. 何から練習すれば一番効果的ですか?
初心者が最初にやるべき“優先度の高いトレーニングは3つ”です。
長く吐く呼吸練習(一番即効性)
声のウォームアップ(震え・詰まり予防)
PREP法で話す練習(頭が真っ白を防ぐ)
この3つだけを毎日続けるだけで、
1〜2週間で「あれ?前より楽」と必ず実感できます。
・例文テンプレ
「まずは呼吸・発声・話し方の3つから始めています。」
Q6. 本番で急に緊張したらどう対処する?
以下の3ステップで、一気に落ち着けます。
① ゆっくり息を吐く(5秒)
② 視線を一度だけ資料に落とす
③ “最初の一文”だけを読む
特に③が重要。
最初の一文さえ言えれば、緊張はスッと抜けます。
・ 例文テンプレ
「まず要点からお伝えします。」
(最初の一言を固定しておくとラク)
Q7. あがり症は病気なんですか?病院に行くべき?
多くの人のあがり症は 病気ではありません。
ただし、以下に該当する場合は
「社交不安症(SAD)」の可能性もあるため、専門機関に相談を。
日常生活が困難
発汗・動悸・震えが強すぎる
人前を極端に避ける
食事の場すらつらい
ただし、ほとんどのあがり症は
セルフトレーニングで十分改善可能 です。
・例文テンプレ
「まずは自分で練習してみて、必要に応じて相談を検討します。」
Q8. 初対面の場で頭が真っ白になるのを防ぐには?
頭が真っ白になるのは
「次に何を話すか考えすぎる」ため。
対策は1つ。
“最初の一言テンプレ”を決めておく こと。
たとえば:
「簡単に自己紹介させていただきます。」
「今日はよろしくお願いします。」
“入り口”が決まっているだけで脳がパニックになりません。
・ 例文テンプレ
「まず簡単に自己紹介をさせてください。」
Q9. 大人数の前だと急に緊張が跳ね上がるのはなぜ?
大人数の前では、
脳が 「注目されている=危険」 と判断するためです。
これは人間の本能で、あなただけではありません。
対策は
“視線を顔ではなく眉間と鼻の間に向ける”
これだけで視線の圧が半減します。
Q10. 噛んだり間違えたりしたら終わりだと思ってしまいます。どうしたら?
噛んでも何も終わりません。誰も気にしていません。
人は
「自分の失敗=全員が大きく反応する」
と誤解しがちですが、それは“脳の錯覚”です。
噛んだ時の最適な対処はこれ:
一呼吸おく
微笑む
言い直す
これだけで逆に“余裕のある話し手”に見えます。
・ 例文テンプレ
「すみません、もう一度言いますね。」
Q11. プレゼン中に質問されると動揺します。どう対応すべき?
質問は“攻撃”ではなく“興味の表れ”です。
動揺しないためには、
「質問を受けたときの型」を決めておく のが最も効果的。
● 3ステップの型
① 質問の感謝
② 要点で回答
③ 補足を一文だけ
これだけで誠実で落ち着いた印象になります。
・例文テンプレ
「ご質問ありがとうございます。要点をお伝えすると〜で、補足すると〜です。」
あがり症の悩みは、一つひとつ原因が明確で、
対策も“誰でもできるもの”ばかりです。
今回のQ&Aを読み進めれば、
「自分だけが特別にダメなのではない」
という安心感を得られるはずです。
あがり症は“才能”ではなく“習慣”。
疑問を解消し、小さな成功を積み重ねることで、あなたは必ず克服へ進めます。
プレゼン開始の例文を使っても、いざという場面で言葉が詰まることはあります。
そんな時に役立つ“詰まっても伝わる話し方”は
【スピーチで緊張しても安心!言葉が詰まっても伝わる話し方】で解説しています。
まとめ
あがり症は性格ではなく習慣。
今日からできる小さなトレーニングを積み重ねるだけで、必ず改善します。
緊張しない話し方に効果的な本・アプリ紹介
おすすめ本
- 『人前であがらずに話す技術』(講談社)
- 『一瞬で心をつかむ!話し方の教科書』(ダイヤモンド社)
おすすめアプリ
- 「スピーチ練習」アプリ(声の録音・分析機能付き)
- 「メンタルリセット呼吸法」アプリ(呼吸テンポをガイド)
これらを使うと、毎日の練習が継続しやすくなります。
関連記事:ステップ1 呼吸を整える
話し始める前の深呼吸は、緊張をほぐす最も手軽で効果的な方法です。
吸う・吐くのリズムを整えることで、心拍数が落ち着き、思考もクリアになります。
🫧もっと詳しい呼吸テクニックを知りたい方はこちら
👇 スピーチ前に心を整える呼吸テクニック|緊張を味方に変える1分メソッド
👇 【緊張が一瞬で消える】たった30秒で心を落ち着ける呼吸法|面接・プレゼン・人前で緊張しないコツ
関連記事:ステップ2 話す前の準備をしっかり行う
「準備」は、緊張を減らす最大の武器。
話す内容を整理し、イメージトレーニングをしておくことで、「失敗するかも」という不安を軽くできます。
👇初対面であがらない人の共通点8選|堂々と話せる人が必ずやっている準備と習慣
関連記事:ステップ3 声の出し方と姿勢を意識する
声が小さいと自信がないように見えてしまい、さらに緊張が増す悪循環に。
しっかり息を吸って、姿勢を整えながら発声することで、自然と堂々とした印象になります。
「声が震える」「体がこわばる」ときの対処法はこちら
👇 人前で話すときに緊張しない方法|実践できる7つのステップとNG例
👇緊張を一瞬で和らげる正しい姿勢と体の使い方|人前でも震えない体をつくるコツ
関連記事:ステップ4 実際に話す場数を踏む
緊張は「経験」で和らいでいくもの。
少人数の前で話す練習から始めて、自信を積み重ねていくことが大切です。
練習で得られる「本番に強くなるコツ」を知りたい方はこちら
👇緊張しない話し方を身につける7つのトレーニング法|人前でも落ち着いて話せる実践メソッド
関連記事:ステップ5 本番で緊張した時の対処法
どんなに準備しても、本番では緊張してしまうもの。
そんなときは、「詰まっても印象を落とさない話し方」を知っておくと安心です。
🎤スピーチ中に焦らず乗り切るテクニックはこちら
👇スピーチで緊張しても安心!言葉が詰まっても伝わる話し方とプロのテクニック
関連記事:ステップ6 失敗を恐れないマインドを持つ
緊張の原因は「失敗したくない」という思いが強すぎること。
完璧を目指すよりも、「自分の想いを届ける」ことに意識を向けましょう。
緊張しても印象を落とさない方法をもう一度確認したい方はこちら
👇緊張しても伝わる話し方|言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術
関連記事:ステップ7 心の奥にある「緊張の根」を癒す
過去の失敗体験や「人前で恥をかいた」記憶が、無意識に緊張を生み出している場合があります。
そんな心のクセをリセットすると、本番でも驚くほど落ち着けます。
🌱心のブロックを手放したい方へ
👇過去のトラウマを癒す心理リセット法|怖い記憶を手放し「話せる自分」に変わる具体ステップ
さらに、今日紹介した呼吸法に加えて“即効性の高い呼吸メソッド”をまとめて知りたい方は、【たった30秒で心が落ち着く。医師も推奨するストレス即リセット呼吸法まとめ】もぜひ参考にしてください。
👇