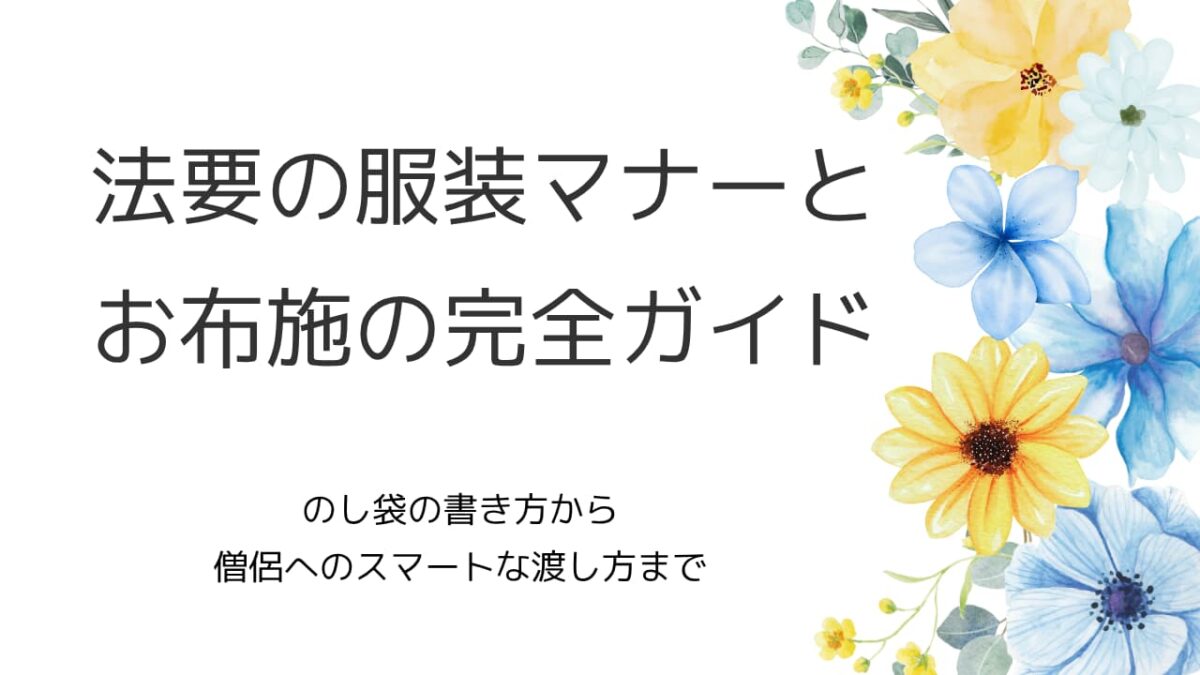「法要に呼ばれたけれど、どんな服装で行けばいいの?」「お布施ののし袋って表書きはどう書くの?」——そんな疑問や不安を抱えていませんか?
法要は、いざ参列するとなると独特の礼儀作法が多く、何を優先すべきか迷いがちです。
本記事では、突然の法要でも慌てずに済むよう、服装マナーからお布施の書き方・渡し方までを網羅的に解説します。
特に検索ボリュームが高い「お布施の書き方」を軸に、現場で恥をかかないためのコツとNG例を豊富に盛り込みました。
この記事さえ読めば、誠意と感謝が伝わる振る舞いが身につき、故人やご遺族に対する敬いが自然と形になります。
ブックマークしておけば、いざというときの安心材料にもなるはずです。
香典返しに添える挨拶状の正しい書き方や文例、送付時期を徹底解説。
失礼のない表現や注意点も紹介しており、法要後のマナーを確認できます。
👇
法要ごとの香典相場(四十九日・一周忌・三回忌)を早見表で確認。
仏式・神式・キリスト教式の表書き、渡し方、マナーの注意点まで徹底解説しています。
👇
香典マナー完全ガイド|金額相場・書き方・渡し方・NG例まで徹底解説
目次
法要とは?基本マナーを押さえよう
法要とは、故人の冥福を祈る仏教の儀式です。
家族や親族が集まり、僧侶の読経を受けて供養を行います。
ここでは、法要の意味や目的、そして基本的な流れやマナーについてわかりやすく解説します。
法要の目的と意味
法要とは、故人の冥福を祈り、遺族や親族が僧侶と共に読経・供養を行う仏教儀式です。
日本では「追善供養」とも呼ばれ、故人が生前に積み残した業を軽くし、来世での幸福を願う意味合いがあります。
宗派ごとに作法は異なるものの、「故人を偲び、心を整える」という本質は共通しています。
遺族・友人・知人が一堂に会し、故人に思いを馳せる場であることを忘れず、礼を尽くす姿勢が何より大切です。
法要の主な種類と時期
故人を偲び、冥福を祈るために行われる法要には、さまざまな種類があります。
それぞれの法要には意味と決まった時期があり、仏教の教えに基づいて執り行われます。
以下に代表的な法要の種類と、一般的な時期の目安をご紹介します。
初七日(しょなのか)法要
時期:亡くなった日を含めて7日目(葬儀当日に行うことも多い)
故人が亡くなってから最初の7日目に営まれる法要で、冥土への旅路の第一歩を供養する重要な法要です。近年では、通夜・告別式と同日にあわせて「繰り上げ初七日」として行うことが増えています。
四十九日(しじゅうくにち)法要
時期:亡くなってから49日目(七七日)
仏教では、故人の魂は七日ごとに閻魔(えんま)王の裁きを受け、49日目に来世が決まるとされています。この日をもって忌明け(きあけ)とする習慣があり、家族や親族が集まり、丁寧に供養を行います。
百か日(ひゃっかにち)法要
時期:亡くなってから100日目
「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、遺族が深い悲しみから立ち直り、日常生活へと戻っていく節目の法要です。四十九日ほど盛大ではありませんが、僧侶を招いてお経をあげてもらうことがあります。
年忌法要(ねんきほうよう)
時期:命日を迎える年ごとに行う法要
年忌法要は故人の命日を迎える節目に行うもので、次のような種類があります:
法要の種類 時期
一周忌 死後満1年 初めての年忌法要で、特に丁寧に営まれる
三回忌 死後満2年 一周忌の翌年に行われる。以降は奇数年ごとに実施されることが多い
七回忌 死後満6年 近親者中心で行うことが一般的
十三回忌 死後満12年 縁のある方々が集まり、故人を偲ぶ機会
十七回忌・二十三回忌・二十七回忌・三十三回忌 年数が経つにつれ簡素化する傾向あり
五十回忌 死後満49年 家によっては「弔い上げ」として最後の法要とする
月命日(つきめいにち)
時期:毎月の故人の命日
毎月の命日に、仏壇にお供えをして手を合わせるのが一般的です。特に初年度は、菩提寺の僧侶にお経をお願いする家庭もあります。
法要の時期は柔軟に対応しても大丈夫
法要は「ちょうどその日」でなくても問題ありません。
遺族や参列者の都合を考慮し、土日などに日程をずらす「繰り上げ法要」や「繰り下げ法要」も一般的です。
ただし、忌明け法要(四十九日など)は遅れないよう配慮が必要です。
法要の服装マナー【遺族・参列者別】
法要に参列する際の服装は、立場や地域の慣習によって異なる場合があります。
遺族と一般の参列者、それぞれにふさわしい服装の基本マナーを確認しておきましょう。
法要は、故人の冥福を祈り、静かに故人を偲ぶ大切な儀式です。
参列者にとって服装は、その場にふさわしい礼節を示す大切な要素のひとつです。
しかし、法要の服装には明確なルールがあるわけではなく、遺族として参列するのか、一般の参列者として招かれるのかによって、求められる服装の格式や配慮の程度が異なります。
また、宗派や地域の風習、法要の規模(自宅での簡素な法要か、寺院で行う正式な法要か)によっても、適切とされる服装に違いがあるため、判断に迷う方も多いのが実情です。
ここでは、遺族と一般参列者それぞれの立場に分けて、法要の場にふさわしい基本的な服装マナーや、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
事前にしっかり確認しておくことで、当日慌てず、心を込めて故人を偲ぶことができるでしょう。
遺族側の服装マナー
遺族は法要を主催する立場であり、服装にもより格式のある礼儀正しい装いが求められます。
特に初七日や四十九日、一周忌などの節目の法要では、正式喪服または準喪服を着用するのが基本です。
男性の服装
- スーツ:黒のフォーマルスーツ(光沢のないもの)
- シャツ:白の無地
- ネクタイ:黒無地(結び目もシンプルに)
- 靴・靴下:黒の革靴、黒の無地靴下
- アクセサリー:結婚指輪以外は外すのが無難
女性の服装
- アンサンブルまたはワンピーススーツ:黒無地の喪服用
- ストッキング:黒無地(肌色はNG)
- 靴:黒で光沢のないパンプス(ヒールは3~5cm程度)
- アクセサリー:真珠の一連ネックレスは許容範囲、華美なものは避ける
子どもの服装
- 制服がある場合は制服で可。
- ない場合は黒やグレー、紺系の落ち着いた服装を心がける。カジュアルすぎないよう配慮を。
季節による調整
夏場の暑い時期でも、半袖や薄手の素材で「黒」「礼節」を意識した服装であれば問題ありません。
ノースリーブや透け感のある素材は避けましょう。
略式喪服と平服の違い
法要の案内状などで「略式喪服」「平服でお越しください」と記載されていることがあります。
どちらも「正喪服」ほど堅苦しくない服装を意味しますが、その意味合いやマナーには違いがあります。
誤解しやすいポイントでもあるため、あらかじめ理解しておきましょう。
略式喪服とは
略式喪服とは、正喪服よりもやや格式を下げた礼装です。
法要や通夜、三回忌以降の法要などに多く用いられます。
- 男性:黒のビジネススーツ(光沢のないもの)に白シャツ、黒ネクタイ
- 女性:黒のワンピース・アンサンブル・パンツスーツなど。露出や華美さを控えたデザインで
あくまで「喪に服している」という意思を表す礼装であり、色や素材、デザインはフォーマル感を重視します。
平服とは
平服とは、「普段着」という意味ではなく、「略式喪服よりもさらに控えめな装い」を指す場合がほとんどです。とはいえ、カジュアルすぎる服装は失礼にあたります。
- 男性:ダークカラーのスーツ(ネクタイも黒か地味な色)
- 女性:黒・紺・グレーなど落ち着いた色のワンピースやセットアップ(過度な露出や装飾は避ける)
案内状で「平服でお越しください」と書かれていても、ある程度のフォーマルさは保つのが無難です。
不安な場合は遺族に事前確認をすると安心です。
宗派・地域による服装の考え方
法要における服装マナーは、基本的なルールのほかに、宗派や地域の慣習によっても異なる場合があります。
知らずにマナー違反となることを避けるためにも、以下の点を把握しておきましょう。
宗派による違い
仏教の宗派によって、法要の作法や考え方が微妙に異なります。
ただし、服装においては大きな違いはない場合が多く、「落ち着いた装い」「故人への敬意」が共通の基本姿勢です。
- 一部の宗派(浄土真宗など)では「死を穢れとしない」考え方から、「喪に服す」という考えが薄く、服装への意識が若干異なる場合もあります。
- 不安な場合は、遺族やお寺にあらかじめ確認することが大切です。
地域による違い
日本各地では、地域によって法要の形式や服装に対する考え方に違いがあります。
- 都市部では略式喪服・平服が主流ですが、地方では正喪服での参列が望ましいとされるケースもあります。
- 地域によっては、色付きの着物や礼服を用いる文化が残っているところもあります。
親戚や知人に確認を取ったり、過去の法要の様子を思い出すなどして、地域に合わせた配慮を心がけましょう。
服装のマナーは、形式だけでなく「思いやりの表現」でもあります。
自分の立場や場の雰囲気を踏まえて、失礼のない装いを心がけましょう。
参列者側の服装マナー
参列者は、遺族に比べてやや控えめな装いで参列するのがマナーです。
準喪服または略式喪服が一般的ですが、法要の規模や故人との関係性によって調整することも可能です。
男性の服装
- スーツ:黒、ダークグレー、濃紺などのダークカラー(派手な柄や光沢のあるものは避ける)
- シャツ・ネクタイ:白シャツに黒ネクタイが基本。ネクタイピンは外す。
- 靴・靴下:黒系で統一。柄のないものが無難。
女性の服装
- ワンピース、セットアップなど:黒やダークカラーで落ち着いたデザイン。肌の露出は控えめに。
- ストッキング:黒か肌色の無地。網タイツや柄入りは避ける。
- 靴:黒系でつま先が隠れるパンプスがベスト。サンダル・ブーツは避ける。
- アクセサリー:必要最低限に。華やかすぎるものはNG。
注意点
- 香水や強い整髪料の使用は避け、身だしなみを整える程度にとどめましょう。
- カジュアルなアイテム(ジーンズ、スニーカー、Tシャツなど)は厳禁です。
どちらの立場でも共通して大切なのは、「故人への敬意を表す心構え」です。
服装を通じてその思いを丁寧に表現することが、何よりのマナーといえるでしょう。
お布施とは?意味と相場を理解する
お布施は、法要を依頼した僧侶への感謝の気持ちを表す大切なものです。
ただし金額や渡し方に迷う方も少なくありません。
ここでは、お布施の意味とその相場についてご紹介します。
法要の際に僧侶へお渡しする「お布施」は、単なる謝礼や支払いではなく、仏教の教えに基づく尊い行い(功徳)のひとつです。
読経や戒名の授与など、法要を円滑に執り行ってもらったことへの感謝の気持ちを形にして表すものとされています。
ただし、普段あまり経験することのない場面であるため、
いくら包めばよいのか?
のし袋はどう選ぶ?
渡すタイミングや作法は?
といった点に迷う方も少なくありません。
この章では、「お布施」の意味と役割を正しく理解したうえで、法要ごとの相場や金額の目安についてもわかりやすくご紹介します。
法要ごとのお布施相場と金額の目安
お布施には明確な「定価」がなく、施主(依頼者)の経済状況や地域、寺院との関係性などによって金額は前後します。
ただし、一般的な相場は存在しますので、目安として参考にしましょう。
初七日・四十九日・一周忌などの法要
最も一般的な法要で、読経と法話をお願いすることが多い場面です。
- 相場の目安:3万円~5万円
- 塔婆供養を含む場合:+3千円~1万円程度(別途包むか、お布施に含める)
- 御車代や御膳料が必要な場合も:それぞれ5千円~1万円ほど
三回忌~七回忌以降の年忌法要
少しずつ規模が小さくなり、参列者も減る傾向がありますが、丁寧な供養を心がけたいものです。
- 相場の目安:2万円~3万円
納骨式・開眼供養・閉眼供養
納骨や仏壇・墓石に関わる儀式で、特別な法要として行われます。
- 相場の目安:2万円~5万円
- 仏壇の開眼供養は住職を本堂から自宅に招くこともあるため、「出張」の意味で御車代を別に包むこともあります。
葬儀・通夜の読経(参考)
葬儀では最も高額なお布施が必要になることが多いです。
- 通夜・葬儀・初七日をまとめて行う場合:20万円~50万円が目安
(※この場合、戒名料が含まれるかどうかも確認しましょう)
なお、相場に迷う場合は親族や檀家の方、寺院に直接たずねるのも失礼にはあたりません。
また、「施主の無理のない範囲で包むこと」が何より大切です。
大切なのは金額そのものよりも、「感謝の気持ちを込めて丁寧に包むこと」です。
お布施の書き方:表書き・裏面・金額の注意点
お布施は、のし袋に入れて丁寧に渡すのが基本です。
表書きや裏面の記載内容、金額の包み方など、失礼のない正しい書き方を具体的に解説します。
お布施の書き方:表書き・裏面・金額の注意点
お布施は、僧侶への感謝の気持ちを丁寧に伝えるためのもの。
したがって、包み方や書き方にも心を込めることが大切です。
ただし、日常的に行うことではないため、
- 「のし袋の表書きはどう書くの?」
- 「裏面に住所や名前は必要?」
- 「お札の向きや枚数にマナーはある?」
といった点に不安を感じる方も多いでしょう。
お布施は単なる金銭のやり取りではなく、仏事ならではの格式と作法が伴うため、細かい部分まで配慮することが求められます。
この章では、以下のような内容について具体的にわかりやすく解説します。
- お布施の正しい表書き(「お布施」と書く位置や文字)
- 裏面に記載すべき住所・氏名・金額の有無
- お札の包み方・新札の使用可否・向きの注意点
- 中袋あり・なしの場合の書き方の違い
- よくあるNG例(表記ミスや金額の書き間違い など)
丁寧な書き方を心がけることで、僧侶に対して失礼がなく、またご自身の気持ちもよりしっかりと伝わるはずです。
形式的に見える部分にも、「供養の心」があらわれると心得ましょう。
お布施の正しい表書き(「お布施」と書く位置や文字)
お布施ののし袋の表書きは、基本的に「お布施」とだけ書きます。
文字は筆ペンで丁寧に、濃くはっきりと書くのが礼儀です。
書く位置は、のし袋の表側中央やや上部が一般的です。
※地域や寺院によっては「御布施」「御礼」など異なる場合もあるため、不安なときは確認を。
裏面に記載すべき住所・氏名・金額の有無
多くの場合、のし袋の裏面に施主の氏名(フルネーム)と住所を記載します。
これは誰からの気持ちかを明確にするためです。
金額は基本的に書きません。
金額を書くと「値札をつける」ような印象を与え、マナー違反とされることが多いです。
お札の包み方・新札の使用可否・向きの注意点
- 新札は避けることが一般的です。
法要の場で新札は「準備していた」印象が強く、急な不幸を想起させるためマナー違反とされる場合があります。
ただし、地域や寺院によっては新札を用いるケースもあるので事前確認を。
- お札の向きは、肖像画が表に見えるようにして入れます。お札の裏側(無地側)を上にして折り曲げるのが正式な包み方です。
- お札は中袋に入れる場合が多いですが、中袋がない場合は直接のし袋に入れても問題ありません。
中袋あり・なしの場合の書き方の違い
- 中袋あり
中袋の表側中央に金額を漢数字で記入し(例:「参萬圓」)、裏側の左下に施主の氏名・住所を記載します。
中袋は白無地の封筒で、のし袋の中に入れます。
- 中袋なし
のし袋の裏面に施主の氏名・住所を記載し、金額は書きません。
よくあるNG例(表記ミスや金額の書き間違い など)
- 表書きに「御布施」以外の不適切な言葉を書く(例:「御礼」や「御車代」と混同する)
- 裏面に金額を書いてしまう
- お札を無造作に折り曲げたり、肖像画が裏向きになるように入れる
- ボールペンで書く、字が乱雑で読めない
- のし袋の汚れや破損を放置する
こうした点に注意し、丁寧な書き方を心がけることで、故人と僧侶に対する敬意が伝わります。
僧侶へのお布施の渡し方:タイミング・作法
お布施はいつ、どのように渡せばよいのでしょうか。
僧侶に失礼のない渡し方やタイミング、言葉遣いのポイントを押さえておきましょう。
法要の大切な儀式のひとつであるお布施の渡し方は、僧侶への感謝の気持ちを示す重要な場面です。
タイミングや渡す際の作法を間違えると、せっかくの気持ちがうまく伝わらなかったり、失礼にあたる場合もあるため、慎重に行いたいものです。
では、具体的にはいつ・どこで・どのように渡すのか、またそのときの言葉遣いやマナーにはどんなポイントがあるのかを押さえておきましょう。
この章では、
- お布施を渡す適切なタイミング
- 手渡しの際の作法や姿勢
- 僧侶に対する言葉遣いのポイント
- お布施以外に必要な場合があるもの(御車代・御膳料など)の渡し方
など、基本のマナーを具体的にご紹介します。
これらを知っておくことで、スムーズで丁寧なやり取りができ、僧侶や参列者にも好印象を与えることができます。安心して法要に臨みましょう。
お布施を渡す適切なタイミング
お布施は、法要や読経が終わったあと、僧侶がお帰りになる前に手渡すのが一般的です。
ただし、寺院や地域によっては、法要開始前や式の受付時に渡す場合もあります。
事前に確認できると安心です。
手渡しの際の作法や姿勢
- お布施は両手で丁寧に包んだのし袋を持ち、相手に向けて差し出します。
- 受け取る僧侶の手が届きやすい高さで差し出し、下を向いたりせず、穏やかな表情で渡しましょう。
- お辞儀をしながら渡すとより礼儀正しい印象を与えます。
僧侶に対する言葉遣いのポイント
渡すときには、「本日は誠にありがとうございました」や「どうぞよろしくお願いいたします」などの感謝やお願いの言葉を添えましょう。
丁寧な言葉遣いを心がけ、宗教的な場にふさわしい落ち着いた口調で話すことが大切です。
お布施以外に必要な場合があるもの(御車代・御膳料など)の渡し方
- 御車代は、僧侶が遠方から来られる場合の交通費として包みます。別ののし袋に入れ、表書きは「御車代」や「御礼」とします。
- 御膳料は法要の際の食事代として包み、表書きは「御膳料」や「お礼」とします。
- これらもお布施と同様、両手で渡し、法要の終了後に一緒に渡すのが一般的です。
これらのポイントを押さえれば、僧侶へのお布施を失礼なく、心を込めてお渡しできます。安心して法要に臨みましょう。
のし袋の選び方と書き方完全図解
お布施を包むのし袋には、宗派や法要の種類に応じた選び方があります。
ここでは、のし袋の選び方と正しい書き方を図解で詳しくご紹介します。
お布施を包むのし袋は、宗派や法要の種類、地域の慣習によって適切なものが異なります。
間違ったのし袋を使うと失礼にあたることもあるため、正しい選び方を知っておくことが大切です。
また、のし袋の表書きや裏面の記載方法もマナーの一部。
これらをきちんと理解し、丁寧に書くことで、僧侶への感謝の気持ちがより伝わります。
この章では、代表的なのし袋の種類や使い分けのポイントを、わかりやすい図解つきで丁寧に解説します。
初心者の方でもすぐに実践できる内容ですので、ぜひ参考にしてください。
法要の種類別にふさわしいのし袋の選び方
法要の種類によって、のし袋の水引や表書きの形式が異なります。
例えば、一般的な法要(四十九日、一周忌など)では、黒白または双銀の水引が使われます。
地域によっては黄白の水引を使うこともあります。
お布施の場合は、紅白の蝶結びは避け、必ず結び切り(ほどけない結び目)が基本です。
例:
- 四十九日法要:黒白結び切りののし袋
- 初盆や一周忌:双銀結び切りののし袋
表書きの正しい書き方・筆文字のポイント
表書きは「お布施」と書くのが基本です。
筆ペンで、読みやすく丁寧に書きましょう。
墨は濃くしっかり、薄すぎず濃すぎずが理想です。
よくある誤り:
- ボールペンやサインペンで書く
- 漢字の間違い(例:「布施」を「施布」と書く)
- 書き損じたまま使う
裏面に書くべき情報とその配置
裏面には、氏名と住所を記載します。
氏名はフルネームで、住所は番地まで正確に。
のし袋の裏面の左下あたりに書くのが一般的です。
金額は書かないのがマナーです。
中袋の使い方と書き方の違い
中袋がある場合は、中袋の表に金額を漢数字で書きます(例:「参萬圓」)。
裏面の左下に施主の氏名と住所を記載します。
中袋がない場合は、のし袋の裏面に氏名と住所を書き、金額は書きません。
よくある間違いや注意点
- 新札をそのまま使う(折り目をつけるのが望ましい)
- 水引の色・種類を間違える(紅白の蝶結びは祝い事用)
- 金額を書く位置を間違える(のし袋の表や裏面に書くのはNG)
- 汚れやしわのあるのし袋を使う
- 表書きと裏面の文字のバランスが悪い
これらのポイントを守れば、失礼のない丁寧なのし袋の準備ができます。安心して法要に臨みましょう。
シーン別お布施の例文集
お布施に添える言葉や封筒に記す文言に悩んだときの参考に。
法要の種類や状況に応じた例文をまとめましたので、シーンにふさわしい表現を選びましょう。
お布施をお渡しするときには、ただ金額を包むだけでなく、心のこもった言葉を添えることが大切です。
しかし、どんな言葉をかければよいか迷うことも多いものです。
ここでは、法要の種類や状況に応じたお布施に添える言葉や、封筒に記す文言の具体的な例文をまとめました。
例えば、四十九日法要や一周忌、初盆など、シーンごとにふさわしい表現を紹介します。
また、葬儀後の挨拶や感謝の気持ちを伝える一言なども合わせてご提案しますので、状況に応じてぜひ参考にしてください。
これらの例文を使うことで、気持ちを丁寧に伝えられ、僧侶や遺族にも好印象を与えることができます。
四十九日法要でのお布施に添える言葉例
「本日はお忙しい中、故人のためにご供養いただき誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。」
一周忌法要でのお布施に添える言葉例
「故人の一年忌法要に際し、ご供養いただきまして誠にありがとうございます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。」
初盆(新盆)でのお布施に添える言葉例
「初盆に際しまして、ご供養いただき深く感謝申し上げます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。」
これらの言葉は封筒に添える短いメッセージカードや、直接お渡しするときの一言としても使いやすいものです。
また、状況に合わせて、「心ばかりですが」や「ささやかではございますが」などの丁寧な言い回しを加えても良いでしょう。
NG例と気をつけたいポイント
お布施には守るべきマナーがあります。うっかり失礼になってしまうNG例や、注意すべきポイントをあらかじめ知っておくことで、安心して準備ができます。
NG例と気をつけたいポイント
お布施を準備・渡す際には、見落としがちなマナー違反が意外と多くあります。
失礼と受け取られないよう、以下のNG例と注意点をしっかり押さえておきましょう。
【NG例】
- お札が折れ曲がっている・汚れている
新札でなくてもよいですが、清潔でシワや汚れのないものを使いましょう。
- 表書きをボールペンや鉛筆で書く
筆ペンや毛筆で丁寧に書くのが基本です。
- のし袋の水引が紅白の蝶結びになっている
お布施には結び切りの黒白か双銀を使います。
- 金額をのし袋の表に書く
金額は中袋に漢数字で書くか、書かないのが一般的です。
- 新札をそのまま使い、折り目をつけていない
折り目をつけておくことで「慶事用ではない」という意味になります。
- 渡すタイミングや場所を間違える
法要の開始前や終了後に、僧侶に直接手渡しするのがマナーです。
【気をつけたいポイント】
- 地域や宗派の慣習を事前に確認する
- 渡すときは両手で丁寧に差し出す
- お布施以外に御車代や御膳料が必要な場合があることを把握する
- のし袋は清潔でシワのないものを選ぶ
これらを守ることで、僧侶やご遺族に対して失礼のない、誠実な対応ができます。安心して法要に臨みましょう。
よくある質問(FAQ)
お布施や法要に関しては、誰もが一度は疑問に思うことがあるものです。ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1:お布施の相場はいくらぐらいが適切ですか?
A:地域や宗派、法要の種類によって異なりますが、一般的には○○円〜○○円が目安です。
詳しくは法要の種類ごとの相場を参考にしてください。
Q2:お布施は新札を使うべきですか?
A:新札でなくても問題ありませんが、折り目をつけて使うのがマナーとされています。
Q3:法要の服装で遺族と参列者で違いはありますか?
A:あります。
遺族は略式喪服や正式喪服を着用し、参列者は地域の慣習に沿った平服や略式喪服が一般的です。
Q4:のし袋の選び方に決まりはありますか?
A:はい。
お布施用ののし袋は結び切りの黒白か双銀の水引が使われます。
紅白の蝶結びは避けましょう。
Q5:お布施はどのタイミングで渡せばよいですか?
A:法要の開始前や終了後に、僧侶に直接両手で渡すのが基本です。
まとめ
お布施のマナーは、相手への敬意を形にする大切な所作です。
ここまでの内容をふり返りながら、法要当日に落ち着いて対応できるようにしておきましょう。
・香典を包む際は金額や渡し方だけでなく、香典返しのマナーも押さえておくと安心です。
香典返しには、贈るタイミングや添える挨拶状の文面にルールがあります。
失礼のない文章例や送付タイミングを詳しく解説した記事は以下からご覧いただけます。
👇
・香典や香典返しとあわせて押さえておきたいのが、法事・法要の案内状の書き方です。
四十九日、一周忌、三回忌など、それぞれの法要に応じた文面やマナーを知っておくと、遺族や参列者に失礼なく案内できます。
具体的なテンプレートや文例も紹介されています。
👇
法事・法要案内状の書き方決定版|四十九日・一周忌・三回忌対応テンプレート付き
・法要ごとの香典相場(四十九日・一周忌・三回忌)を早見表で確認。
仏式・神式・キリスト教式の表書き、渡し方、マナーの注意点まで徹底解説しています。
👇
法要の香典相場とマナー|四十九日・一周忌・三回忌ごとの金額早見表と宗教別注意点
お布施、供物、線香、手土産など、法要当日に必要な持ち物を一覧化。
チェックリスト付きで漏れなく準備できます。
👇
初めての法要準備ガイド|日程・手順・持ち物一覧とマナー・NG集付き
香典の郵送方法だけでなく、同封する添え状の書き方も知っておきたい方は、こちらをご確認ください。
👇
香典を郵送するマナーと現金書留の送り方|失礼にならない添え状文例付き
香典の金額相場(両親・親族・友人別)、表書きや中袋の書き方、渡すタイミング、やってはいけないNGマナーまで徹底解説。
葬儀や法要に参列する前にチェックしておきましょう。
👇