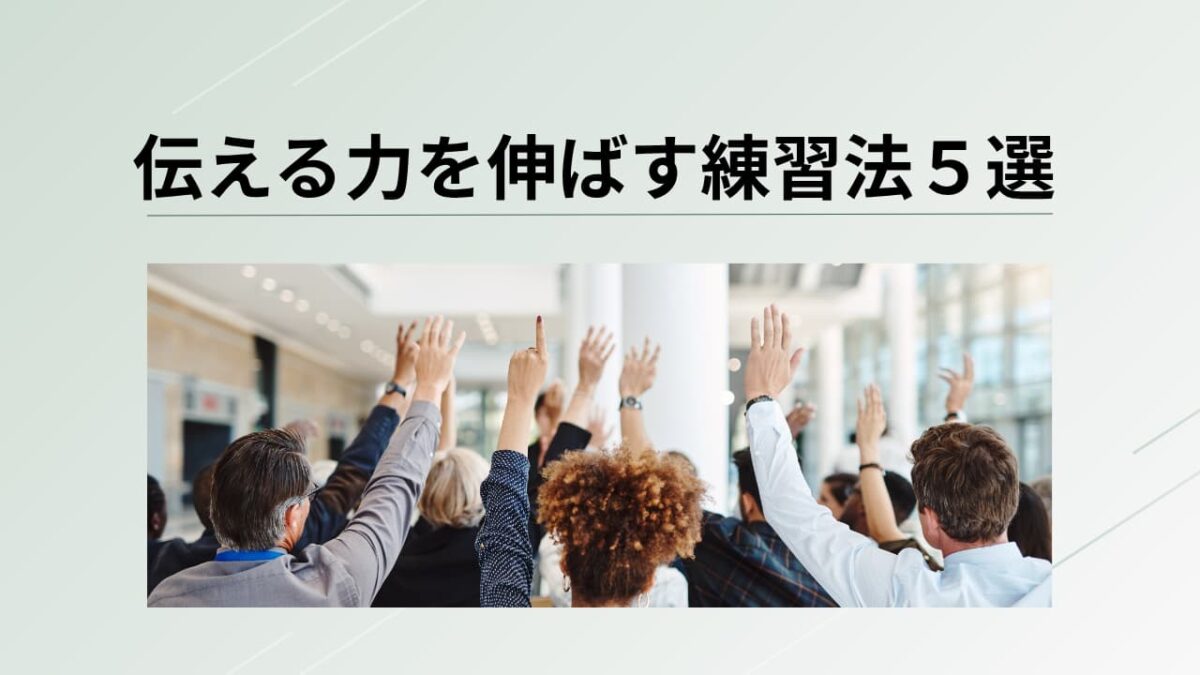「思っていることをうまく言葉にできない」「話しても相手に伝わっていない気がする」――そんな“伝わらない会話”にモヤモヤを感じることはありませんか?
けれど安心してください。
伝える力は生まれ持ったセンスではなく、練習によって確実に伸ばせるスキルです。
この記事では、会話が苦手という方でも今日から実践できる「伝える力を伸ばす練習法5選」を、具体的な例文とともにご紹介します。
さらに、やってはいけないNG例、および日常に取り入れやすい習慣まで含めて丁寧に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
…この型はビジネスでも日常会話でも使える万能フォーマットです。詳しい方法は「話が整理される構成の作り方」の記事でご紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。
…録音してもそのまま聞き流してしまい「自分は話せてる」だけで終わる。「聞く」ことを放置すると成長につながりません。録音・録画を活用した「自分の話し方を客観視する方法」もおすすめです。
…まずは場を大きく捉えすぎないことがポイントです。人前で話すシーンに強くなりたい方は、こちらの「人前で緊張しない話し方トレーニング」記事も併せてお読みください。
目次
- 1 伝える力とは?なぜ重要なのか
- 2 会話が苦手でも大丈夫!伝える力は“練習”で伸ばせる理由
- 3 伝える力を伸ばす練習法5選(実践編)
- 4 伝える力を高める「日常習慣」3つ
- 5 NG集:やってはいけない伝え方のクセ
- 6 よくある質問(Q&A)
- 6.1 Q1. 「人前で話すと緊張して頭が真っ白になります。どうすればいいですか?」
- 6.2 Q2. 「上司や取引先にうまく伝えられません。ビジネス向けの練習法はありますか?」
- 6.3 Q3. 「会話の途中で何を話せばいいかわからなくなります…」
- 6.4 Q4. 「伝える力を伸ばしたいけど、話す機会が少ない場合はどうすればいいですか?」
- 6.5 Q5. 「会話が一方通行になってしまいます。どうすれば双方向になりますか?」
- 6.6 Q6. 「相手の反応が薄いとき、どうリアクションすればいいですか?」
- 6.7 Q7. 「相手に誤解されやすいです。伝え方の工夫はありますか?」
- 6.8 Q8. 「声が小さい・通らないとよく言われます。改善できますか?」
- 6.9 Q9. 「人に説明するとき、話が長くなってしまいます。」
- 6.10 Q10. 「話す内容をすぐ忘れてしまいます。記憶を保つコツはありますか?」
- 6.11 Q11. 「話している途中で相手に遮られることが多いです。どうすればいいですか?」
- 7 まとめ|伝える力は“毎日の少しの意識”で変わる
- 8 内部リンク配置案
伝える力とは?なぜ重要なのか
「伝える力」の本当の意味
「伝える力」という言葉を聞くと、「話し上手」や「プレゼンがうまい人」をイメージするかもしれません。
しかし本質的には「自分の考えや気持ちを相手に分かりやすく届ける能力」です。
つまり、相手が“何を言おうとしているのか”をすぐ理解できるように物事を整理して言葉にできることが、伝える力なのです。
たとえば、「今日ね、ちょっと嫌なことがあって…」という話が続くより、「今日は上司とのミーティングで意見が食い違って困りました。その理由は…」と話し始めた方が、聞く側は“どんな話か”を予想しやすくなります。
このように、自分の伝えたいことを構造化して、相手が受け取りやすいかたちにするのが「伝える力」です。
伝える力がある人とない人の違い
伝える力が“ある人”と“ない人”の違いはどこにあるでしょうか。
以下のような特徴があります。
- 伝える力がある人:結論を先に述べ、理由や具体例を続ける/言葉を整理して相手に提示する/相手の立場や反応を少し意識して話す
- 伝える力がない人:話が行き当たりばったりで結論が曖昧/具体例ばかりで何が言いたいか伝わらない/相手の理解度を気にせず続ける
たとえば、会議で「この企画、やりますか?」と聞いて、「えーと、あの、先週資料を作って…」と話し始める人は、相手に「何について?」と疑問を持たせてしまいやすいです。
逆に「この企画を進めたいです。理由は〜。具体的には〜」と順序立てて話す人は、話の流れがスムーズです。
伝える力が高い人が得られるメリット
伝える力を高めると、以下のようなメリットがあります:
- 人間関係がスムーズになる:誤解が減り、相手との信頼関係が築きやすい
- ビジネスでの成果アップ:提案や報告が明確になり、承認や理解を得やすくなる
- 自信が持てるようになる:自分の言いたいことを伝えられると、話すこと自体のハードルが下がる
- ストレス軽減:言えずにモヤモヤすることが減り、頭の中が整理される
このように、ただ“話せる”ではなく“伝わる”話し方ができると、仕事・プライベート問わず大きな好影響があります。
会話が苦手でも大丈夫!伝える力は“練習”で伸ばせる理由
脳の仕組みから見た「言語化のコツ」
人は自分の考えを言葉にする瞬間、脳が「内的に整理」→「言語化」→「発話」というプロセスを踏んでいます。
言語化が苦手な人は「言いたいけど言葉にならない」「頭の中はモヤモヤしているけど話せない」状態です。
ですが、この言語化のプロセスは訓練可能です。
近年のSEO・コンテンツ作成の観点でも、構造をもった話し方/書き方こそが読み手・聞き手にとって理解しやすく評価されるとされています。
つまり、話す前に「何を言うか」「順序はどうか」を意識するだけで、伝える力は確実に高まります。
人見知り・口下手でも伸ばせる思考法
「私は口下手だから…」という人でも、考え方を少し変えれば伝える力は伸びます。
ポイントは以下の3つ。
- 小さな場面で“伝えやすい言葉”から始める:例えば「今日の一番嬉しかったこと」を30秒で人に話す。
- 相手の反応を“観察”する習慣を付ける:「あ、今相手は分かってくれた」「あ、首をかしげた」などに気づく。
- 完璧を求めない:自然に伝わるのが目的で、流暢なスピーチではなく「相手に分かる」話し方で十分。
こうした思考を持つことで、会話自体が練習の場になり、「人に伝える」ことが段々と楽になります。
伝える力を伸ばす練習法5選(実践編)
【練習法①】1日3分の「要約トレーニング」
話を整理する力が伝える力の土台です。
毎日たった3分、「今日あった出来事を一言でまとめてみる」――これだけで言語化能力が鍛えられます。
解説:
方法は簡単です。
1)1日の終わりにその日の出来事を思い出す。
2)「何が一番印象的だったか」を言葉にする。
3)その言葉を30秒以内で説明する。
例えば:
「今日は上司に褒められました。理
由は、自分が提案した資料が分かりやすかったからです。」
このように、出来事を「結局どうだったか」にフォーカスする習慣をつけると、自然と話の“核”が整理されて伝えやすくなります。
例文:
- 「今日のニュースでは○○社が新製品を発表しました。注目ポイントは、価格が思ったより安いことです。」
- 「家族との夕食で久しぶりに和やかな時間が取れました。きっかけは妹が最近就職してから四人そろったからです。」
NG例:
「今日はね、なんかいろいろあって疲れた。で、上司がなんか言ってて、そのあと…」
このように結論が見えず、話がモヤモヤしたままだと“伝わる話”にはなりません。
【練習法②】“結論→理由→具体例”で話すクセをつける
相手が理解しやすい話には「型」があります。
結論を先に言い、その後に理由と具体例をつけることで、話が整理されるだけでなく、説得力も生まれます。
解説:
この型はビジネスでも日常会話でも使える万能フォーマットです。
例えば:
「私はこの企画に賛成です。なぜなら、コストが下がるうえに社員の負担も減るからです。実際に昨年同様の施策で成果が出ています。」
具体的に①結論:『賛成です』→②理由:『コストが下がる』『社員の負担も減る』→③具体例:『昨年同様の施策で成果』という流れです。
例文:
- 「この映画はおすすめです。というのも、ストーリーが予想以上に深くて、最後まで飽きませんでした。実際に上映後に涙を流す人も多かったです。」
- 「今朝ランニングを始めました。理由は体調が少し優れなかったためです。昨日ウォーキングした時より今日は心拍数も安定しています。」
- NG例:
「この映画…あー、なんかよかったんです。えっと、登場人物が多くて…」
結論が曖昧で、何を伝えたいのかがぼやけてしまっています。
【練習法③】鏡の前で「話す練習」をする
- 表情…眉間にシワ寄ってないか?
- 声のトーン…大きすぎないか、小さすぎないか?
- 姿勢…背筋が伸びているか?
例文:
鏡の前で「今月の売上について報告します。先月比10%増でした。理由は新規顧客が増えたからです。」と話しながら、自分の表情・声・姿勢を観察します。
このような練習を週に2~3回繰り返すと、無意識に“話す姿勢”が整っていきます。
NG例:
話しているうちに目線が下がり、声が小さくなり、「えーっと」が連発してしまう。こうしたクセがあると、聞き手に「自信がない」「何を言いたいか分からない」と受け取られやすくなります。
【練習法④】自分の話を録音して“客観視”する
自分の話し方を“他人の耳で聞く”ことで、気づかなかったクセや改善点が明らかになります。
録音はスマホでもOK。
定期的に習慣にすることで、伝える力が確実にアップします。
解説:
手順は以下の通り。
- スマホなどで自分の話を録音(1〜2分程度)
- 聞き返してみて「どこが聞きづらいか」「話がスムーズか」をチェック
- 改善したい点をメモし、次回に意識して話す
例えば、話が早すぎて聞き取りづらい/「えーっと」が多い/声のトーンが単調、など。
録音内容:「今日のプロジェクト報告ですが、あの、昨日までに資料をまとめて…」。聞き直して、「えーっと」が繰り返されていたので次回「昨日までに資料をまとめました。ポイントは…」と整理して話してみる。
こうした “聞く→気づく→改善” のサイクルが、習慣化されれば自分の話し方がどんどん磨かれていきます。
NG例:
録音してもそのまま聞き流してしまい「自分は話せてる」だけで終わる。「聞く」ことを放置すると成長につながりません。
【練習法⑤】相手の反応を観察するトレーニング
伝える力は「自分が話すこと」だけではなく、「相手がどう受け取るか」を意識することでも磨かれます。
会話中に“相手の表情・うなずき・目線”を観察する習慣をつけることで、より伝わる話し方が身につきます。
解説:
ポイントは以下の通り。
- 相手がうなずいているか、目をそらしていないか
- 話を聞いている時の表情・雰囲気
- 自分の言葉に反応があるか(「そうですね」と返ってくるか)
これらを確認しながら話すと、相手の理解度や興味の度合いが掴め、「もう少し丁寧に説明しよう」「このポイントを飛ばしても大丈夫だな」と反応に応じてアジャストできます。
- 例文:
会話例:「この商品のメリットは2つあります。まず…」と話し始めた時、相手が目をキョロキョロしていたら「少し難しそうかな?」と感じ、 「つまりこういうことです」と補足して話す。これで相手に伝わる確率が上がります。
NG例:相手の反応を全く気にせず延々と話し続ける。
結果として「話が長い」「何を言ってるのか分からない」と受け取られてしまいます。
伝える力を高める「日常習慣」3つ
読書・ニュースで「言葉の引き出し」を増やす
- 読書:ジャンルを問いません。エッセイ、ビジネス書、小説など。読んだあと「印象に残った言葉」を書き出してみる。
- ニュース:記事を読んだら、「結局何が言いたかったのか」を自分の言葉でまとめる。
書籍を読んで「敬意と信頼は、築くものではなく育むものだ」という言葉が印象に残った。→自分の言葉に:「人間関係は、一朝一夕ではなく日々の信頼の積み重ねで育つものです。」
このように“言葉を自分の言葉に変える”練習が、自然な伝え方に繋がります.
NG例:
ニュースや本を読んでも“ただ読み流し”で終わる。結果、新しい言葉も構成も定着しません。
雑談で“練習の場”を増やす
気構えず、日常的な雑談も伝える力を磨く場になります。
5分でもいいので、「ちょっと話してみる」ことをルーティンにすれば、自然と話す・伝えることのハードルは下がっていきます。
解説:
方法としては:
- 朝の挨拶+「昨日何してた?」を続ける
- 昼休み、同僚に「最近何か面白いことあった?」と聞く
- 家族と夕食中に「今日、何が一番嬉しかった?」と共有する
こうした“軽い話”こそ、結論→理由→具体例の構成を練習する絶好の機会です。
例文:
同僚:「昨日何してたの?」
あなた:「夕方ジョギングに行きました。なぜなら運動不足を感じていたからです。走ってみたら意外と気分がスッキリしました。」
軽い雑談でも、伝わる話し方を意識すれば練習になります。
NG例:
「特に何も」だけで終わってしまう。話す機会を逃してしまい、自分の言葉を整理するクセがつきません。
「うまく話そうとしない」意識を持つ
伝える力を伸ばす上で意外に大切なのが、「うまく話そうとしない」ことです。
力みすぎると逆に言葉が出なくなったり、相手に伝わりづらくなったりします。
気楽に、でも意識的に話す、というバランスが鍵です。
解説:
- 完璧な話を目指さない:「間違えても大丈夫」「伝われば良い」くらいの気持ちで。
- 相手を“理解者”だと思う:形式ばらず、まずは「伝えたいこと」を伝えることがスタート。
- フォーマル/非フォーマルを意識:かしこまる必要がない相手なら、少しくだけた表現もOK。緊張がほどけ、自然な話し方になります。
例文:
「今日はちょっと失敗しちゃって…だけど、そこでこう思ったんです」という素直な言い方。
話し方が上手くないと感じても、相手に「伝えようとしてるんだな」という姿勢が見えれば、理解は得られます。
NG例:
「絶対に間違えたくない」「完璧に話さなきゃ」というプレッシャーを自分にかけすぎて、結果として声が小さくなったり、話が途切れてしまったりというパターン。
NG集:やってはいけない伝え方のクセ
- 話が長くて何が言いたいのか分からない
- 結論を後回しにしてだらだら話す
- 相手の反応を気にせず一方的に話す
- 声を小さく、モゴモゴ話す/表情が硬いまま話す
これらは聞き手の理解や関心を阻害します。意識的に避けていきましょう。
よくある質問(Q&A)
伝える力を鍛えようとすると、多くの人が「緊張」「言葉が出ない」「話がまとまらない」といった壁にぶつかります。
この章では、そんな悩みに対して実践的なアドバイスと、すぐに使えるテンプレートを紹介します。
あなたが会話で自信を持てるように、ひとつずつ丁寧に解説していきましょう。
Q1. 「人前で話すと緊張して頭が真っ白になります。どうすればいいですか?」
A1.
緊張は「失敗したくない」という思いが強いときに起こります。
まずは、場を大きくとらえず「1人の相手に話す」と意識を切り替えましょう。
次の3ステップで緊張をやわらげられます。
- 小さな成功体験を積む: 家族や同僚との1対1の会話で先に話す練習を。
- 話す前に3秒深呼吸: 頭と体をリセットして脳を落ち着かせます。
- 完璧を求めない: 「100点よりも、伝わればOK」という心構えを持つことが大切です。
テンプレート例文:
「緊張していますが、まずは自分の言葉で伝えたいと思います。」
繰り返し使うことで、自然に落ち着いて話せるようになります。
Q2. 「上司や取引先にうまく伝えられません。ビジネス向けの練習法はありますか?」
A2.
ビジネスでは「結論から話す」ことが最も重要です。
人は最初の15秒で話の価値を判断します。
次の構成を意識しましょう。
- 結論 → 理由 → 提案 の順で話す
- 相手の関心を想定して内容を調整する
(上司なら「コスト」「成果」、取引先なら「メリット」「信頼」) - 口頭で話す前に、メールやメモで整理しておく
テンプレート例文:
「この企画を進めたいです。
理由はコスト削減と作業効率の向上が見込めるためです。
そのために、まずは試験導入から提案します。」
NG集:
× 専門用語を多用する
× 前提を説明しない
× 結論が最後まで出てこない
Q3. 「会話の途中で何を話せばいいかわからなくなります…」
A3.
「話を続けよう」と思うと焦りや沈黙が生まれます。
代わりに“相手の話を引き出す”ことに意識を向けましょう。
おすすめはこの3つ:
- オウム返し:「そうなんですね」「つまりこういうことですか?」
- 質問で広げる:「その後どうなりましたか?」「どうしてそう思われたんですか?」
- 結論を先に言う:「私もそう感じました」「実は似た経験があります」
テンプレート例文:
「なるほど、ということは○○ということですね?」
こうした“相手と一緒に会話を作る”意識を持つと、沈黙が怖くなくなります。
Q4. 「伝える力を伸ばしたいけど、話す機会が少ない場合はどうすればいいですか?」
A4.
実際に人と話さなくても練習は可能です。
おすすめは“自己対話型トレーニング”。
鏡の前で話す、日記に書く、音声メモに残すだけでも効果があります。
- 鏡の前で話す:表情や姿勢をチェックしながら伝える練習。
- スマホ録音:声のトーン・話すスピードを客観的に確認。
- 日記に要約:文章化することで思考整理が上手になります。
テンプレート例文(日記形式):
「今日は上司に報告したい内容をまとめて話してみた。
最初に結論を言うことで、よりスムーズに伝えられた。」
Q5. 「会話が一方通行になってしまいます。どうすれば双方向になりますか?」
A5.
会話のキャッチボールができない人は、“相手に問い返す習慣”が足りていません。
次のポイントを意識してみましょう。
- 相手の感情に反応する:「それは嬉しかったですね」「大変でしたね」
- 具体的に尋ねる:「そのときどうしましたか?」
- 話題を少し広げる:「ちなみに最近はどうですか?」
テンプレート例文:
「へえ、そうだったんですね。ちなみに、そのときどう感じましたか?」
NG例:
× 自分の話ばかりする
× 相手の話を途中で遮る
× 相槌だけで終わる
Q6. 「相手の反応が薄いとき、どうリアクションすればいいですか?」
A6.
反応が薄い=理解していないとは限りません。
ポイントは「聞き手の表情を観察して、ペースを合わせる」こと。
- 相手が無表情なら、話を短く区切り質問を交える
- うなずきが少ない場合は、「ここまで大丈夫ですか?」と確認
- 話すスピードを相手の呼吸に合わせてみる
テンプレート例文:
「少し早口だったかもしれませんが、ここまで伝わっていますか?」
Q7. 「相手に誤解されやすいです。伝え方の工夫はありますか?」
A7.
誤解される人の多くは「主語」と「目的」が曖昧です。
次の3点を意識するだけで改善します。
- 主語を明確にする:「私は」「会社として」「チームで」
- 目的を先に言う:「〜を改善したいので」「〜を確認したいので」
- 感情より事実を優先する:「○○が起きた」→「だから○○が必要」
テンプレート例文:
「私の意図としては、作業の効率を上げたいという点です。」
NG例:
× 「なんでやってくれないの?」(感情的)
× 「これ違うんだけど」(曖昧)
Q8. 「声が小さい・通らないとよく言われます。改善できますか?」
A8.
声の大きさはトレーニングで変えられます。
“喉から出す”のではなく、“お腹(腹式呼吸)”で話すことが重要です。
- 毎朝、深呼吸+発声練習:「あ・い・う・え・お」を腹から発音
- 録音して聞くと改善点が見えやすい
- 姿勢を正すだけでも声の通りが良くなります
テンプレート例文(練習用):
「おはようございます! 本日は○○についてご説明します。」
最初は大げさに感じても、続けるうちに自然に通る声になります。
Q9. 「人に説明するとき、話が長くなってしまいます。」
A9.
話が長くなる人は、「要点を整理していない」ケースが多いです。
以下の順序で話すと、聞き手が理解しやすくなります。
- 結論(最初に):「○○が結論です。」
- 理由(なぜなら):「理由は○○だからです。」
- 具体例(たとえば):「たとえば○○の場合です。」
テンプレート例文:
「結論から言うと、この方法が最も効率的です。
理由はコストを抑えつつ成果が出せるためです。
たとえば昨年のA社では同様の結果がありました。」
Q10. 「話す内容をすぐ忘れてしまいます。記憶を保つコツはありますか?」
A10.
伝える力には「思考の整理」が欠かせません。
話す前に3つのキーワードをメモしておくと、忘れにくくなります。
- 「結論」「根拠」「具体例」を一言ずつ紙に書く
- 話の途中で目線を外して思い出す癖をつける
- 1分前に「何を伝えたいか」を口に出して確認する
テンプレート例文(準備用メモ):
・結論:採用基準の見直しが必要
・理由:応募者の質が変化
・例:前期データの傾向
Q11. 「話している途中で相手に遮られることが多いです。どうすればいいですか?」
A11.
遮られる原因は「話が長い」「前置きが多い」ことがほとんどです。
相手の理解を優先する構成を心がけましょう。
- 先に「要点から伝える」
- 遮られても焦らず「ありがとうございます、続けてもよろしいですか?」と丁寧に返す
- 話の区切りを短くし、途中で質問を挟む
テンプレート例文:
「ありがとうございます。今の部分を補足してもよろしいですか?」
丁寧さと落ち着きを意識すれば、相手も最後まで聞く姿勢になります。
悩みを感じる瞬間こそ、伝える力を伸ばすタイミングです。
焦らず一つずつ実践していくことで、「話せる」ではなく「伝わる」自分に変わっていきます。
- 「話し方を変える第一歩」 → 内部リンク:
/how-to-start-speaking/
→ 本文例:「話す前に整理するコツは、こちらの記事『話し方を変える第一歩』で詳しく解説しています。」 - 「緊張しないスピーチ術」 → 内部リンク:
/speech-nervous/ - 「ビジネスで伝わる言葉選び」 → 内部リンク:
/business-communication/
まとめ|伝える力は“毎日の少しの意識”で変わる
伝える力は一回で劇的に変わるわけではありません。
大切なのは習慣化と振り返りです。
毎日少し、3分からでも良いので「自分の話し方を整理する」「相手を意識する」ことを継続しましょう。
内部リンク配置案
- 「結論→理由→具体例」の話し方を深掘りした記事:アンカーテキスト「話が整理される構成の作り方」
- 録音・動画を使った話し方改善の記事:アンカーテキスト「自分の話し方を客観視する方法」
- 緊張対策・人前で話すコツの記事:アンカーテキスト「人前で緊張しない話し方トレーニング」