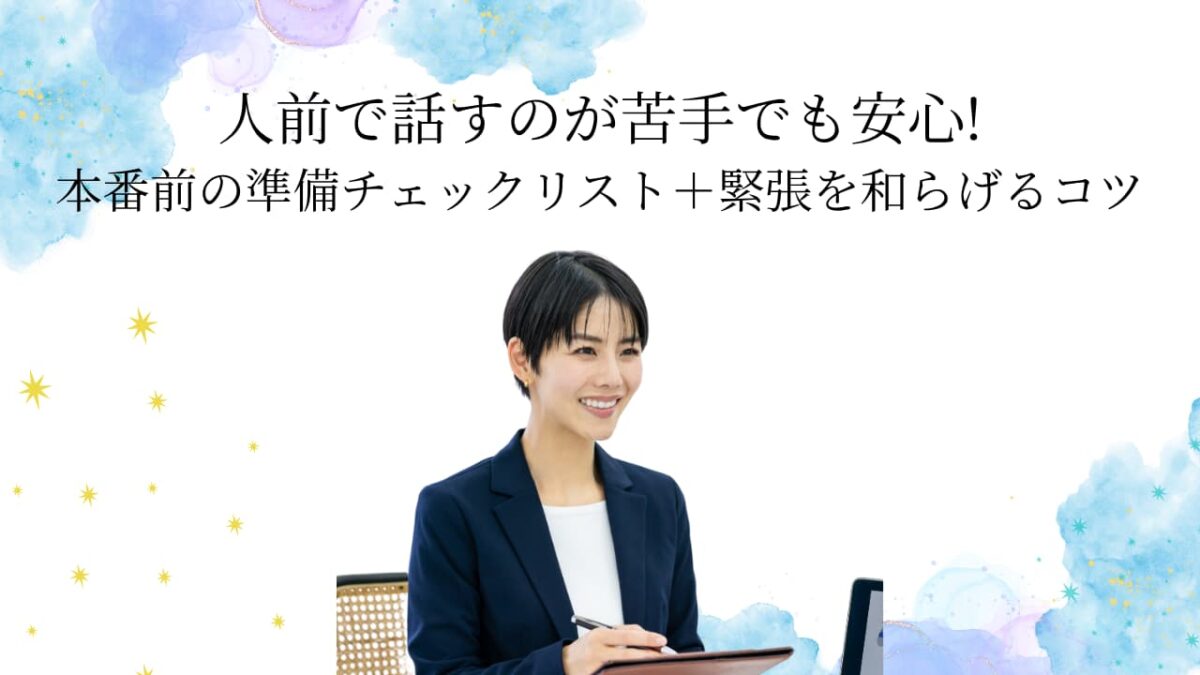人前で話すのが苦手な方にとって、プレゼン・会議・スピーチなどは大きな壁かもしれません。
「緊張で声が震える」「何を言えばいいか分からなくなる」「時間オーバーしてしまう」……そんな悩みを抱えている人は多いでしょう。
ですが、その不安の多くは“準備”を丁寧にすることで大きく軽減できます。
本記事では、話すのが苦手な人でも安心して本番を迎えられるよう、ステップごとの準備チェックリストを詳しく解説します。
さらに、緊張対策の即効テクニック、NG例、実際に使える例文まで網羅。
あなたの「人前で話す自信」を育てるためのガイドとして、ぜひ最後まで読んでください。
目次
- 1 人前で話すのが苦手な理由とは
- 2 本番前の準備チェックリスト
- 3 話す内容を「結論 → 理由 → 具体例」で整理する
- 4 原稿を「読み上げるため」ではなく“練習のため”に作る
- 5 制限時間内に話せるかタイマーで練習する
- 6 本番直前の“緊張対策”チェックリスト
- 7 深呼吸より効果が高い「4-2-6呼吸」
- 8 姿勢を整えて“声の出る身体”にする
- 9 直前に読むべき“3行スクリプト”を準備する
- 10 やってはいけないNG集
- 11 4原稿を丸暗記しようとする
- 12 早口で話してしまう
- 13 アイコンタクトが極端に少ない
- 14 話すのが苦手でも使える具体例(例文つき)
- 15 NG(やってはいけない)集:準備・本番で失敗しやすいポイント
- 16 よくある質問(Q&A)
- 16.1 Q1. 本番で頭が真っ白になったらどうすれば良い?
- 16.2 Q2. 声が震えるのを止めたいです
- 16.3 Q3. 相手の視線が怖くて目を合わせられません
- 16.4 Q4. 噛んだり言い間違えたりしたらどうすればいい?
- 16.5 Q5. 手が震えて原稿が持てません
- 16.6 Q6. プレゼンの最初の一言が緊張で出ません
- 16.7 Q7. 説明が長くなってしまいます。短く話すコツは?
- 16.8 Q8. 練習ではうまく話せるのに本番で崩れます
- 16.9 Q9. 途中で何を話しているか分からなくなります
- 16.10 Q10. 緊張しない人なんて本当にいるの?
- 16.11 Q11. 本番前にできる“最強の準備”はありますか?
- 16.12 Q12. 声が小さい、滑舌が悪いのですが、どう改善すればいいですか?
- 16.13 Q13. 原稿を読むのは本当に良くないですか?
- 16.14 Q14. 場数を踏む以外に上達する方法はありますか?
- 16.15 Q15. 途中で“上がって”しまった時はどうすればいい?
- 17 まとめ:準備すれば誰でも話せるようになる
- 18 緊張しない話し方に効果的な本・アプリ紹介
人前で話すのが苦手な理由とは
人前で話すのが苦手な人は、「話す能力が低い」わけではありません。
実際には、ほとんどの人が“環境”や“過去の経験”によって緊張しやすくなっているだけです。
この章では、人がなぜ緊張するのか、なぜ上手く話せないと感じるのか、心理学や行動科学に基づいて分かりやすく解説します。
原因がわかれば、自分の課題を正しく把握でき、対策も明確になります。
まずは「なぜ話せないのか?」という根本原因を理解するところから始めましょう。
“失敗したらどうしよう”という予期不安
多くの人が本番前に抱くのは「失敗への想像」です。
例:
・「噛んだらどうしよう」
・「笑われたらどうしよう」
しかしこれは、実際の失敗ではなく“想像上の失敗”。
脳は架空の不安にも緊張反応を起こすため、本番で過度なドキドキにつながります。
完璧主義による負担
完璧主義の人ほど話すことが苦手になりやすいです。
「ミスなく話さなきゃ」というプレッシャーが緊張を生みます。
例:
「1語でも間違えたら終わりだ」
「プロみたいに話さないと恥ずかしい」
→ これが本番の硬さを招きます。
過去の失敗経験によるブレーキ
昔の発表でミスした経験があると、身体が条件反射的に緊張します。
例:
・頭が真っ白になった経験
・質問で固まった経験
これは“学習された緊張”であり、対処可能です。
「人前で話すとつい緊張してしまう…」そんな方におすすめ。
自宅で簡単にできるトレーニング法をステップごとに解説しています。
プレゼンや面接でも落ち着いて話せる実践メソッドを紹介。
👉 緊張しない話し方を身につける7つのトレーニング法|人前でも落ち着いて話せる実践メソッド
本番前の準備チェックリスト
話すのが苦手な人ほど「準備が足りていない」場合が多く、逆に言えば、準備さえ整えば本番での安心感が大きく変わります。
この章では、人前で話す前に必ず押さえておきたい準備項目を「初心者でも迷わない順番」でチェックリスト化しました。
原稿の作り方、構成の整え方、練習法、想定質問の作り方まで網羅しています。
準備が整えば整うほど、本番の緊張は激減します。
この記事を読みながら、あなた自身の“発表準備シート”として活用してみてください。
話す内容を「結論 → 理由 → 具体例」で整理する
最初から原稿を書くと混乱しやすいので、以下のテンプレが有効です。
✔ 結論
✔ 理由
✔ 具体例
✔ まとめ
例:
結論:伝わる話は構成が大事です。
理由:人は順番が整理されていない話を理解しづらいためです。
具体例:PREP法を使うと迷わなくなります。
まとめ:話す前に構成を作りましょう。
原稿を「読み上げるため」ではなく“練習のため”に作る
初心者は「原稿通りに読もう」とすると噛みます。
原稿は“話すための地図”として使うのが正解。
NG例:
× 一字一句覚えようとする
× 原稿を見る時間が長い
OK例:
〇 見出しだけをメモ化する
〇 5行以内のメモにまとめる
制限時間内に話せるかタイマーで練習する
講師やプロも必ずやる基本です。
例:
5分スピーチ → 120秒で序盤を終える
3分スピーチ → 前半で結論を伝える
本番直前の“緊張対策”チェックリスト
どれだけ準備をしても、本番が近づくと緊張するのは当然のことです。
問題は「緊張をゼロにする」ことではなく、「緊張していても話せる状態に整える」こと。
本章では、プロのアナウンサーや講師も実際に使っている“本番直前の緊張対策”をまとめました。
呼吸、姿勢、声の出し方、会場への入り方など、ちょっとしたコツが驚くほど効きます。
5分前でも効果が出るため、ぜひ本番前に見返してください。
深呼吸より効果が高い「4-2-6呼吸」
4秒吸う → 2秒止める → 6秒吐くのリズムで行う「4-2-6呼吸法」は、副交感神経を活性化し、自律神経のバランスを整えるためのシンプルで効果的な呼吸法です。
特に「吐く息を長くする」ことで心拍が落ち着き、精神的な緊張をやわらげます。
やり方のポイント:
- 背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜く
- 鼻から吸って、ゆっくり口から吐く
- 吸うときはお腹がふくらむ腹式呼吸を意識
- 吐く時は「細く、長く」ゆっくりと
4秒吸う → 2秒止める → 6秒吐く を3回繰り返すだけで、交感神経の高まりが抑えられ、心拍がゆるやかに落ち着きます。
効果の根拠
- ゆっくりと長い呼気が迷走神経を刺激し、副交感神経が優位になる
- 吐く時間が長いほど心拍変動(HRV)が安定し、ストレス耐性が上がる
- 呼吸のリズムへ意識を向けることで「不安の思考ループ」が遮断される
- 腹式呼吸により横隔膜が大きく動き、胸郭が緩むことで脳の緊張も緩和
この複合的な作用により、短時間でも心身がリラックスしやすくなります。
いつ行うと効果的か
- 緊張しやすい場面(会議・本番前・プレゼン前)
- イライラ・不安感が強い時
- 寝る前・起床直後…睡眠の質向上にも◎
- 仕事・勉強の合間のリフレッシュに
- パニック・過呼吸気味になりそうな時(無理のない範囲で)
注意点
- 深く吸いすぎるとめまいが出るので自然な呼吸の延長で行う
- 息を止める時間を無理に伸ばさない
- 食後すぐ・運動直後は避ける
- 呼吸器や心疾患がある場合は医師に相談
- 違和感があればすぐ中止して普段の呼吸に戻す
4-7-8呼吸法との違い
4-2-6呼吸法と比較されることが多いのが、海外でも人気の「4-7-8呼吸法」です。
両者の違いをまとめると以下の通りです。
- 4-2-6呼吸法…吸う4秒/止める2秒/吐く6秒
→ 日常で取り入れやすく、即効性の高いリラックス法。
- 4-7-8呼吸法…吸う4秒/止める7秒/吐く8秒
→ より深いリラックスや睡眠導入に向いているが、息を止める時間が長く、初心者には少しハード。
息を止める7秒が長いと感じる人や、途中で苦しくなる人には4-2-6呼吸法が適性◎
一方、睡眠前にじっくり呼吸を深めたい場合は4-7-8呼吸法も有効です。
ある大学の心理学研究チームが、20〜50代男女60名を対象に「通常呼吸」「4-2-6呼吸法」を比較する実験を行いました。
- 4-2-6呼吸を3分行ったグループは心拍数が平均8%低下
- ストレスホルモンに関連する唾液中アミラーゼが約12%減少
- 呼吸後の自己評価で「不安感が軽減した」と回答した人が78%
- 集中力スコアが10〜15%上昇する傾向も確認
姿勢を整えて“声の出る身体”にする
姿勢が悪いと声が震えます。
✔ 背中を伸ばす
✔ 顎をひく
✔ 足を肩幅に開く
5秒で安定します。
直前に読むべき“3行スクリプト”を準備する
長い原稿は覚えられません。
そこで本番前は以下の3行だけ読みます。
例:
① 今日伝えたい結論
② その理由
③ 最後のまとめ
これで“話す筋道”がリセットされます。
やってはいけないNG集
人前で話すのが苦手な人が失敗する理由の多くは、「やってはいけない行動」を無意識にしてしまっているからです。
これは技術ではなく“癖”なので、途中で直すのは難しいですが、事前に知っていれば簡単に回避できます。
本章では、実際の研修現場や講演でよく見るNG例をまとめ、「なぜダメなのか」「どう直すのか」までセットで紹介します。
特に初心者ほどやりがちな“危険なNG例”も含めてチェックしておきましょう。
4原稿を丸暗記しようとする
失敗率が最も高いNG行動です。
× 一字一句覚えようとする
→ 忘れた瞬間に頭が真っ白に。
早口で話してしまう
緊張すると早口になりますが、聞き手はついていけません。
改善例:
句読点ごとに1秒止まる
語尾をゆっくり出す
アイコンタクトが極端に少ない
視線が泳ぐ → 緊張が伝わる → 空気が固まるという悪循環。
話すのが苦手でも使える具体例(例文つき)
以下は、実際に使える例文を複数パターンご紹介します。
目的やシーンに応じてアレンジして使ってみてください。
最初のあいさつ例
- ビジネスプレゼンで
「皆さま、本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。緊張もありますが、私が伝えたいことを力を込めてお話ししますので、どうぞよろしくお願いいたします。」
- 社内報告で
「本日は進捗報告の機会をいただき、ありがとうございます。簡潔に、しかし正確にお伝えしたいと思います。」
- カジュアルな講演/スピーチで
「こんにちは、〇〇です。今日は私自身も学びながら皆さまと共有したいテーマがあります。どうぞ最後までお付き合いください。」
説明の例(構成化された話し方)
結論 → 理由 → 具体例 → 補足結論 の流れ:
- 結論:「新製品のAは、私たちの業務効率を大幅に改善できます。」
- 理由:「なぜなら、Aは操作が簡単で、従来ツールより学習時間が短いため、多くの部署で導入しやすいからです。」
- 具体例:「たとえば、B部署では導入から1ヶ月で作業時間が20%削減されました」
- 補足結論:「以上より、Aを導入することで短期〜中期的に大きなコストメリットが得られます。」
締めの言葉例
- プレゼン終わり:
「以上で私の説明を終わります。ご質問やご意見があれば、どうぞ気軽にお聞かせください。ありがとうございました。」
- 会議報告終わり:
「それでは本日の報告は以上です。今後の進め方や懸念点など、ご意見があればぜひお聞かせください。」
- 講演/スピーチ終わり:
「最後までお聞きいただき、ありがとうございました。このテーマについて、皆さまの考えやご感想があればぜひお話を伺いたいです。」
NG(やってはいけない)集:準備・本番で失敗しやすいポイント
- 詰め込みすぎたスライド:1ページに大量の文字を入れると、話が埋もれてしまい、聞き手が離れてしまう。
- 原稿をそのまま読み下ろす:書き言葉すぎたり長すぎると、聞き手に伝わりづらくなる。
- リハーサルをしない:練習なしで本番を迎えるのは非常に危険。時間配分や言い回しの改善ポイントを確認する機会を失う。
- マイクや機材チェックを怠る:当日になってから音が出ない、スライドが映らないというトラブルは致命的。
- 自己否定で始まる:「自分は話が下手だ」「どうせ失敗する」と思いながら話すと、そのネガティブな感情が声や表情に出てしまう。
よくある質問(Q&A)
ここでは、人前で話すのが苦手な方から寄せられる「本当に多い悩み」を、実践的な視点でまとめました。
発表の直前や、準備の途中で不安になったときに読み返せば、心がかなり落ち着きます。
どの質問も、単なる精神論ではなく、すぐに使える「具体的な行動」と「テンプレート例文」をセットで紹介しています。
実際の講師やスピーチ指導の現場でも使われている再現性の高い方法なので、初めての人でもそのまま真似するだけでOKです。
また、悩み別に内部リンクも用意しているため、気になるテーマを深掘りしながら自分のペースで学べます。
ぜひ、本番前の“お守り”として活用してください。
Q1. 本番で頭が真っ白になったらどうすれば良い?
最も効果的なのは、事前に用意しておいた 「3行スクリプト」 に戻ることです。
これは「結論 → 理由 → まとめ」という最低限の流れだけを3行で書いておく方法です。
頭が混乱すると、細かい順番や例文を忘れるのは当然。
しかし、話の“柱”さえ思い出せれば何度でも立て直せます。
① 結論:私は〇〇だと考えています。
② 理由:なぜなら、□□という根拠があるからです。
③ まとめ:つまり、△△という点が重要になります。
初対面でも落ち着いて話せる人は、特別な才能があるわけではありません。
この記事では、あがりにくい人が実践している「8つの習慣」を分解しながら、今日から使える具体的なコツを紹介しています。
「人前で話すと緊張してしまう」「初対面が苦手」という方は、こちらの記事も合わせて読むと理解が深まります。
👉初対面であがらない人の共通点8選|堂々と話せる人が必ずやっている準備と習慣
Q2. 声が震えるのを止めたいです
声の震えは「喉が震えている」のではなく、ほとんどが 呼吸の乱れ から来ます。
そこで使えるのが、プレゼン講師もよく使う 4-2-6呼吸法 です。
- 4秒吸う
- 2秒止める
- 6秒吐く
これを2〜3回繰り返すだけで、副交感神経が働き、声の震えが一気に収まります。
(本番前)
4秒吸う → 2秒キープ → 6秒ゆっくり吐く × 2セット
Q3. 相手の視線が怖くて目を合わせられません
全員の目を直接見る必要はありません。
まずは相手の “眉間(みけん)”を見るだけ で大丈夫です。
相手からすると「ちゃんと視線が合っている」と認識されます。
慣れてきたら、眉間 → 口元 → ノート → 聴衆3点(左・中央・右)へと、徐々に範囲を広げると自然なアイコンタクトになります。
視線に困ったら、まず眉間を見る → 次に3人へ順番に視線を送る
Q4. 噛んだり言い間違えたりしたらどうすればいい?
噛むのは誰でもよくあるので、焦らず 「言い直す」か「一度止まる」かの2択 でOKです。
言い間違えを無理に隠そうとすると、かえって不自然になります。
「失礼しました。正しくは〇〇です。」
「少し言い直しますね。□□という意味です。」
Q5. 手が震えて原稿が持てません
手の震えは「体が緊急モード」になっている状態。
もっとも効果的なのは “前腕に力を入れて10秒キープする方法” です。
筋肉がいったん緊張すると、そのあと自然に力が抜けて震えが止まります。
また、原稿は クリップボード に挟むと震えが目立ちません。
前腕にギュッと力を入れる → 10秒 → 脱力 → 原稿をクリップボードで固定
Q6. プレゼンの最初の一言が緊張で出ません
最初の一言だけ 完全暗記 しておくと、立ち上がりがスムーズになります。
「おはようございます。本日は〇〇についてお話しします。」だけでOK。
最初を暗記 → 中盤はスクリプトを見る
というハイブリッド型が最も安定します。
「おはようございます。今日は〇〇について、お話をさせていただきます。」
Q7. 説明が長くなってしまいます。短く話すコツは?
短く話すコツは PREP法を使う こと。
Point(結論) → Reason(理由) → Example(例) → Point(再結論)
この流れで話すと、ダラダラせず5〜20秒にまとまります。
結論:〇〇です。
理由:□□だからです。
例:たとえば△△という事例があります。
結論:つまり〇〇が重要です。
Q8. 練習ではうまく話せるのに本番で崩れます
原因は「練習の環境が本番と違う」こと。
本番で緊張しないためには、練習を“本番化”する必要があります。
- 立って話す
- ストップウォッチを使う
- 録画する
- 人に聞いてもらう
この4つを入れると、本番とほぼ同じ状態で練習できます。
練習:立つ → 録画 → 時間計測 → 人に見てもらう
Q9. 途中で何を話しているか分からなくなります
話が迷子になる人は、原稿ではなく 「見出し(タイトル)」だけを一覧化したスライド を作ると改善します。
話す内容を“地図”として目で確認できるからです。
スライド1:結論
スライド2:理由①
スライド3:理由②
スライド4:まとめ
Q10. 緊張しない人なんて本当にいるの?
「全く緊張しない人」はほぼ存在しません。
違いは 緊張を味方にできているかどうか です。
緊張によって脳が覚醒し、むしろパフォーマンスが上がる人もいます。
大事なのは「緊張しないこと」ではなく “緊張しても話せる状態を作ること” です。
緊張=悪い → ×
緊張=集中力UP → ○
Q11. 本番前にできる“最強の準備”はありますか?
最強なのは 「3分の通し練習×3回」 です。
心理学的にも、短時間×回数のほうが本番で崩れません。
- 3分で全体を軽く通す
- 休憩
- また3分
- 最後に3分
練習量は多くなくて大丈夫。
「脳に流れを刻む」ことが目的です。
3分通し → 休憩 → 3分通し → 休憩 → 最後に3分
Q12. 声が小さい、滑舌が悪いのですが、どう改善すればいいですか?
A. 発声と呼吸の練習を中心に改善できます。
- 腹式呼吸:緊張しているときほど浅い呼吸になりがちです。話す前に深く吸ってゆっくり吐く練習をし、声の土台を安定させましょう。
- 発声練習:リップロールや母音発声(アー、イー、ウー、エー、オー)を朝晩5分ずつ行うことで、滑舌・声量・安定感を高めることができます。
- 速度をコントロールする:普段より少しゆったりめに話すことで、言葉が明瞭になり、聞き手に伝わりやすくなります。語尾の部分(最後の1音)を意識的にしっかり発音すると、聞き取りやすさがアップします。
Q13. 原稿を読むのは本当に良くないですか?
A. 完全に読むのは問題ありませんが、「読む前提の原稿」は注意が必要です。
ポイントは以下の通りです:
- 口語に直す:書き言葉だと硬く聞こえるので、「〜です」「〜ます」など話し言葉に直しましょう。
- 一文を短く:長文は読みづらく、理解されにくいため、短めの文で構成します。
- 視線を使う:原稿を読む場合でも、定期的に顔を上げて聴衆の方を見るようにして、アイコンタクトを取るタイミングを設けます。
このようにすれば、原稿を読むことが「棒読み」にならず、自然で聞き取りやすい話し方になります。
Q14. 場数を踏む以外に上達する方法はありますか?
A. 少人数練習やフィードバックを活用するのが非常に効果的です。
- 友人や家族に向けて話す:2〜3人相手にリハーサルを行い、反応を見ながら話せる経験を積みましょう。
- 録画/録音+自己分析:自分の声や姿を見ることで、改善すべき点(早口・姿勢・間など)が明確になります。
- メンター/コーチの活用:社内や外部でプレゼン経験者にアドバイスを求めるのも有効です。具体的な改善ポイントを指摘してもらうことで、短期間で成長できます。
Q15. 途中で“上がって”しまった時はどうすればいい?
途中で頭が真っ白になって上がった時に最も効果的なのは、
「一度、間(ま)をつくる→1フレーズだけ読み返す」 という流れです。
上がった時、人は「すぐ話さなきゃ」と焦りますが、
実は“沈黙2〜3秒”は相手にはほとんど気づかれません。
むしろ「落ち着いて話している」とさえ見えます。
【対処のステップ】
① 2〜3秒、ゆっくり息を吐いて間を作る
焦って話そうとすると噛みやすくなるため、
一度ゆっくり息を吐くだけで脳の混乱がリセットされます。
② 手元の“次の1行”だけ見る(スクリプトに戻る)
原稿全体を見るとパニックが再燃します。
見るのは たった1行だけでOK。
例:
- 「結論:今日は〇〇をお伝えします」
- 「ポイント①:□□が重要」
1行=話の“起点” になるため、そこから自然に話を戻せます。
③ その1行をゆっくり読んで再スタート
話の流れは多少ズレても問題ありません。
「軌道に戻すこと」が最優先です。
【使えるテンプレート例文】
「少し整理しますね。」
「続いてお伝えしたいのは、〇〇のポイントです。」
「話を戻します。大事なのは□□です。」
※ これらを使うと、不自然な中断が“意図的な間”に見えるため、
聴衆には“上がった”とは気づかれません。
【ワンポイント】
途中で上がる人の多くは、
「話し続けること」が義務だと思っている ことが原因です。
しかし実際には、
プロのアナウンサーでも“間”で立て直すのが普通。
間を味方につけると、むしろ落ち着いて見えます。
まとめ:準備すれば誰でも話せるようになる
話すのが苦手な人が本番で成功するには、
✔ 構成を作る
✔ メモを準備する
✔ 練習する
✔ 緊張対策をする
緊張しない話し方に効果的な本・アプリ紹介
おすすめ本
- 『人前であがらずに話す技術』(講談社)
- 『一瞬で心をつかむ!話し方の教科書』(ダイヤモンド社)
おすすめアプリ
- 「スピーチ練習」アプリ(声の録音・分析機能付き)
- 「メンタルリセット呼吸法」アプリ(呼吸テンポをガイド)
これらを使うと、毎日の練習が継続しやすくなります。
関連記事:ステップ1 呼吸を整える
話し始める前の深呼吸は、緊張をほぐす最も手軽で効果的な方法です。
吸う・吐くのリズムを整えることで、心拍数が落ち着き、思考もクリアになります。
🫧もっと詳しい呼吸テクニックを知りたい方はこちら
👇 スピーチ前に心を整える呼吸テクニック|緊張を味方に変える1分メソッド
👇 【緊張が一瞬で消える】たった30秒で心を落ち着ける呼吸法|面接・プレゼン・人前で緊張しないコツ
関連記事:ステップ2 話す前の準備をしっかり行う
「準備」は、緊張を減らす最大の武器。
話す内容を整理し、イメージトレーニングをしておくことで、「失敗するかも」という不安を軽くできます。
👇初対面であがらない人の共通点8選|堂々と話せる人が必ずやっている準備と習慣
関連記事:ステップ3 声の出し方と姿勢を意識する
声が小さいと自信がないように見えてしまい、さらに緊張が増す悪循環に。
しっかり息を吸って、姿勢を整えながら発声することで、自然と堂々とした印象になります。
「声が震える」「体がこわばる」ときの対処法はこちら
👇 人前で話すときに緊張しない方法|実践できる7つのステップとNG例
👇緊張を一瞬で和らげる正しい姿勢と体の使い方|人前でも震えない体をつくるコツ
関連記事:ステップ4 実際に話す場数を踏む
緊張は「経験」で和らいでいくもの。
少人数の前で話す練習から始めて、自信を積み重ねていくことが大切です。
練習で得られる「本番に強くなるコツ」を知りたい方はこちら
👇緊張しない話し方を身につける7つのトレーニング法|人前でも落ち着いて話せる実践メソッド
関連記事:ステップ5 本番で緊張した時の対処法
どんなに準備しても、本番では緊張してしまうもの。
そんなときは、「詰まっても印象を落とさない話し方」を知っておくと安心です。
🎤スピーチ中に焦らず乗り切るテクニックはこちら
👇スピーチで緊張しても安心!言葉が詰まっても伝わる話し方とプロのテクニック
関連記事:ステップ6 失敗を恐れないマインドを持つ
緊張の原因は「失敗したくない」という思いが強すぎること。
完璧を目指すよりも、「自分の想いを届ける」ことに意識を向けましょう。
緊張しても印象を落とさない方法をもう一度確認したい方はこちら
👇緊張しても伝わる話し方|言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術
関連記事:ステップ7 心の奥にある「緊張の根」を癒す
過去の失敗体験や「人前で恥をかいた」記憶が、無意識に緊張を生み出している場合があります。
そんな心のクセをリセットすると、本番でも驚くほど落ち着けます。
🌱心のブロックを手放したい方へ
👇過去のトラウマを癒す心理リセット法|怖い記憶を手放し「話せる自分」に変わる具体ステップ
あがり症を克服するための最強トレーニング法を徹底解説。
緊張に強くなる習慣、実践しやすい例文、やってはいけないNG行動まで、今日から使える対策をまとめています。
👇
あがり症を克服する最強トレーニング法|緊張に強くなる習慣・例文・NG集つき
呼吸法に加えて“即効性の高い呼吸メソッド”をまとめて知りたい方は、【たった30秒で心が落ち着く。医師も推奨するストレス即リセット呼吸法まとめ】もぜひ参考にしてください。
👇