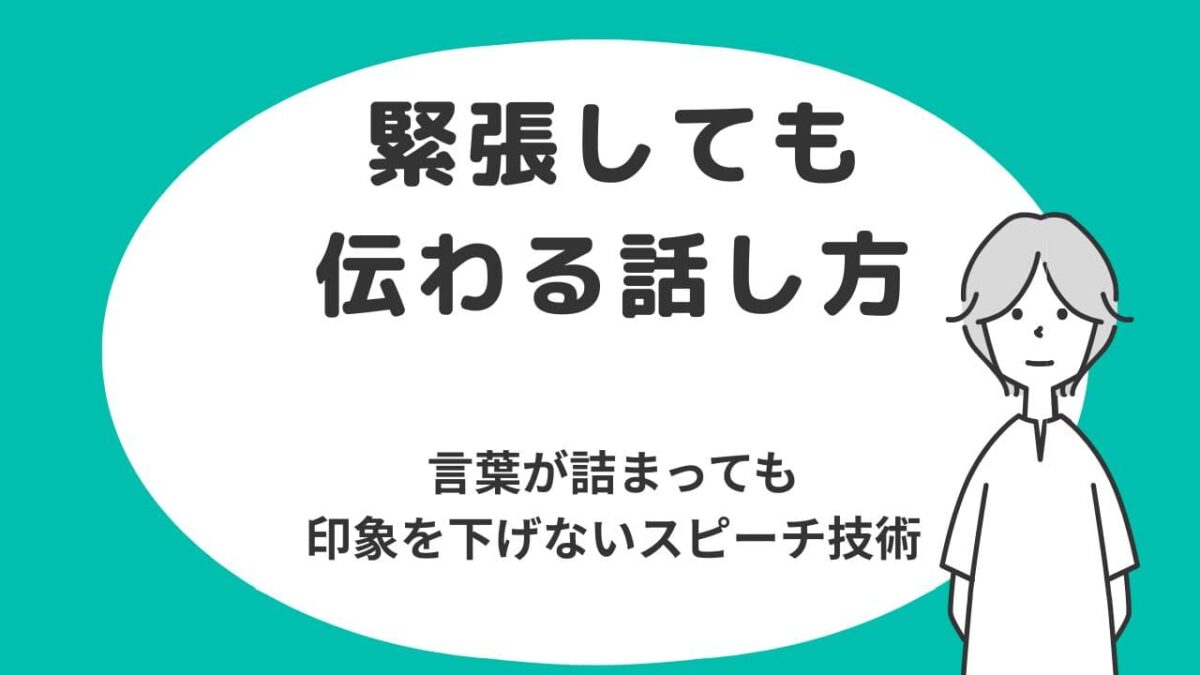大切な場面で、頭が真っ白になったり、言葉が詰まってしまった経験はありませんか?
誰もが緊張するものです。
ですが、「言葉が出ない=印象が悪い」というわけではありません。
実は少しのコツで、緊張しても伝わる話し方がぐっと身につきます。
本記事では、「言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術」を、具体例とともに丁寧に解説します。
ビジネス、友人前、プレゼン、どんな場でも使える実践的な内容です。
ぜひ最後までお読みください。
緊張を完全になくそうとするより、“味方につける”意識が大切です。
緊張をポジティブに変える心の整え方は、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
👉 スピーチ前に心を整える呼吸テクニック|緊張を味方に変える1分メソッド
目次
- 1 緊張しても伝わる話し方とは
- 2 言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術
- 3 緊張を和らげる準備とトレーニング
- 4 聞き手の心をつかむ伝え方のポイント
- 5 話し方が変わると印象が変わる
- 6 よくある質問(Q&A)
- 6.1 Q1. 緊張で声が震えてしまうとき、どうすればいいですか?
- 6.2 Q2. 頭が真っ白になったとき、何と言えばいい?
- 6.3 Q3. 話す内容を忘れたときの再開のコツは?
- 6.4 Q4. 緊張しない人なんて本当にいるの?
- 6.5 Q5. 緊張で声が小さくなってしまいます。どうしたらいい?
- 6.6 Q6. 人前で手が震えるときの対処法は?
- 6.7 Q7. 話している途中で噛んでしまいました。どうすれば?
- 6.8 Q8. 聴き手の反応が薄いとき、どうすればいい?
- 6.9 Q9. プレゼン中に間違いに気づいたときは?
- 6.10 Q10. 話の途中で感情的になってしまうのはNGですか?
- 6.11 Q11. 終わったあとに「ああ言えばよかった」と後悔します…
- 7 NG集(やってはいけない対応)
- 8 まとめ
緊張しても伝わる話し方とは
人前で話すと、どうしても緊張してしまい、「言葉が出ない」「声が震える」「頭が真っ白になる」と感じる方は少なくありません。
ですが、ここで大切なのは「完璧に話す」ことではなく、「しっかり伝える」ことです。
むしろ、緊張しているからこそ伝わる誠実な言葉もあります。
この章では、「うまく話す」ことへのプレッシャーを手放し、「伝える」ことにフォーカスした話し方とは何かを整理します。
そして、緊張をネガティブな感情ではなく“味方に変える”ための心構えについても触れます。
「うまく話す」より「伝える」ことが大切
人は聞き手として、「滑らかに流れる話し方」ばかりを求めているわけではありません。
むしろ、その人の言葉が届いているかが大切なのです。
たとえ言葉が詰まったとしても、「あなたの言葉を届けようとしている」という姿勢が感じられれば、聴き手は好印象を持ちます。
例えば、冒頭で「慣れない場なので、少しゆっくりめに話させてください。」と一言添えることで、その率直さがむしろ信頼に繋がることもあります。
重要なのは流暢さではなく、聞き手への思いです。
聴き手は“完璧な話”より“誠実さ”を求めている
実は、聴き手は“完璧なスピーチ”を期待していません。
むしろ、「自分に届こうとしている話」を求めています。
たとえば、上手に構成されたスライドよりも、微笑みながら語りかける姿勢のほうが記憶に残ることがあります。
話し方教室でも「受講生の話が印象に残るのは、“体験を語った誠実な言葉”」という指摘があります。
緊張で言葉が詰まることを恐れず、「誠実に伝える」ことに切り替えてみましょう。
緊張を味方に変える3つの心構え
緊張をゼロにするのは困難ですが、緊張をコントロールすることは可能です。
以下、心構えを三つ紹介します。
- 【理解】「緊張するのは当然」と自分に言い聞かせる。緊張=私がこの場を大切に思っている証。
- 【受容】「言葉が詰まっても大丈夫」と許可を出す。完璧ではなく、“伝える”を優先。
- 【変換】緊張の“高まり”を「自分のエネルギー」と捉える。手足の震えや心拍の増加も「伝えたい気持ちの高まり」と意識する。
「準備力」は緊張を和らげる最大の武器です。
初対面や人前で堂々と話せる人がどんな準備をしているのか、具体例を知りたい方は以下をご覧ください。
👉 初対面であがらない人の共通点8選|堂々と話せる人が必ずやっている準備と習慣
言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術
話している途中で言葉が詰まったり、頭が真っ白になったり…そんな経験がある方も多いでしょう。
でも、それ自体が“失敗”というわけではありません。
むしろ、詰まった瞬間の対処法が印象を左右するのです。
この章では、言葉が詰まった時にどうするか、沈黙や間をどう使うか、声と姿勢で安心感を伝えるコツ、そして避けるべきNG集まで、具体的な技術を豊富な例文とともに紹介します。
詰まった時は「沈黙」を恐れない
多くの人が言葉に詰まると、つい「えー」「あー」「すみません」と余計なつなぎ言葉を挟んでしまいます。
ですが、実は「沈黙」を短く受け入れて、自分のペースを取り戻すほうが印象がいいことが多いです。
たとえば、本番で「…少々お待ちください」と一呼吸おく、または微笑んで「整理しますね」と言うだけで、聞き手には「落ち着いている印象」が残ります。
例文:
「それでは、次に…(2秒の間)整理して参ります。」
「少し言葉を選びますね。…はい。」
このように一呼吸置くことで、「焦ってない」「次に話す準備をしている」という安心感を与えられます。
「間」を使って信頼感を生む話し方
話に“間”を入れることは、聞き手にとって聞きやすく、話し手にとっても緊張を整える時間になります。
音声トレーニングでも「間」を取ることの効果が紹介されています。
例えば、重要なフレーズを言う前に「(1~2秒の間)」を入れることで聞き手が意識を向けやすくなります。
例文:
「私が最も大切にしていることは、(1秒)“信頼”です。」
「このプロジェクトで学んだことは、(2秒)“挑戦する心”です。」
このように構成上“間”を設けると、言葉が詰まりそうな場面でも自然に聞こえ、むしろ説得力が増します。
詰まった瞬間の“リカバリー例文”
言葉に詰まった瞬間、焦って無理に次に進むと印象ダウンにつながります。
そこで使える“リカバリー例文”をいくつか紹介します。
- 「少し整理しますね。」
- 「お伝えしたいのは、…(間)…こういうことです。」
- 「失礼しました。改めてお話しします。…」
NG例:「あ、あのー…えーっと…」という長いつなぎ言葉。
聞き手に「焦っている」「準備不足」と感じさせてしまう危険があります。
このようなリカバリーをあらかじめ準備しておくだけで、詰まった瞬間も印象を下げずに切り返せます。
声と姿勢で安心感を伝えるコツ
言葉以外の“声”と“姿勢”も重要な印象要素です。
例えば、背筋を伸ばし、ゆっくりとした口調で話すだけで、聞き手に「安心」「信頼感」を与えられます。
スピーチがわかりにくい人の特徴に「一文が長い」「声に抑揚・間がない」というものがあります。
例文:
(姿勢を正しながら)「皆さん、まずはこちらをご覧ください。(間)…この図が示すのは、…”」
声を低め・落ち着いたトーンにして、重要な言葉を少しだけ大きくする“抑揚”を加えるとより効果的です。
また、手を無駄に動かさず「おへその前」あたりに軽く置くと安心感が出ます。
【NG集:避けるべき話し方・言葉】
印象を下げてしまう、よくあるNGをまとめます。
- 長い“えー”“あー”のつなぎ言葉:話が止まって見える。
- 一文が長すぎて「何が言いたいの?」と聞き手が迷う。
- 足を動かす/視線が下を向くなど、不安定な姿勢。
- 内容とは関係ない身振り手振りを常に行う:逆に聞き手をそらしてしまう。
- 声が一本調子/抑揚・間がない:聞き手の集中を奪う。
緊張を和らげる準備とトレーニング
スピーチで緊張を感じても、準備とトレーニングを重ねれば自信に変わります。
この章では、話す前の呼吸法、内容構成の整理法、キーワードメモの使い方、そして録音・録画を活用した練習法まで、段階を追って紹介します。
緊張を感じた瞬間でも、自分を落ち着かせて話す土台を整えておきましょう。
呼吸法で心を整える「4-7-8呼吸法」
緊張すると呼吸が浅くなりがちで、声が震えたり言葉が詰まったりしやすくなります。
そんなときには「4秒吸う → 7秒止める → 8秒かけて吐く」という呼吸法が心を落ち着けるのに有効です。
この呼吸を2~3回行った後に話し始めるだけで、心拍・声の震えが和らぐことが多いです。
例文:
(心の中で)「4…5…6…7(止める)…8…9…10…11…12…13…14…15…16…17…18…」
そして「はい、始めます」と一言。
このような手順を毎回のスピーチ前に習慣化すると、「話す直前=落ち着く合図」として体が反応するようになります。
話す内容を“構造化”して安心感をつくる
せっかく準備した内容も、本番で構成が見えなくなると焦りに繋がります。
そこで役立つのが「結論→理由→具体例→まとめ」という4ステップ構造です。
「私の結論は、“緊張は敵ではなく味方になり得る”です。
理由としては三つあります。まず…(理由1)、次に…(理由2)、最後に…(理由3)。
具体例として、私自身が…(具体例)。
まとめると、…」
このように構造を先に整理しておけば、途中で言葉が飛んでも“どこまで話したか”を思い出しやすくなります。
「息を整える」だけで、緊張は想像以上に軽くなります。
より即効性のある呼吸法を知りたい方は、こちらも参考になります。
👉 【緊張が一瞬で消える】たった30秒で心を落ち着ける呼吸法|面接・プレゼン・人前で緊張しないコツ
原稿を覚えるより「キーワードメモ」で話す
丸暗記形式のスピーチは、一度言葉を失うと修復が難しくなります。
むしろオススメなのは、キーワードだけを書いたメモを手元に置いて話すこと。
例:キーワードメモ
・緊張=準備が物語る
・沈黙を恐れない
・間で聞き手の意識を集中
このシンプルなメモを手元に置いて、話すときは「このキーワードで次何を話すか」を意識します。
もし言葉が詰まっても、「次はこのキーワードから話す」と思えるので安心です。
練習法:録画・録音・第三者フィードバック
話し方を改善するためには、実践後の振り返りが欠かせません。
例えば、自分をスマホで録画し、以下をチェックしてみましょう。
- 一文が長すぎていないか?
- 手ぶり・身振りが適切か?
- 声の抑揚・間・姿勢はどうか?
また、信頼できる第三者に聞いてもらい「ここが印象的だった/ここが聞き取りづらかった」とフィードバックを受けると、自分では気づけないクセも改善できます。
さらに、本番に近い環境(衣装・立ち位置・時間制限あり)で練習することで、緊張慣れにもなります。
聞き手の心をつかむ伝え方のポイント
スピーチで大切なのは「伝えたい」内容だけでなく、「聞き手に届いているか」です。
この章では、聞き手の心に響く伝え方のポイントを紹介します。
冒頭30秒で共感を掴むフレーズ、表情・ジェスチャーによる補強、そして聞き手を巻き込む質問の投げかけまで。
話す内容だけでなく“聞き手との関係”を築く技術も身につけましょう。
最初の30秒で「共感」を生むフレーズ
スピーチの冒頭は、聞き手の意識が最も高く、興味がつきやすい時間帯です。
ここで「あなたもこんな経験はありませんか?」という共感を生む問いかけを入れると、聞き手の関心を引きつけられます。
例文:
「皆さん、“大勢の前で話すと、体が震えた”という経験はありませんか?」
「緊張で言葉が出なくなったこと、覚えていますか?」
こうした問いかけを入れるだけで、「あ、自分のことだ」と聞き手のアンテナが立ちます。その後に「実は私もそうでした」と続けると、話し手への親近感が生まれます。
表情・ジェスチャーで説得力を補う
話し方で忘れがちなのが、言葉以外の“表情・身振り手振り”です。
聞き手は視覚的な情報を無意識に受け取っています。
例えば、笑顔で「本当にありがとうございます」と言えば、言葉だけよりも信頼が増します。
例文:
(手をおへその前で軽く組みながら)「この機会を頂けたこと、心から感謝しています。」
また、2つのポイントを説明する際に、左手を少し開いて“ポイント1”を示し、右手を少し開いて“ポイント2”を示すと、聞き手の理解も深まります。
聴き手に質問を投げかけて“空気を変える”
スピーチを“一方通行”にせず、聞き手を巻き込むことで、場の空気が活気づきます。
例えば「~と思う方、手を挙げてください」といった簡単な問いかけを入れるだけで、聞き手の意識がこちらに向きます。
例文:
「このテーマに『ええ、私も』と思われた方、挙手をお願いします。」
「そう感じたことがある方、2秒間だけその時の表情を思い出してみてください。」
こうした参加型の問いかけを入れることで、聞き手が受け身ではなく能動的になります。その結果、あなたの話し方にも“伝わりやすさ”という成果が現れます。
話し方が変わると印象が変わる
人前で話すという行為は、ただ情報を伝えるだけでなく、あなた自身の印象を残す機会でもあります。
話し方を少し変えるだけで、「緊張していたけど伝わった」「誠実だと感じた」と思われる印象に大きく変わります。
この章では、緊張を“弱点”ではなく“誠実さ”に変える考え方と、どんな場面でも活きる「伝えたい気持ち」の重要性についてお伝えします。
緊張を“弱点”ではなく“誠実さ”に変える
例えば、スピーチの出だしで「少し言葉を選びながらになりますが、正確にお話しします。」と正直に伝えると、「この人は真剣なんだ」と聴き手に伝わります。
言葉が詰まることを恐れるあまり、無理をして滑らかに話そうとするより、誠実に伝えようとする態度の方が聞き手の印象には残ります。
緊張を「伝えたい気持ちの裏返し」と捉えてみましょう。
それが、聞き手にとって“あなたの言葉”として響くのです。
「伝えたい気持ち」が何よりも大切
テクニックも練習も大切ですが、最終的に話し手の印象を左右するのは「この人は私に何かを伝えようとしている」という熱量です。
たとえ言葉が詰まっても、聞き手がその熱量を感じれば、内容以上に信頼が生まれます。
逆に、流暢に話しても「ただ伝えている」だけでは印象が薄くなりがちです。
スピーチ前に「私の言葉を誰に届けたいか」「この話を通じて相手にどうなってほしいか」をイメージしてから臨むと、言葉の一本一本が力を持ちます。
実は、緊張を和らげるには「心」だけでなく「体」も重要です。
正しい姿勢と体の使い方を身につけると、自然と自信が出てきます。
👉 緊張を一瞬で和らげる正しい姿勢と体の使い方|人前でも震えない体をつくるコツ
よくある質問(Q&A)
スピーチやプレゼンの場で、誰もが一度は感じる「緊張」「言葉が詰まる」「何を話すか忘れる」などの不安。
この記事を読んでくださっている方の多くも、「どうすれば自然に話せるのか」「失敗したらどうしよう」と悩んでいることでしょう。
ここでは、実際に多く寄せられる質問をもとに、具体的な対処法・テンプレート・心理的なコツをセットで解説します。
どんなに緊張しても、“あなたの想いがきちんと届く”話し方を、ひとつずつ身につけていきましょう。
Q1. 緊張で声が震えてしまうとき、どうすればいいですか?
A. 声の震えは、ほとんどが「呼吸の浅さ」と「体のこわばり」が原因です。
スピーチ前に「4-7-8呼吸法」(4秒吸う→7秒止める→8秒吐く)を2~3回行いましょう。
また、話すときはおへその前で手を軽く組む姿勢にすると、体幹が安定して声がブレません。
視線を聴き手の“目ではなく口元”に向けると緊張が和らぎ、自然に落ち着いた印象になります。
テンプレート例文:
「少しドキドキしていますが、伝えたいことがたくさんあります。しっかりお伝えしたいと思います。」
この一言で“誠実さ”が伝わり、聴き手の心があなたの味方になります。
Q2. 頭が真っ白になったとき、何と言えばいい?
A. 無理に言葉を続けようとするほど焦りが増します。
そんな時は一呼吸おいて、正直に「少し整理しますね」と伝えるだけで印象は大きく変わります。
聴き手は“完璧な話”よりも、“一生懸命伝えようとする姿”に共感します。
テンプレート例文:
「すみません、少し整理しますね。(1秒の間)改めて…」
このように言うと、自然に呼吸が整い、再開しやすくなります。
Q3. 話す内容を忘れたときの再開のコツは?
A. 一瞬内容を飛ばしても、焦らず「つなぎ言葉」を使えば問題ありません。
おすすめは、「たしか…先ほどの話に関連して言うと…」のように、“考えながら話している”印象を与える言葉です。
さらに、話す途中でキーワードメモを見直す癖をつけておくと安心です。
テンプレート例文:
「たしか、少し前に触れた通りですが…ポイントとしては…」
自然な流れで再開でき、聴き手も違和感を持ちません。
練習を重ねるほど、緊張は“慣れ”によって和らぎます。
具体的なトレーニング法をステップで知りたい方はこちら。
👉 緊張しない話し方を身につける7つのトレーニング法|人前でも落ち着いて話せる実践メソッド
Q4. 緊張しない人なんて本当にいるの?
A. 実際にはほとんどの人が緊張しています。
有名な講演家やアナウンサーでさえ「毎回少し緊張する」と言います。
大切なのは、“緊張しないこと”ではなく、“緊張しても伝えられる自分”になること。
小さな発表や友人との会話の中でも成功体験を積み重ねると、少しずつ緊張が“味方”になります。
テンプレート例文:
「お聞き苦しい点があるかもしれませんが、最後までお付き合いいただければ幸いです。」
誠実さと熱意を同時に伝えることができます。
Q5. 緊張で声が小さくなってしまいます。どうしたらいい?
A. 声が小さくなる原因は「息を止めて話している」ことにあります。
話す前に“息を吐きながら声を出す”意識を持つだけで、声量は安定します。
また、背筋を伸ばし、顎を軽く引くことで自然と声が通ります。
テンプレート例文:
「皆さんにしっかりお届けしたいと思います。」
この一文を“少しゆっくり・はっきり”言うと、自信が伝わります。
Q6. 人前で手が震えるときの対処法は?
A. 手の震えは「余った緊張エネルギー」が原因です。
話す前に両手を軽く握って5秒キープし、ゆっくり開くストレッチを3回行ってください。
また、手元にペンやマイクを持っていると、震えを隠す効果があります。
テンプレート例文:
「手元に少し力が入っていますが、落ち着いてお伝えしますね。」
自然体の一言で、聴き手の緊張もやわらぎます。
Q7. 話している途中で噛んでしまいました。どうすれば?
A. 噛んでしまっても慌てず笑顔で受け流しましょう。
「すみません、ちょっと緊張してますね」と一言添えると場が和みます。
無理に言い直すより、“ユーモアで流す”方が印象が良くなります。
テンプレート例文:
「ちょっと今、舌が追いつきませんでした(笑)。もう一度だけ。」
このような返しは“人間味”を感じさせ、場を明るくします。
Q8. 聴き手の反応が薄いとき、どうすればいい?
A. 無表情な反応に焦るのは自然ですが、多くの場合“集中して聞いているだけ”です。
表情ではなく「うなずき」「メモ」を観察しましょう。
一方的になっていると感じたら、質問を投げかけて空気を変えるのが効果的です。
テンプレート例文:
「ここまでで、皆さんの中でも似た経験はありますか?」
一言で空気が動き、聴き手との距離がぐっと縮まります。
Q9. プレゼン中に間違いに気づいたときは?
A. 間違いに気づいても、すぐに訂正せず「流れの中で補足」しましょう。
途中で止めて訂正するとテンポが崩れます。
後半で「先ほどの部分を補足しますね」と伝えるだけで十分誠実です。
テンプレート例文:
「先ほど一部言葉を補足します。正しくは~です。」
誠実な印象を残し、信頼を損ないません。
Q10. 話の途中で感情的になってしまうのはNGですか?
A. 感情がこもるのは悪いことではありません。
ただし、涙声や怒りに近い声になってしまうと、聴き手が内容に集中しづらくなります。
「一度深呼吸して、声のトーンを落とす」と冷静さが戻ります。
テンプレート例文:
「少し感情が入りましたが、それだけ大切なことだと感じています。」
感情を認める言葉に変えることで、誠実な印象を保てます。
Q11. 終わったあとに「ああ言えばよかった」と後悔します…
A. ほとんどの人が経験します。
完璧を求めるほど反省が残りますが、“伝えようとした気持ち”こそが一番大切です。
終わったあとに「3つ良かった点」をノートに書き出すと、次に生かせる前向きな習慣になります。
テンプレート例文:
「今日はすべて言い切れませんでしたが、大切な部分はお伝えできたと思います。」
このように自分を肯定して締めると、話すことへの自信が続きます。
本番中に言葉が詰まっても、印象を落とさずリカバリーする方法があります。
👉 スピーチで緊張しても安心!言葉が詰まっても伝わる話し方とプロのテクニック
NG集(やってはいけない対応)
| 状況 | NG対応 | 改善例 |
|---|---|---|
| 言葉が詰まった時 | 無言で焦って笑う | 「少し整理しますね」と一言添える |
| 噛んだ時 | 「あ、間違えました!」と慌てる | 「ちょっと今、早口でしたね(笑)」 |
| 聴き手が無表情 | 必死に早口で説明 | 「ここまでで質問はありますか?」と余白を作る |
| 緊張で声が震える | 「すみません」と連呼 | ゆっくり呼吸して一拍おく |
「うまく話せなかった」と落ち込むより、自分を責めずに心を癒すことが大切です。
過去の失敗やトラウマをリセットする具体的なステップは、こちらの記事で解説しています。
👉 過去のトラウマを癒す心理リセット法|怖い記憶を手放し「話せる自分」に変わる具体ステップ
まとめ
緊張して言葉が詰まる――それは決して“失敗”ではありません。
むしろ、その瞬間をどう受け止め、どう対応するかが印象を大きく左右します。
今回ご紹介したように、沈黙を恐れず、間を使い、声と姿勢で安心感を与え、構造化とキーワードメモで準備を整え、そして聞き手との共感を意識すれば、「緊張しても伝わる話し方」は誰でも身につけられます。
あなたの言葉を聞き手に届けるために。
今日から少しずつ、緊張を味方に変える話し方に取り組んでみてください。
誠実に、そして自信をもって。
関連記事:ステップ1 呼吸を整える
話し始める前の深呼吸は、緊張をほぐす最も手軽で効果的な方法です。
吸う・吐くのリズムを整えることで、心拍数が落ち着き、思考もクリアになります。
🫧もっと詳しい呼吸テクニックを知りたい方はこちら
👇 スピーチ前に心を整える呼吸テクニック|緊張を味方に変える1分メソッド
👇 【緊張が一瞬で消える】たった30秒で心を落ち着ける呼吸法|面接・プレゼン・人前で緊張しないコツ
関連記事:ステップ2 話す前の準備をしっかり行う
「準備」は、緊張を減らす最大の武器。
話す内容を整理し、イメージトレーニングをしておくことで、「失敗するかも」という不安を軽くできます。
👇初対面であがらない人の共通点8選|堂々と話せる人が必ずやっている準備と習慣
関連記事:ステップ3 声の出し方と姿勢を意識する
声が小さいと自信がないように見えてしまい、さらに緊張が増す悪循環に。
しっかり息を吸って、姿勢を整えながら発声することで、自然と堂々とした印象になります。
「声が震える」「体がこわばる」ときの対処法はこちら
👇 緊張で声が震える原因と防ぐ方法|本番で落ち着いて話すための準備と対処法
👇緊張を一瞬で和らげる正しい姿勢と体の使い方|人前でも震えない体をつくるコツ
関連記事:ステップ4 実際に話す場数を踏む
緊張は「経験」で和らいでいくもの。
少人数の前で話す練習から始めて、自信を積み重ねていくことが大切です。
練習で得られる「本番に強くなるコツ」を知りたい方はこちら
👇緊張しない話し方を身につける7つのトレーニング法|人前でも落ち着いて話せる実践メソッド
関連記事:ステップ5 本番で緊張した時の対処法
どんなに準備しても、本番では緊張してしまうもの。
そんなときは、「詰まっても印象を落とさない話し方」を知っておくと安心です。
🎤スピーチ中に焦らず乗り切るテクニックはこちら
👇スピーチで緊張しても安心!言葉が詰まっても伝わる話し方とプロのテクニック
関連記事:ステップ6 失敗を恐れないマインドを持つ
緊張の原因は「失敗したくない」という思いが強すぎること。
完璧を目指すよりも、「自分の想いを届ける」ことに意識を向けましょう。
緊張しても印象を落とさない方法をもう一度確認したい方はこちら
👇緊張しても伝わる話し方|言葉が詰まっても印象を下げないスピーチ技術
関連記事:ステップ7 心の奥にある「緊張の根」を癒す
過去の失敗体験や「人前で恥をかいた」記憶が、無意識に緊張を生み出している場合があります。
そんな心のクセをリセットすると、本番でも驚くほど落ち着けます。
🌱心のブロックを手放したい方へ
👇過去のトラウマを癒す心理リセット法|怖い記憶を手放し「話せる自分」に変わる具体ステップ
あがり症を克服するための最強トレーニング法を徹底解説。
緊張に強くなる習慣、実践しやすい例文、やってはいけないNG行動まで、今日から使える対策をまとめています。
👇
あがり症を克服する最強トレーニング法|緊張に強くなる習慣・例文・NG集つき
呼吸法に加えて“即効性の高い呼吸メソッド”をまとめて知りたい方は、【たった30秒で心が落ち着く。医師も推奨するストレス即リセット呼吸法まとめ】もぜひ参考にしてください。
👇
たった30秒で心が落ち着く。医師も推奨する“ストレス即リセット呼吸法”まとめ