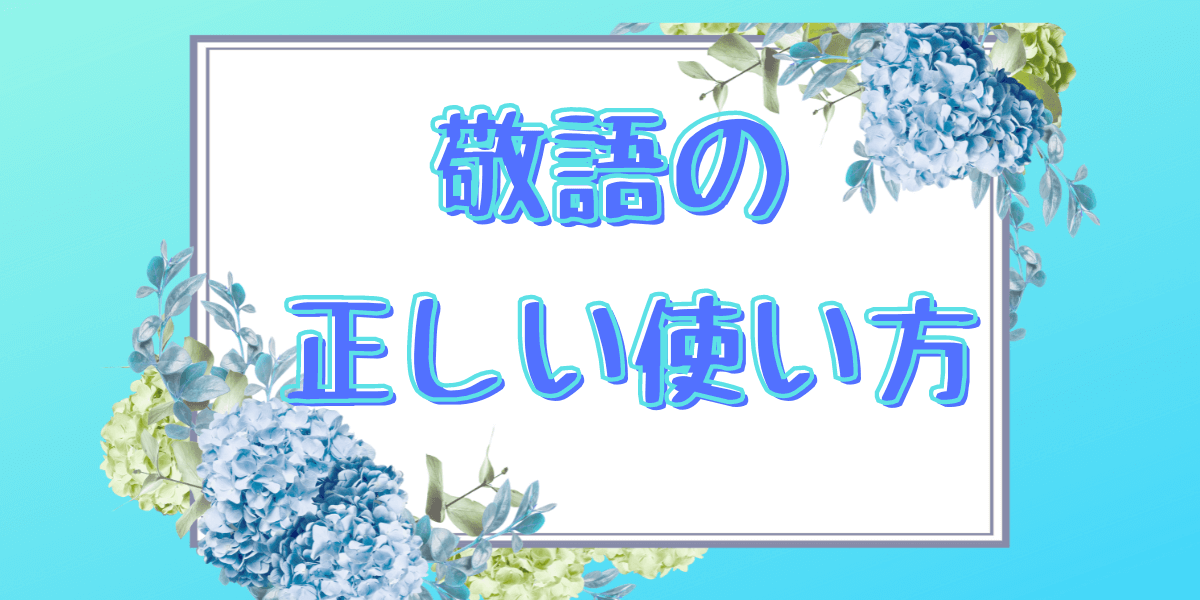この記事では、
敬語の正しい使い方やマナーを解説します。
敬語を正しく使うことで、
周囲との人間関係や信頼関係を築くためには、
敬語を正しく使えることは重要だと言えるでしょう。
敬語が正しく使えなければ、
仕事上でのやりとり以前に、
周囲との人間関係や信頼関係を築く事が
困難になる場合もあるかもしれません。
ビジネスシーンにおいては適切な言葉遣いがあり、
正しく使えることは、重要だと言えるでしょう。
敬語に苦手意識のある人は、実に7割とも言われています。
「丁寧な言葉づかいをしなければいけない」という意識が
強すぎるせいか、かえってくどく聞こえることもあります。
それは、話し言葉でも書き言葉でも同じこと。
ここでは間違いやすい表現について、確認してみましょう!
目次
敬語とは
敬語は、口語や文書などで言葉を表現する場合、
その当事者同士の上下関係を、言葉で表現するために
用いられる語法です。
つまり相手を敬う気持ちを示す方法として敬語が存在します。
敬語を正しく使用する事は、
現代社会においてとても大切なマナー。
また、ビジネスシーンのみならず、
日常生活など様々な環境において人間関係の基本となります。
正しく理解し、使うことで、社会人として
恥ずかしくないマナーを身につけておきたいものです。
敬語の種類
それでは、敬語の5分類の型を説明します。
1.尊敬語:「いらっしゃる・おっしゃる」型
2.謙譲語1:「伺う・申し上げる」型
3.謙譲語2(丁重語):「参る・申す」型
4.丁寧語:「です・ます」型
5.美化語:「お酒・お料理」型
「美化語」は、
「お手紙用の便箋」などのように、
ものごとを美化して述べるものです。
しかし、「私のお電話番号は9999-9999です」
「このところお休みがとれずお肌の調子が悪くて」。
など、
自分だけに関する事柄に「お」や「ご」を
付けすぎるのは不自然と感じる人も多いもの。
いくら美化語のつもりで使っている言葉でも、
中には相手側の尊敬語としてしか使わない言葉もありますので、
使いすぎにも注意して、適切かつ正しい言葉で表現しましょう。
敬語を使うにあたっての注意点
社外の方には全て敬語
来客や顧客など、
社外の方に対しては全て敬語で対応します。
例:「いらっしゃいませ、どうぞご案内いたします。」
社外の方への上司の説明にはNO敬語
社外の方と話す場合、
自分の上司などに関しての話題に敬語は使いません。
例:「部長の○○(苗字のみ)を紹介します」
例:「その件は課長の○○(苗字のみ)が説明します」
社内では目上の人に対しては全て敬語
社内では、上司や先輩に対しては敬語で、
また同僚には丁寧語を使うように心がけましょう。
例:「部長がおっしゃったように、資料をご覧ください。」
社内での身内の話はNO敬語
上司や同僚、顧客などに対して、
両親や兄弟など自分の家族を
話題にする場合、敬語は使いません。
例:「母が上京します。」
例:「父が事故に遭いました。」
顧客や他社についての話題は全て敬語
顧客や他社を話題にする場合は、
どのような状況でも敬語を使います。
例:「先方の担当者からご提案をいただきました。」
例:「A社の○○様とおっしゃる方からお電話がありました。」
相手の動作にはNO謙譲語
(誤)詳細は担当者に伺ってください。
(正)詳細は担当者にお尋ねください。
(正)詳細は担当者にお聞きください。
(誤)プレゼンの資料は3階で拝見してください。
(正)プレゼンの資料は3階でご覧になってください。
(正)プレゼンの資料は3階でご覧ください。
謙譲語を尊敬語のように使わない
(誤)経理部で旅費をいただかれてください
(正)経理部で旅費をお受け取りください
例
(誤)不明な点は私にお伺いください
(正)不明な点は私にお尋ねください
身内に敬語を使わない
(誤)課長は、ただ今、席を外していらっしゃいます。
(正)課長は、ただ今、席を外しております。
恥をかかない敬語表現と正しい使用例
間違いやすい表現「○○様でございますか」
「ございます。」は、
自分のことやモノについていうときに用います。
相手のことについて話す(書く)ときには
「いらっしゃいます。」を用いましょう。
(誤) 田中さんのご出身はどちらでございますか。
(正) 田中さんのご出身はどちらでいらっしゃいますか。
(正) わたくしの実家は静岡市内にございます。
例
(誤) 山田さんのご子息はスポーツ万能でございますね。
(正) 山田さんのご子息はスポーツ万能でいらっしゃいますね。
二重敬語に気をつけて、くどく聞こえる表現をスッキリと
(誤) 先日、お義母さまがおっしゃられたお話ですが、
(正) 先日、お義母さまがおっしゃったお話ですが、
例
(誤) 先日、お義母さまがお話しになられました。
(正) 先日、お義母さまがお話しになった。
例
(誤) お酒をお召し上がりになられますか。
(正) お酒を召し上がりますか。
「〜させていただきます」の使いすぎ
「できるだけ丁寧に言いたい。」「言わなければならない。」ときに、
つい使ってしまいがちなのが「させていただく」という表現。
これは本来、相手の許可や依頼を得て
何かをするときにつかわれる言葉です。
たとえば、芸能人が結婚を報告するときに、
「かねてよりお付き合いさせていただいておりました△△さんと…」
という言い方をしますが、世間の許可を得てお付き合いしていた
わけではないのですから、正しい言い方とはいえません。
その一方で、結婚式の招待状の返事に、
「出席させていただきます」とするのは間違いではありません。
なぜなら、相手からの出席依頼を受けて、相手の厚意により、
出席させていただくのですから、ふさわしい使い方といえます。
ビジネスシーンで、
「このたび弊社で開発させていただいた新商品ですが、
先日ご報告させていただいたように、当初予定より
時期を早めて発売させていただくことになりました。」
などは耳障りに聞こえますから、要注意!
(誤) ご説明させていただきます。
(正) ご説明いたします。
(正) 説明いたします。
例
(誤) 宅建に合格させていただきました。
(正) 宅建に合格いたしました。
例
(誤) 保彦さんとは3年ほどお付き合いさせていただいております。
(正) 保彦さんとは3年ほどお付き合いしております。
*「さ入れ言葉」は過剰敬語ではなく誤り
(誤) 書かさせていただきます。
(正) 書かせていただきます。
まとめ
この記事では、
敬語の正しい使い方やマナーを解説しました。
コミュニケーションを、
良好にするためにとても大切な語法となる敬語。
ただし、正しい使い方をしなければ
かえって相手を敬う気持ちにはつながらず、
失礼にあたる場合もあるかもしれません。
それぞれの特徴や目的を理解し、状況ごとに
判断して正しい使い分けが出来ると良いでしょう。